出産のために会社を休んだ際には、収入の減少を補う目的で「出産手当金」が支給されます。
ただし、出産手当金を受け取るには条件を満たさなければなりません。
「自分は出産手当金を受け取れるの?」「受け取る際にはどのような点に注意する必要がある?」など、悩む人もいるのではないでしょうか。
この記事では、出産手当金を受け取るための条件や、受け取る際の注意点を紹介します。
- 出産手当金の概要
- 出産手当金を受け取れないケース
- 出産手当金を受け取る際の注意点
※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
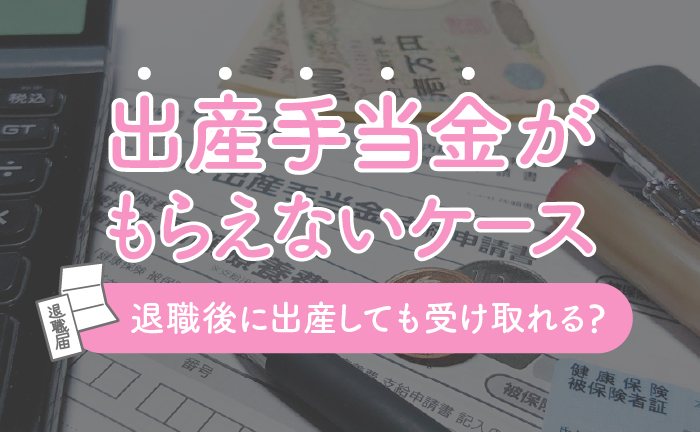
【監修】株式会社RKコンサルティング河合 克浩

一般企業、外資系金融機関を経て、現在はファイナンシャルプランナー(FP)として年間150件超のお金の相談に対応。難しく感じる経済やお金の話をわかりやすく説明することに定評がある。夢を実現するため相談者に寄り添い、人生が豊かになるサポートを心がけている。
出産のために会社を休んだ際には、収入の減少を補う目的で「出産手当金」が支給されます。
ただし、出産手当金を受け取るには条件を満たさなければなりません。
「自分は出産手当金を受け取れるの?」「受け取る際にはどのような点に注意する必要がある?」など、悩む人もいるのではないでしょうか。
この記事では、出産手当金を受け取るための条件や、受け取る際の注意点を紹介します。
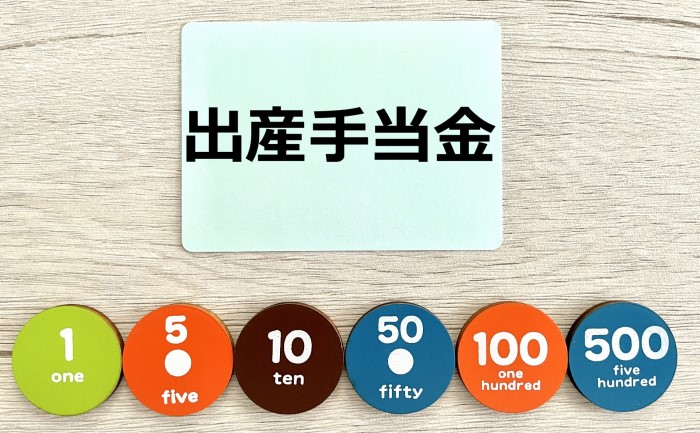
出産で会社を休み、その間の給与の支払いがない場合には、一時的な収入の減少を補う目的で、休んだ期間に応じた出産手当金が加入している健康保険から支給されます。
出産手当金を受け取るには、条件を満たす必要があります。対象者の条件は、以下の通りです。
・勤務している会社の健康保険に加入している
・出産のために産前および産後休業を取得している
・出産が妊娠4ヵ月(85日)以後である
1日当たりの支給額:(出産手当金の支給開始日以前12ヵ月の標準報酬月額平均額÷30日)×2/3(※産前産後休暇期間にあたる日数分支給)
1.加入している健康保険から出産手当金支給申請書を受け取る
2.申請書に本人および医師が必要事項を記入し、産後休業明けに会社に提出する
3.事業主が受け取った申請書に必要事項を記入し、健康保険の窓口に提出する
申請後、約1~2ヵ月で指定口座に振り込み
出産日の42日前から出産日後56日まで
注意したいのは、申請期限が2年となっていることです。産前産後休暇が終了した時点で申請を行いましょう。
出産手当金については、こちらの記事『出産手当金とは?支給条件・支給額や申請方法』も参考にしてください。

中には、出産手当金がもらえないケースもあります。もらえると思っていたのに実際はもらえないといった状況に陥ることのないように、もらえないケースをしっかりと確認しておきましょう。
出産手当金は、勤務先の健康保険組合など社会保険に加入している被保険者が受け取れます。したがって、会社の健康保険組合の被保険者以外は対象外です。
国民健康保険には出産手当金に相当する制度は設けられていないため、自営業者や個人事業主などで国民健康保険の被保険者になっている場合は、出産手当金を受け取れない点に注意しましょう。
会社の健康保険組合に加入していたとしても、被保険者の配偶者で、専業主婦などの被扶養者に該当する場合は支給の対象外です。
また、専業主婦でなく、パートやアルバイトなどで収入があったとしても、所得が少なく被扶養者になっている場合も対象外です。
対象者はあくまでも「被保険者」であるため、夫(被保険者)の扶養に入っている場合は、対象になりません。
会社を退職して「任意継続制度」を利用している場合は対象外です。
健康保険任意継続制度とは、会社を退職したあとも健康保険に一定期間加入できる制度です。国民健康保険よりも手厚いサービスが受けられるため、加入している人も多く見られます。
任意継続制度に加入している場合、健康保険の主な制度は利用できるものの、出産手当金は対象外となっています。
任意継続被保険者は出産手当金の対象外ですが、以下の条件に当てはまる場合に限り受給できます。
産休および育休中に会社から給与の支払いがある場合は、出産手当金を受け取れません。
出産する女性に対して産休を取得させることは、事業主に義務づけられていますが、休業中の給与の支払いについては会社の規定によります。中には休業中であっても給与を支払う企業もあります。
ただし、給与が支払われていても、その額が出産手当金の額よりも少ない場合は、その差額を受け取れます。
出産手当金は自分で申請する必要があり、申請期限があります。
期限は「出産のために休業を取り始めた日から2年以内」となっており、最後に休んだ日から2年以内ではない点に気をつけましょう。
申請は、産前および産後分をまとめて申請する方法と、分けて申請する方法がありますが、分けて申請する方が早く受け取れます。早く受取りたいなら、産前に出産予定日までの分を申請するか、出産後すぐに出産日までの分を申請するようにしましょう。
有給休暇を使っている場合は、会社から給与が支払われている状態になるので、出産手当金を受け取れる条件に該当しません。産休中に有給休暇を使った場合、その有給休暇によって給与を受け取った日数分の出産手当金は支給されないことになります。
産休中に有給休暇を利用する場合は、適用される期間が短くなる点に注意してください。

前述の通り、基本的には扶養に入っている場合は出産手当金の支給対象外となります。
ただし、出産を機に退職し、夫の健康保険の被扶養者になったとしても、出産手当金がもらえる可能性があります。具体的には、以下の条件を満たすことで出産手当金を受け取れます。
これらは、どちらかではなく両方の条件を満たす必要がある点に注意しましょう。
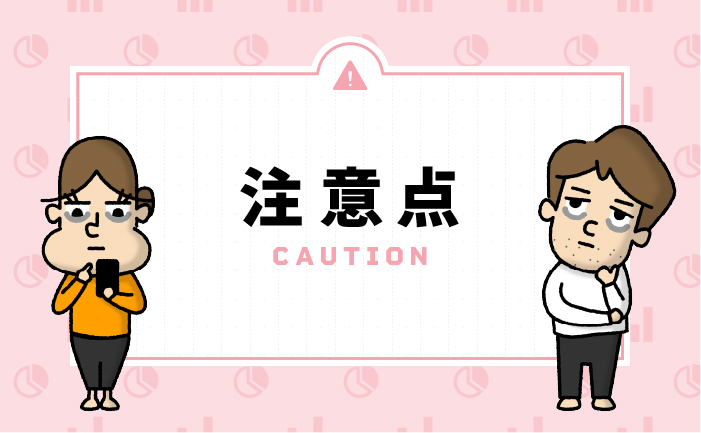
退職後に出産手当金を受け取る際には以下の点に注意しましょう。
退職日に勤務した場合、継続給付を受ける要件を満たさなくなります。そのため、退職日の翌日以降の出産手当金が支払われなくなる点に注意が必要です。
退職にあたり、会社に挨拶に行こうと考える人もいるかもしれませんが、その場合は出産手当金の支給期間が終わったあとにするなど調整しましょう。どうしても挨拶等のために出社しなければならない場合でも、会社に「勤務」扱いにしないよう確認しておきましょう。
退職日が出産手当金の支給期間に当てはまらない場合、出産手当金は受け取れません。そのため、退職日は必ず出産手当金の支給期間に設定するようにしましょう。
出産手当金の支給期間は、原則として出産日前42日から出産後56日です。ただ、出産予定日よりも遅れて出産した場合は、出産予定日から出産日までの日数が加算されます。
計算間違いで出産手当金を受け取れないといった状況に陥らないよう、自分が受け取れる出産手当金の支給期間を確認し、その期間内に退職日を設定することが大切です。

子どもの教育費は高額なため、どのように捻出すればいいのか悩む人もいるでしょう。教育費を貯めるために行うべきことは、以下の通りです。
まずは、子どもの教育方針や進路について夫婦で話し合いましょう。
夫婦間で認識が違うというケースは多いです。高校まで公立に通わせるのか、中学から私立にするのかでは必要な費用は大きく変わってきます。
幼稚園から大学までの学費の平均は、下表の通りです。
| 私立 | 国公立 | |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 約92万7000円 | 約49万8000円 |
| 小学校 | 約1000万2000円 | 約211万8000円 |
| 中学校 | 約431万1000円 | 約161万7000円 |
| 高等学校 | 約316万5000円 | 約153万9000円 |
| 大学 | 文系:約363万8000円 理系:約497万6000円 |
約242万6000円 |
家計管理の方法の見直しとは、現状の収入と支出のバランスを把握し、教育費用として貯蓄できる余裕があるか、なければどこか節約できる箇所がないかを確認することです。
まず、どのくらいの貯蓄額が必要なのかを決め、それに近づけるためには毎月どのくらいの貯蓄が必要か、そのために節約できることはないか考えましょう。そのうえで、生活に必要な支出に優先順位をつけるとともに、無駄な支出がないかチェックしてください。
無駄な支出を見直すためには、通信費などの固定費の見直しが効果的です。携帯電話のキャリアを変えるだけでも節約になる可能性もあるので、検討してみることをおすすめします。
固定費を節約するためのアイデアをもっと詳しく知りたい方は、『家計の見直しはどこから始める?節約のポイントや具体例を解説』をご覧ください。より具体的な節約方法が紹介されています。
資産形成とは、長期間に渡って資産を増やしていくことです。そのための手段として、株式や債券、投資信託といった投資が挙げられます。超低金利が続くいま、預貯金ではほとんどお金が増えないですが、投資なら効率よく貯めていくことができます。
注意すべきなのは、長期的な視点で行うことです。前述したように、特に大学進学には多額の費用がかかるため、早い時期から準備していくとよいでしょう。
教育費用を貯める方法としては学資保険もありますが、返戻率が低いことやインフレに対応できないという理由から、あまりおすすめできません。詳しくはこちらの記事『学資保険をおすすめしない理由』も参考にしてください。
教育費用の捻出に悩んだ際には、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談もおすすめです。FPには家計の見直しや教育資金の準備方法のほか、資産運用、税金対策など幅広い分野での相談が可能です。
資金計画については、夫婦でしっかりと話し合いながら決めていくことが大切です。自分たちだけではお金の悩みを解決できないと感じた際には、早めにFPに相談するようにしましょう。

出産手当金の対象者は、会社の健康保険の被保険者です。そのため、退職などで被保険者の扶養に入った場合など、要件を満たさないケースでは受け取れない点に注意が必要です。ただし、退職した場合でも受け取れる可能性もあるので、しっかりと確認したうえで申請するようにしましょう。
出産手当金は、出産によって会社を休んだ際の給与の支払いを補填する役目を持っています。申請には期限があるので、早めに申請することも忘れないようにしてください。
キーワードで記事を検索