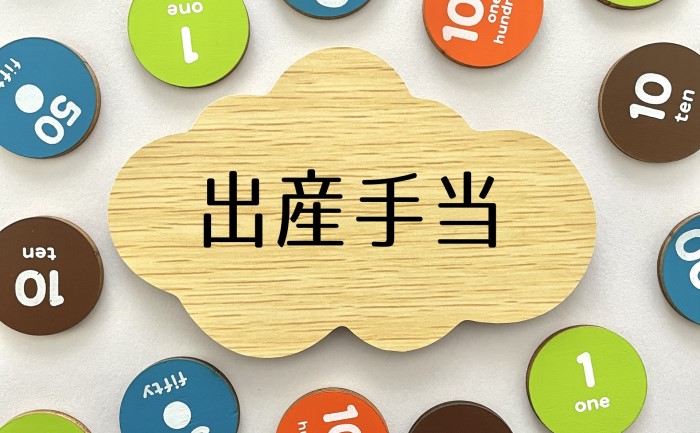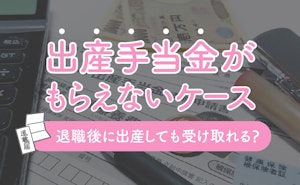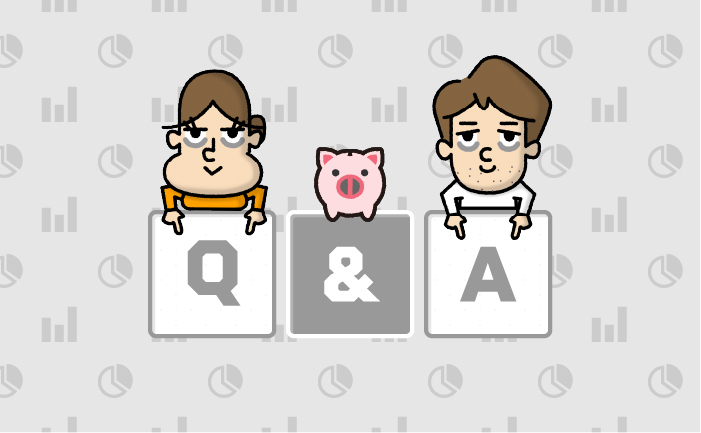出産によって家族が増えるのは喜ばしいことです。しかし、子どもを産み、育てるには想像以上にお金がかかります。
特に、子どもの教育資金をどのように用意するかは大きな課題です。子どもの進路によって必要となる金額は異なるため、計画的に準備する必要があります。
お金に関して、産休・育休中に行っておきたいことは以下の通りです。
- 子どもの進路を夫婦で話し合う
- 家計について見なおす
- 資産運用を検討する
- FPに相談する
子どもの進路を夫婦で話し合う
子どもの教育資金を準備するためには、子どもの教育方針や進路について夫婦で話し合うことが大切です。
夫婦間に考えの相違があると、目標とする費用が定まりません。例えば、夫は「高校まで公立」と考えていたのに、妻が「中学から私立に通わせたい」と考えていた場合、かかる費用が変わってきます。
幼稚園から大学までの学費の平均は、以下の通りです。
|
私立 |
国公立 |
| 幼稚園 |
約92万7000円 |
約49万8000円 |
| 小学校 |
約1000万2000円 |
約211万8000円 |
| 中学校 |
約431万1000円 |
約161万7000円 |
| 高等学校 |
約316万5000円 |
約153万9000円 |
| 大学 |
文系:約363万8000円
理系:約497万6000円 |
約242万6000円 |
出典:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」「私立大学等の令和3年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」「国立大学の授業料その他の費用に関する省令」
それぞれの進学課程において、私立と国公立でどのくらい費用が異なるのか相場を把握しておく必要があるでしょう。
家計について見直す
教育費を捻出するためには、まずは家計を見直すとよいでしょう。節約ができれば、貯蓄額を増やすことにつなげられます。
家計を見直す際には、現在の収支がどのようになっているか把握したうえで節約できる部分を見つけましょう。そのためには、毎月の預貯金額など、目標を立てることも大切です。
また、家計を見直す際には、固定費に注目してください。固定費とは、住居費や通信費、水道・光熱費など毎月かかる費用のことです。固定費は一度見直すとその効果が長く続きます。
家計の見直しを具体的に行うための方法や節約アイデアについては、『家計の見直し方法や節約アイデア』を参考にしてください。
資産運用を検討する
家計の見直しによって、貯蓄できるだけの見通しが立ったら、次に資産運用も検討しましょう。投資信託や株式などを購入することにより、資産を増やせる可能性が広がります。
資産運用は、早くから行うことで、その効果がより大きくなります。教育費用についてはできるだけ早く、可能であれば子どもが産まれる前からどのような方法で準備していくか考えることが大切です。
FPに相談する
出産のタイミングは、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのに理想的なタイミングです。
FPには、家計の見直しや教育資金のほか、資産運用、住宅購入、保険、節税など、さまざまな分野の相談ができます。FPに相談することで自分たちに合った資産形成方法をアドバイスしてもらえます。
FPへの相談には有料のものと無料のものがあります。おすすめのFP相談は、以下の記事も参考にしてください。
◆ FP相談おすすめ一覧!お金の相談ができるサービスを無料・有料別に紹介