子育てに必要なお金は、子どもの年齢によっても大きく異なります。「何歳までにいくら用意すればいいの?」「子育ての費用はどうやって準備すればいい?」という疑問を持つ人もいるでしょう。
子育て費用の総額は、小学校から大学まですべて公立に通った場合でも2000万円以上かかります。
この記事では、子どもの年齢別に必要な費用をシミュレーションします。また、そのお金をどうやって工面していけばいいのかも解説します。
- 年齢別の子育て費用相場
- 公立・私立学校別の費用シミュレーション
- 子育て費用の準備方法
※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
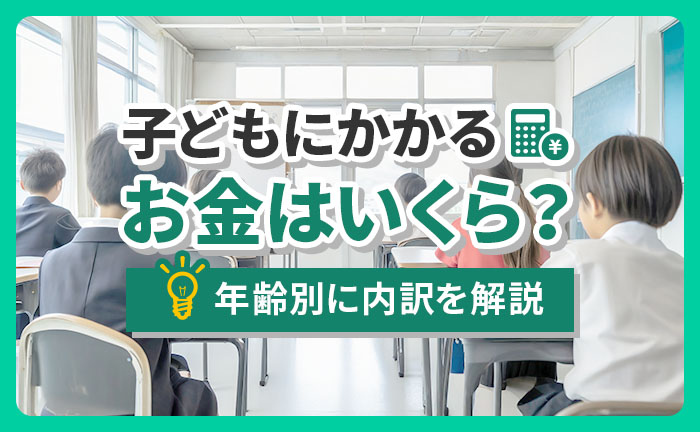
【監修】株式会社RKコンサルティング河合 克浩

一般企業、外資系金融機関を経て、現在はファイナンシャルプランナー(FP)として年間150件超のお金の相談に対応。難しく感じる経済やお金の話をわかりやすく説明することに定評がある。夢を実現するため相談者に寄り添い、人生が豊かになるサポートを心がけている。
子育てに必要なお金は、子どもの年齢によっても大きく異なります。「何歳までにいくら用意すればいいの?」「子育ての費用はどうやって準備すればいい?」という疑問を持つ人もいるでしょう。
子育て費用の総額は、小学校から大学まですべて公立に通った場合でも2000万円以上かかります。
この記事では、子どもの年齢別に必要な費用をシミュレーションします。また、そのお金をどうやって工面していけばいいのかも解説します。

まず子どもにはどのようなお金がかかるのか、内訳別に見ていきましょう。
これらの中でも、長期的な視点で準備が必要なのが教育費です。とくに負担が大きいのが大学に通った場合です。
教育費は、子どもの進路によっても違いがあります。一般的に国公立と私立では、2~2.5倍の差があるといわれています。
教育費については、『教育費はいくらかかる?学費の負担を減らす方法を紹介』も参考にしてみください。

子育てにはどれくらいのお金がかかるのか、内閣府の資料をもとに各年代で見ていきましょう。
| 生活費項目 | 金額 |
|---|---|
| 食費 | 4万9738円 |
| 水道・光熱費 | 1万6102円 |
| 家具・家事用品 | 9,683円 |
| 服飾費 | 1万2795円 |
| 保険・医療費 | 1万1865円 |
| 交通・通信費 | 4万7077円 |
| 教育費 | 407円 |
| 娯楽費 | 2万3816円 |
| その他の支出 | 5万644円 |
| 生活費合計 | 22万2127円 |
まずは子どもが出生してから2歳前後までにかかるお金です。乳児から幼児にかけては突然の体調変化が多く、上表でも医療費負担が目立ちます。この時期は、産休・育休などにより収入が減るケースも多いでしょう。
自治体によっては、子どもの医療費を自治体負担とするところがあります。先進医療など公的保険を除く医療費全額がカバーされる自治体と、1回500円などと金額上限が設定されている自治体があるので、自分の居住する自治体の制度を確認しましょう。
| 生活費項目 | 金額 |
|---|---|
| 食費 | 5万7854円 |
| 水道・光熱費 | 1万7560円 |
| 家具・家事用品 | 8,673円 |
| 服飾費 | 1万4287円 |
| 保険・医療費 | 1万777円 |
| 交通・通信費 | 4万1780円 |
| 教育費(幼稚園・保育園など) | 1万8831円 |
| 娯楽費 | 3万1551円 |
| その他の支出 | 5万3746円 |
| 生活費合計 | 25万5059円 |
子どもが3~5歳になると、教育費の負担が増えます。保育園は認可保育園と無認可保育園があり、保育料も大きく変わります。認可に入れるかは、待機児童の状況や、家族の条件などによって変わってくるでしょう。
また、旅行や日々のイベントなどで、娯楽費が上昇する時期でもあります。家族によっては2人目、3人目の子どもを考える時期でもあるため、目の前の子どもだけではなく、将来的なライフプランについてしっかり検討することが大切です。
| 生活費項目 | 金額 |
|---|---|
| 食費 | 6万8771円 |
| 水道・光熱費 | 1万8630円 |
| 家具・家事用品 | 8,936円 |
| 服飾費 | 1万5586円 |
| 保険・医療費 | 9,656円 |
| 交通・通信費 | 3万6424円 |
| 教育費 | 8,606円 |
| 娯楽費 | 4万1941円 |
| その他の支出 | 5万4704円 |
| 生活費合計 | 26万3254円 |
6~11歳は小学生の時期です。幼児期と比べて、小学生になると食費と娯楽費の負担が増えます。
服飾費が高いのは、短期間で身体が成長して衣服の買い替え頻度が高まるためです。最近はリユースの市場なども成長しているため、上手に利用したいところです。
| 生活費項目 | 金額 |
|---|---|
| 食費 | 7万5540円 |
| 水道・光熱費 | 2万872円 |
| 家具・家事用品 | 8,804円 |
| 服飾費 | 1万6043円 |
| 保険・医療費 | 8,657円 |
| 交通・通信費 | 3万9432円 |
| 教育費 | 2万4639円 |
| 娯楽費 | 3万381円 |
| その他の支出 | 6万4292円 |
| 生活費合計 | 28万8660円 |
中学校からは私立に通わせる人も増えます。一般的な目安ですが、私立の教育費は公立に比べて2~2.5倍かかります。食費や水道・光熱費といった日常生活に必要な費用も増すため、家計のやりくりが一層重要になります。
とはいえ、この3年間がピークではなく、ここからさらに全体的な費用が上がっていくため、12歳を迎えるまでにどれだけ資金を準備できるかがポイントです。
| 生活費項目 | 金額 |
|---|---|
| 食費 | 8万229円 |
| 水道・光熱費 | 2万1848円 |
| 家具・家事用品 | 1万122円 |
| 服飾費 | 1万6041円 |
| 保険・医療費 | 9,909円 |
| 交通・通信費 | 4万5612円 |
| 教育費 | 3万7794円 |
| 娯楽費 | 3万1630円 |
| その他の支出 | 7万2504円 |
| 生活費合計 | 32万5689円 |
全体的にさらに費用が増えています。場合によっては、預貯金の取り崩しが必要となってくる時期といえるでしょう。とはいえ、このあとの18~21歳ではさらに大きな負担がかかるため、親にとってはふんばりどころです。定期的にライフプランを見直し、家計をコントロールするようにしましょう。
子どもは学業や部活、キャリア形成などで重圧を受ける時期でもあるため、こまめに話し合い、現実性も踏まえた選択肢を取っていきましょう。
| 生活費項目 | 金額 |
|---|---|
| 食費 | 7万6248円 |
| 水道・光熱費 | 2万1841円 |
| 家具・家事用品 | 1万2154円 |
| 服飾費 | 1万9266円 |
| 保険・医療費 | 1万831円 |
| 交通・通信費 | 5万4506円 |
| 教育費 | 3万7697円 |
| 娯楽費 | 3万1545円 |
| その他の支出 | 9万1945円 |
| 生活費合計 | 35万6033円 |
子どもが国公立大学に進むか、私立大学に進むかによって教育費の負担は大きく変わります。また下宿や一人暮らしをする場合には、さらに大きな資金が必要になります。家計のやり繰りは厳しい時期ですが、子育ても残りわずかです。
浪人による予備校費や、突然の志望校変更などで追加費用が発生する可能性もあるため、余裕をもって準備しておきましょう。

教育費は、子どもの進路によって大きく変わります。子どもがどのような進路を希望してもいいように、しっかり相談して準備しておくことが大切です。
ここでは、小学校から大学までにかかる教育費と生活費について、高校・大学を私立へ進学した場合、公立へ進学した場合に分けてシミュレーションしてみます。
まず、中学校まで公立に通い、高校・大学と私立に通った場合のシミュレーションです。
合計額は3355万円です。
続いて、高校・大学ともに公立に通った場合のシミュレーションです。
大学卒業までの生活費:189万円(※個人により異なる)
合計額は2441万円です。
高校から公立に進学した場合よりも、私立に進学した場合の方が約1.4倍費用がかかります。なお、東京や大阪など都市部の大学に行くか、地方の大学に行くかで物価の違いも想定されます。
大学費用については、こちらの記事で詳しく解説されています。あわせてご確認ください。
参考:長男高1。貯金ゼロ。大学費用どうしよう?|中学受験(受検)のアレコレ

子育てにかかるお金を準備するポイントは、以下の通りです。
子どもを育てるための費用は、早い段階から準備しておくことが大切です。貯蓄を着実に増やす方法は、以下の通りです。
子どもにかかるお金の貯め方については、『子どものために必要な貯金額はいくら?』も参考にしてください。
貯蓄は意識しているけれど貯まらないという人は、家計簿をつけるのもおすすめです。家計簿をつけると、毎月の収支が把握しやすくなります。
毎月の支出は、変動費と固定費に分けて管理することが大切です。固定費は住居費や水道・光熱費など、変動費は食費や交際費などです。家計簿をつけたうえで前月以前と比較することで、使い過ぎていないか判断できます。
スマートフォンの家計簿アプリを使う方法もあります。レシートをカメラで撮影するとて、支出項目が分けられるなど利便性が高いです。
通常の給与振込や生活費の引き出しに使用している口座とは別に、教育費を貯蓄するための口座を持っておくことも有効な方法です。用途別に口座を分けることで、ついお金を引き出してしまうのを避けられるでしょう。
支出を減らすだけでなく、収入を増やすのも有効です。より高収入な会社に転職したり、副業したりする方法があります。最近は副業を解禁する会社も増えています。
株式や投資信託などで資産運用に取り組む方法もあります。学資保険など、貯蓄性のある保険を活用すると、万が一の場合の保障をしながら資産形成をすることも可能です。
家族構成や年収などの要件を満たしていれば、国や自治体の助成金制度を利用できることがあります。主な助成金制度は、以下の通りです。
児童手当は、0歳~中学生までの児童を養育している世帯が支給対象です。2024年10月に制度改正を予定しており、支給対象が高校生まで延長されます。
高校生は必ず学校に通っていなければならないわけではなく、同年代で就職している人や、無職の人も対象となります。18歳を迎えたあと、最初の3月31日までが支給期間です。
国公私立を問わず、年収要件を満たした世帯の生徒に対して、授業料を限度に就学支援金として助成金が支払われます。家庭環境によって高等学校に通うことができなくなる生徒を金銭面でフォローする制度です。
制度の利用には所得要件が定められています。制度設計が複雑なので、対象になるかどうかは行政機関への確認をおすすめします。
月あたりの支給限度額の目安は、以下の通りです。
学費の負担を軽減するために、奨学金を利用する方法もあります。とくに利用者が多いのが、日本学生支援機構(JASSO)が提供している奨学金です。
JASSOの奨学金は給付型と貸与型に分けられます。また、貸与型も無利息の第一種、有利息の第二種があります。
奨学金については、『奨学金の借り方|申請方法や審査基準・借りるときの注意点』も参考にしてください。

子育てにかかる費用は、年齢や子ども自身の進む道によって必要額が大きく変わります。この記事では0~21歳までを6段階に分け、どのような費用がかかるのか、ほかの年代と比較して支出総額はどうなるのかをまとめました。
子どもが成長するにつれ必要な費用も増えていきます。とくに大学進学時には大きな費用がかかるため、子どもがまだ小さいうちから長期的な計画を立てて資金を準備していくことが大切です。
家計簿をつけて無駄な出費を減らし、貯蓄用の口座を作るなど、できることから始めましょう。わからないことがあるのなら、お金の専門家であるFPへ相談する方法もあります。
キーワードで記事を検索