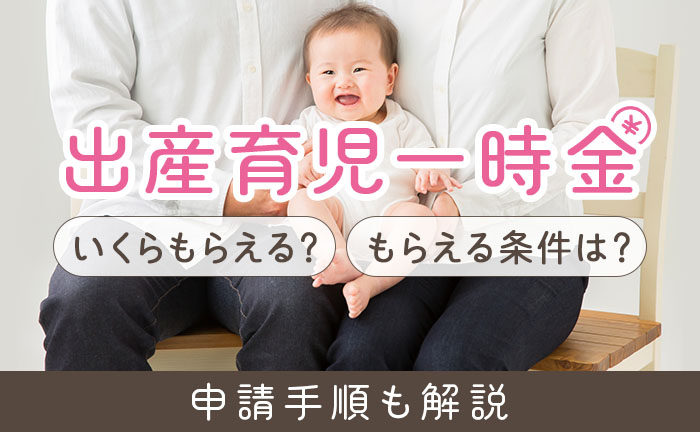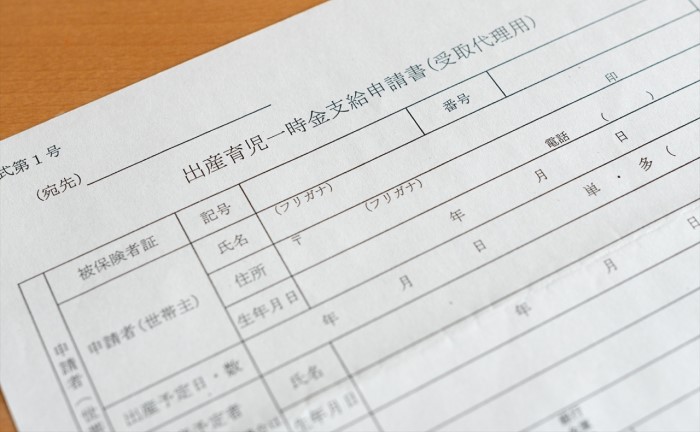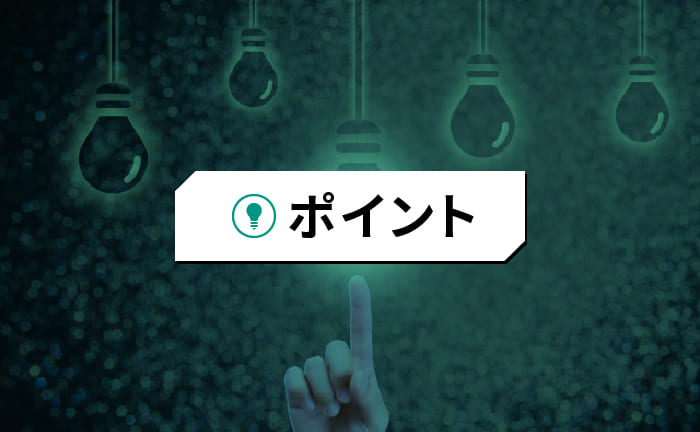出産育児一金とは、国民健康保険や健康保険組合の被保険者が子どもを産んだときに支給されるものです。
原則として妊娠および出産については保険の適用外となり、費用は全額自己負担です。そのため、妊娠経過の定期検査や出産費用まで含めると数十万円の負担になり、家計を圧迫する可能性があります。
そこで、経済的な負担を気にせずに安心して出産できるよう、出産育児一金の制度が設けられています。
出産育児一時金はいくらもらえる?
出産育児一時金の支給額は原則として50万円です。以前は42万円でしたが、出産費用が増加している背景を受け2023年4月より50万円に引き上げられました。
実際に出産にかかる費用の内訳は、以下の通りです。
正常分娩時に必要な費用内訳
| 項目 |
内訳 |
| 入院料 |
11万5776円 |
| 分娩料 |
27万6927円 |
| 新生児管理保育料 |
5万58円 |
| 検査・薬剤料 |
1万4419円 |
| 処置・手当料 |
1万6135円 |
| その他費用(お祝い膳など) |
3万2491円 |
| 合計(その他費用を除く) |
47万3315円 |
出典:厚生労働省「出産育児一時金について(令和3年度)」
2021年度の出産にかかる費用は合計で約47万円ですが、このほかに個室を選ぶなど保険適用外のサービスを選ぶと、さらに費用が大きくなります。
実際にかかった費用が50万円未満だった場合でも、50万円の支給が受けられます。一方、50万円を超えた場合は、50万円が支給上限となります。
以下の場合は支給額が異なるので、注意しておきましょう。
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合:48万8000円
- 妊娠週数が22週に達しておらず、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合:48万8000円
出典:厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」
出産育児一時金の対象者
出産育児一時金の対象者は、国民健康保険および健康保険組合の被保険者と、その配偶者である非扶養者です。
また、出産育児一金を受け取るには、以下の要件を満たさなければなりません。
そのほか、帝王切開や吸引分娩など異常分娩の人も対象です。外国籍の人や海外出産の場合も、日本の健康保険に加入しており、妊娠85日以上の出産であれば対象になります。
ただし、生活保護者は健康保険に加入しているといった要件を満たさないため、出産育児一時金の対象外です。
出産育児一時金の支給時期
出産育児一時金の支給時期は申請方法によって異なります。
直接支払制度および受取代理制度を利用した場合は、加入している健康保険から病院に直接費用が支払われます。直接申請する場合は、いったん自分で費用を立て替え、後日申請して受け取る形になります。
直接支払制度や受取代理制度を利用すれば、費用を立て替える必要がないため、経済的な負担も軽減されます。ただし、病院によっては直接支払制度や受取代理制度を取り入れていないところもあります。
出産するにあたり、病院を選ぶ際には、その病院が出産育児一時金の申請方法としてどの方法を取り入れているかを事前に確認しておきましょう。
出産育児一時金と出産手当金の違い
出産育児一時金以外に出産時にもらえるお金としては、出産手当金があります。出産育児一時金と出産手当金は混同されやすいですが、異なる制度です。
出産手当金は健康保険組合の制度です。出産のために会社を休んだ際の収入を一部保障するのが目的のため、会社に勤めている人でなければ受け取れません。
違いを下表にまとめるので、どのような相違点があるのか理解しておきましょう。
| |
出産育児一時金 |
出産手当金 |
| 目的 |
出産にかかる経済的な負担を軽減する |
出産のために会社を休んだ際の収入減少を負担する |
| 対象者 |
健康保険に加入している被保険者および被扶養者 |
健康保険組合に加入している被保険者 |
| 金額 |
50万円 |
(1日あたり)標準報酬月額÷30日×2/3 |
| 申請先 |
健康保険の窓口もしくは病院 |
健康保険組合 |