結婚したら、一人暮らしや実家暮らしのときと比べて、生活費が大きく変わります。「結婚したらどれくらい生活費がかかる?」「夫婦で生活費の負担割合はどうする?」「結婚後も貯蓄はできる?」など、結婚後のお金について不安を感じている人もいるのではないでしょうか。
夫婦2人の生活費の平均は、約23万6000円です。
この記事では、夫婦で賢く節約するためのお金の管理方法について解説します。
- 新婚夫婦の生活費相場
- 地域・間取り別の家賃相場
- 夫婦で上手に節約して貯蓄する方法
※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

【監修】株式会社RKコンサルティング河合 克浩

一般企業、外資系金融機関を経て、現在はファイナンシャルプランナー(FP)として年間150件超のお金の相談に対応。難しく感じる経済やお金の話をわかりやすく説明することに定評がある。夢を実現するため相談者に寄り添い、人生が豊かになるサポートを心がけている。
結婚したら、一人暮らしや実家暮らしのときと比べて、生活費が大きく変わります。「結婚したらどれくらい生活費がかかる?」「夫婦で生活費の負担割合はどうする?」「結婚後も貯蓄はできる?」など、結婚後のお金について不安を感じている人もいるのではないでしょうか。
夫婦2人の生活費の平均は、約23万6000円です。
この記事では、夫婦で賢く節約するためのお金の管理方法について解説します。

総務省が公表している統計をもとに、新婚夫婦の生活費平均と割合を紹介します。
住居費は住む場所によって大きく異なります。そのため、「生活費の相場」と家賃や住宅ローンといった「居住費の相場」を分けて紹介します。
総務省の家計調査によると、2人暮らしの生活費の平均は毎月23万6061円です。
| 世帯の分類 | 勤労世帯 | 割合 |
|---|---|---|
| 食費 | 6万7573円 | 29% |
| 光熱・水道費 | 2万2073円 | 9% |
| 家具・家事用品 | 1万840円 | 1% |
| 服飾費 | 6,820円 | 3% |
| 保険医療費 | 1万4895円 | 6% |
| 交通・通信費 | 3万4348円 | 15% |
| 教育費 | 413円 | 0% |
| 教養・娯楽費 | 2万3118円 | 10% |
| その他の支出 | 5万5981円 | 24% |
| 1ヵ月あたりの生活費合計 | 23万6061円 | 100% |
地域・間取り別に家賃相場をまとめました。
| 地域 | ワンルーム・1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3LDK |
|---|---|---|---|
| 東京23区(東京都) | 6.98~13.61万円 | 11.11~25.85万円 | 16.20~33.70万円 |
| 大阪市(大阪府) | 5.26~6.67万円 | 6.77~13.14万円 | 8.62~21.21万円 |
| 名古屋市(愛知県) | 4.55~6.35万円 | 6.07~10.02万円 | 7.43~14.94万円 |
| 札幌市(北海道) | 3.33~4.71万円 | 4.66~6.19万円 | 5.87~9.94万円 |
| 金沢市(石川県) | 約5.22万円 | 約7.85万円 | 約9.93万円 |
| 岡山市(岡山県) | 3.97~5.23万円 | 4.95~6.91万円 | 5.28~9.02万円 |
| 高松市(香川県) | 約4.46万円 | 約6.07万円 | 約6.33万円 |
| 那覇市(沖縄県) | 約5.39万円 | 約9.57万円 | 約18.03万円 |
三大都市部は多くの行政区に分かれており、どこの区に住むかによって家賃相場が大きく異なります。そのため、同じ間取りでも、ほかの地域より三大都市部の方が価格帯は幅広い傾向があります。
前述した生活費相場(家賃抜き)の金額23万6061円に、上表の金額を合計すれば、住居費を含めた1ヵ月間の生活費が計算できます。
2人暮らしに必要な生活費については、『2人暮らしの生活費は平均いくら?世帯手取り別のシミュレーションや節約術』も参考にしてください。

夫婦でのお金の管理方法は、以下の2パターンに分けられます。
家計共有型は、1つの共通する財布を夫婦で管理する方法です。一方、家計独立型は夫婦がそれぞれの財布で管理する方法です。
夫婦お互いの収入を1つの共通する財布にまとめて、家計を一元管理する方法です。
家計共有型はお互いが貯蓄額を確認できるため、以下のようなメリットがあります。
しかし、夫は趣味を楽しみたい一方で、妻はしっかり貯蓄したいなど、お金の使い方に関する考えが異なるとストレスになり、夫婦間でトラブルになるかもしれません。
家計共有型は、貯蓄をする場合「何のために」「いつまでに」「いくら」といった目標を明確にし、自由に使うお金についても、事前に夫婦で折り合いをつけておくことが大切です。
夫婦それぞれの財布を持ち、夫が保険料やスマートフォン代、妻が食費や日用品費といったように、項目ごとに支払いを分ける方法です。
決められた項目さえ支払えば、夫婦がお互いの支出について干渉することなく、趣味や娯楽など自由に使えるメリットがあります。
しかしお互いが浪費家の場合、気が付いたらどちらも貯蓄が残っていないことがあるなど、お金が貯まりにくいデメリットがあります。お互いの財布とはいえ、定期的にお金について話し合う場を設けることが大切です。
家計独立型は、夫婦どちらも家計管理が得意な場合に向いている家計管理方法といえるでしょう。

結婚後の夫婦間のお金の管理は、ある程度のルールを決めておくことが重要です。2人で暮らす以上、お互いが好き勝手にお金を使ったらトラブルになりかねません。
望ましい管理方法は、共働きなのか、どちらか一方が専業主婦(主夫)かによって異なるため、それぞれ解説します。
共働きの場合のお金の管理方法として、以下の2種類があります。
「家賃は夫、食費は妻」など、費用ごとにどちらが出すか決める方法です。一般的な費用の分け方は以下の通りですが、生活スタイルに合わせて自由に決めて構いません。
自分が担当する費用さえ支払えば、相手に収入の総額を知られることがないのがメリットです。
ただし、お互いに相手の収入状況がわからない状態だと、いざというときに困る可能性もあります。例えば、急に大きな出費が必要になっても、相手の貯蓄がまったくないという事態も起こり得るでしょう。
また、子どもができたら食費や教育費が増えるなど、かかる費用は年々変化していきます。適宜担当を変更したり、管理方法そのものを見直したりするなど、柔軟に対応しましょう。
共通の銀行口座を作り、それぞれの収入に合わせて毎月の生活費を入金し、その中でやりくりする方法です。残りはそれぞれのお小遣いにしたり、貯蓄に回したりします。「毎月いくら出せばよいか」が明確になるので、トラブルになりにくいのがメリットです。
ただし、こちらも口座に入れるお金以外は、相手の収入やお金の使い道はわかりません。相手が残ったお金をすべて使ってしまい、貯蓄がまったくない事態も考えられます。
そのため、生活費用の口座とは別に貯蓄用口座を作り、そこにお互いが毎月一定額ずつ入金する形が望ましいでしょう。
片方が専業主婦(主夫)の場合は、家計担当を決めて一括管理する方法がよいでしょう。給料をすべて家計担当に預け、そこからお小遣いをもらう形です。
この方法のメリットは、家計を一元管理できるので貯蓄がしやすいことです。ただし、お小遣いをもらう側は自由になる金額が少なくなるため、不満が生じやすくなります。
この方法をとる場合は、管理する側が相手に支出や貯蓄の情報をこまめに報告しましょう。また、相手の要望があれば一時的にお小遣いを増やすなど、ある程度は柔軟に対応することも必要です。
さらに詳しく夫婦でお金を管理する方法や、円満にお金の管理をするコツを知りたい方は、『夫婦でお金の管理する方法』で詳しく解説しています。

夫婦での家計管理に関して、調査を行いました。寄せられた意見を紹介します。
結婚する予定のカップルや、結婚したばかりの夫婦にとって重要なのが「お金の管理方法を決める」ことです。2人で暮らす以上、どちらかが身勝手なお金の使い方をするとトラブルが起きる可能性があります。

結婚後のお金の管理では、以下のようなトラブルが起きがちです。
夫婦関係を良好に保ち、これらのトラブルを回避するためにも以下のコツを心得ておきましょう。
毎月の収支を夫婦で共有して、不透明な部分をなくすことは重要です。
片方だけが収支を管理していると、相手に黙ってお小遣いに使うなどのルール違反が起きやすくなります。こうしたルール違反は、後々トラブルになる可能性があります。
情報を共有するためには、共通のアカウントで利用できる家計簿アプリを使うのもおすすめです。家計簿アプリの中には、2人の共通のお金と個人のお金を分けて管理できるものもあります。プライバシーを保ちつつ、家庭のお金の状況をリアルタイムに把握できるので便利です。
毎月の貯蓄額は無理のない金額で設定しましょう。目安は手取り収入の20%といわれていますが、生活費を確保できないようならこれより少なくて構いません。
無理な節約をしたことでストレスを溜め、その反動で浪費に走ってしまったら元も子もありません。また、貯蓄を始めるときは、「5年後にマイホームを買うために500万円貯める」というように、目標金額や期間を決めるのがおすすめです。
お互いに干渉しない自由なお金を設定しておくことも重要です。自由なお金がなかったり、相手のお金の使い方に干渉しすぎたりすると、相手によっては「へそくり」をするなどしてお金を確保しようとするかもしれません。
その事実が発覚すると、「隠し事をしていた」と相手に不信感を与えることになるでしょう。さらにはこれが原因で、別居や離婚など、深刻な状況に発展する可能性もあるでしょう。
夫婦で将来のビジョンについて話し合っておくことも大切です。例えば、「持ち家に住むか、賃貸に住み続けるか」「子どもの有無や人数」などについて、結婚する段階で話し合い、意見をまとめておきましょう。
ただし、「将来はこうしたい」という希望があっても、先立つものがなければ難しいのが現実です。お金がないことが原因でビジョンを変更せざるを得なくなれば、夫婦間のトラブルの原因になりかねません。
トラブルを防ぐためにも、以下の点を話し合い、確認しておきましょう。

夫婦はお互いの支出や貯蓄に関する考え方が異なるケースもあり、独身よりも貯蓄が難しくなる場合があります。子どもが生まれたら、さらに貯蓄が難しくなるでしょう。そこで夫婦で賢く節約して貯蓄するコツを3つ紹介します。
5年で100万円貯めたい、60歳までに1000万円貯めたいなど、目標を明確にするとお金が貯まりやすくなります。
大きなお金は1年や2年といった短い期間では貯まりません。例えば10年で1000万円を貯めようとすると、毎月8.4万円の貯蓄が必要です。しかし20年あれば毎月約4.2万円の貯蓄で1000万円が貯められます。
一方で、時間をかけるほど挫折もしやすくなります。コツコツと貯蓄を続けるためには、貯蓄の目標を明確にすることが必要です。5年後の海外旅行、10年後の子どもの教育費など具体的な目標を定めましょう。
普段意識していないと、余計な支出をしてしまいがちです。毎月家計簿をつけて自身の支出を振り返るようにするだけで、お金が貯まりやすくなるでしょう。
家計簿に慣れていないと、すべての支出を記録しなければならないと考え、長続きしないことがあります。慣れないうちは、おおよそでも大丈夫です。無理せずに、自身の支出の傾向を把握することから始めましょう。
家計簿をもとに、過去の支出について「もっと安くできなかったか?」「余計な買い物ではなかったか」など振り返りをすることで、今後に向けた節約のヒントが見つかることがあります。
多くの人が、毎月の収入から光熱費、保険料などを支払い、そこから生活費、娯楽などの支出を引いて余った金額を貯蓄に回そうとします。しかし、確実に貯蓄するなら逆の方がいいでしょう。
収入があったら先に一定額を貯蓄に回し、残った金額で生活費をやりくりする方法です。自動的に貯蓄に回す仕組みを作ることで、意識せずにお金が積み立てられていきます。
具体的には、以下のような方法があります。
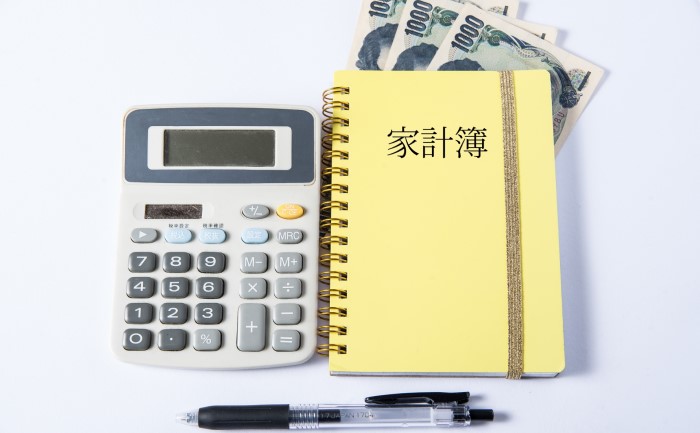
家計簿をつけると、その月に、何に、いくら使ったかが一目でわかります。余計な支出、見直せる支出などが見えてくるようになります。
例えば、週に1回外食をしていた場合、「外食を2週間に1度にする」「1回あたりの外食にかかる費用を減らす」などの対策が立てられます。
家計簿は貯蓄や節約をするうえで効果的な反面、継続が難しいというデメリットがあります。無理なく家計簿を継続するには、「食費」「日用品費」「レジャー費」など、まずは大雑把な分類で管理してみるなど、自身で管理できる方法から始めましょう。
最近では使いやすい家計簿アプリもあります。また支払いをクレジットカード払いにすれば、利用明細を家計簿代わりに使えます。
あわせて読みたい

ファイナンシャルプランナー(FP)は社会保障や保険、税金、年金、相続など幅広い知識を持ち、顧客のお金に関するあらゆる悩みを解決する「お金の専門家」です。
FPの専門分野にもよりますが、一般的に次のような相談に応じることができます。
多くの人がお金に対して漠然とした不安を持っています。FPに相談することで問題点が明確になるうえ、解決方法の提案や実行までのサポートが受けられます。

夫婦で賢く節約して貯蓄をするためには、貯蓄の目標を明確にしたうえで、貯蓄を仕組み化することが大切です。家計簿を付けることも効果的ですが、慣れないうちは自身の管理しやすい方法で、まずは続けることを心がけましょう。
将来の生活資金に不安がある人は、FPへの相談もおすすめです。FP相談なら何度でも相談無料で、お金に関する幅広い悩みに対応してくれます。
キーワードで記事を検索