長年勤め上げたことに対する報償的意味合いの強い退職金ですが、実際にいくらもらえるのか気になる人も多いのではないでしょうか。退職金の相場は、企業規模や学歴、勤続年数、退職理由によって異なります。
この記事では、企業規模別の退職金相場や計算方法、注意点などについて解説します。
※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
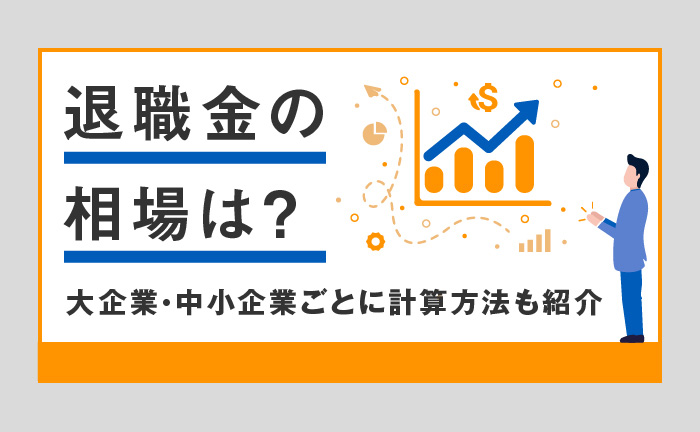
マネーFix 編集部

マネーFix 編集部は、FP有資格者や「ビジネス書」や「学習参考書」などさまざまなジャンルの編集経験者で構成されています。わかりやすく確かな情報を発信し「人生におけるお金の決断」の判断基準となる、信頼できるメディアを目指します。
長年勤め上げたことに対する報償的意味合いの強い退職金ですが、実際にいくらもらえるのか気になる人も多いのではないでしょうか。退職金の相場は、企業規模や学歴、勤続年数、退職理由によって異なります。
この記事では、企業規模別の退職金相場や計算方法、注意点などについて解説します。

退職金とは、定年などで企業を退職する際に支給されるお金のことです。
退職金の相場は、企業規模や勤続年数によって異なります。ここでは、企業規模別に退職金の相場について解説します。
厚生労働省中央労働委員会「令和3年賃金事情等総合調査」によると、満勤勤続の場合の平均退職金額は以下の表の通りです。
| 学歴 | 退職金の相場 |
|---|---|
| 大学卒 | 2230万4000円 |
| 高校卒 | 2017万6000円 |
退職金の金額は、業種によっても異なります。
業種別の退職金の相場を見てみましょう。
| 業種 | 退職金の相場(大卒の場合) |
|---|---|
| 建設業 | 2583万円 |
| 製造業 | 2687万円 |
| 銀行・保険業 | 2308万円 |
| 小売業 | 2463万円 |
| 海運・倉庫業 | 1752万円 |
| 新聞・放送業 | 2643万円 |
| ホテル・旅行業 | 2202万円 |
| 石油業 | 4072万円 |
| 繊維業 | 3942万円 |
| 化学業 | 2174万円 |
| 機械業 | 1253万円 |
大企業の場合、2500万円前後の退職金がもらえる業種が多いことがわかります。
退職金の金額は、基本的に勤続年数が長くなるほど大きくなります。
厚生労働省中央労働委員会の調査データによると、勤続年数別の退職金の相場は以下の通りです。
| 勤続年数 | 退職金の相場 |
|---|---|
| 5年 | 118万円 |
| 10年 | 310万2000円 |
| 20年 | 953万1000円 |
| 30年 | 1915万4000円 |
勤続年数5年と30年を比較すると、退職金の金額の差は約16倍です。
これに対して勤続年数の差は6倍なので、長期間勤め続けた方が退職金の恩恵が大きくなることがわかります。
退職理由には、大きく「会社都合」「自己都合」の2種類があります。
会社都合の退職とは定年退職のほか、倒産やリストラなどによる退職のことです。
一方、自己都合の退職とは、転職や家庭の事情などで退職することを指します。
基本的に、自己都合退職よりも会社都合退職の方が退職金の金額は大きくなります。
りそな年金研究所「企業年金ノート」によると、退職理由別の退職金の相場は以下の通りです。
| 退職理由 | 退職金の相場(勤続年数30年の場合) |
|---|---|
| 会社都合 | 2012万9000円 |
| 自己都合 | 1898万3000円 |
大企業の場合、会社都合退職と自己都合退職で、114万6000円の差が出ることがわかります。
東京都産業労働局「令和2年 中小企業の賃金・退職金事情」調査結果によると、定年退職時の退職金の相場は以下の通りです。
| 学歴 | 退職金の相場 |
|---|---|
| 大学卒 | 1118万9000円 |
| 高校卒 | 1031万4000円 |
退職金の金額は業種によっても異なります。
東京都産業労働局「令和2年 中小企業の賃金・退職金事情」によると、中小企業における業種別の退職金の相場は以下の通りです。
| 業種 | 退職金の相場(大卒の場合) |
|---|---|
| 建設業 | 1313万8000円 |
| 製造業 | 1148万7000円 |
| 情報通信業 | 1154万5000円 |
| 運輸業、郵便業 | 893万2000円 |
| 卸売業、小売業 | 1088万4000円 |
| 金融業、保険業 | 1725万5000円 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 1353万7000円 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 1007万1000円 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 1104万2000円 |
| 教育、学習支援業(学校教育を除く) | 656万9000円 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 996万円 |
中小企業の場合、1100万~1300万円が退職金の相場という業種が多いです。
勤続年数が長くなるほど、退職金の額も大きくなります。
りそな研究所「企業年金ノート」によると、中小企業における勤続年数ごとの退職金の相場は以下の通りです。
| 勤続年数 | 退職金の相場 |
|---|---|
| 5年 | 60万3000円 |
| 10年 | 148万3000円 |
| 20年 | 425万円 |
| 30年 | 785万6000円 |
勤続年数5年と30年とを比較すると、退職金の金額は約13倍です。
それに対して、勤続年数の差は6倍であるため、中小企業の場合も長期間勤め続けた方が退職金の恩恵が大きくなることがわかります。
中小企業の、退職理由別の退職金額についても見ていきましょう。
| 退職理由 | 退職金の相場(勤続年数30年の場合) |
|---|---|
| 会社都合 | 785万6000円 |
| 自己都合 | 705万9000円 |
中小企業の場合、会社都合の退職と自己都合の退職で79万7000円の差が出ることがわかります。

退職時にもらえる退職金の計算方法には、以下の3種類があります。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
年功型とは、勤続年数に比例して賃金が増えたり、昇進したりする仕組みのことです。
年功型で退職金が算出される場合は、勤続年数に応じて退職金が増えます。
年功型の退職金の計算方法は、以下の通りです。
「退職事由係数」とは、自己都合退職の場合に関係してくる数字です。
企業によっても異なりますが、会社都合の場合にはこれが100%なのに対し、自己都合だとそれよりも低い割合となります。
成果報酬型とは、勤続年数は考慮せずに、役職や職能級(肩書ではなく、能力や実績に応じて変化する等級)によって退職金額を決める方法のことです。
成果報酬型の場合、成果次第では勤続年数が短くても、勤続年数が長い人より多くの退職金を得られる可能性があります。
一方、いくら長期間勤め続けても、役職や職能給が低ければ退職金の金額は小さくなってしまいます。
成果報酬型の退職金の算出方法は、以下の通りです。
ポイント制とは、従業員の勤続年数や役職、スキル、成果、貢献度などをポイント化し、その合計にポイント単価と退職事由係数を掛けて退職金を算出する方法です。
ポイントがもらえる基準やポイント単価は、企業によって異なります。
ポイント制の退職金の計算方法は、以下の通りです。
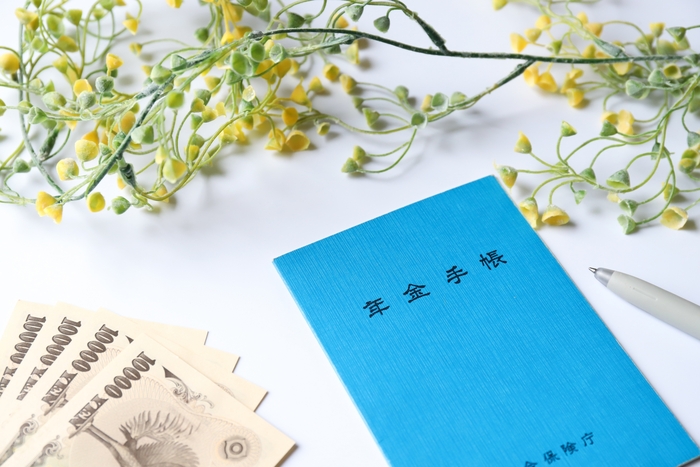
退職金は一時金として受け取る方法のほかにも、年金として受け取る方法もあります。
詳細は以下の通りです。
| 年金の種類 | 加入要件 | 支給要件 |
|---|---|---|
| 確定給付企業年金(DB) | 厚生年金保険の被保険者であること | ・老齢給付金 (1)60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したとき (2)50歳以上、(1)で定めた年齢未満の、規約で定める年齢以降に退職したとき ・脱退一時金加入者期間が3年以上で、老齢給付金の受給要件を満たさない者が脱退したとき ・障害給付金規約で定める障害状態になったとき ・遺族給付金加入者または受給権者などが死亡したとき |
| 厚生年金基金 | 厚生年金基金を設立・運営する企業の従業員で、厚生年金保険の被保険者であること | 60歳到達時または厚生年金の支給開始時 |
| 企業型確定拠出年金(DC) | 厚生年金保険の被保険者(公務員を除く)であること | ・老齢給付金加入者が60歳以降になったとき(加入期間によって支給開始時期が繰り下げられることがある) ・脱退一時金個人別資産が1万5000円以下で一定の条件を満たす者が脱退したとき ・障害給付金加入者が75歳までに高度障害に該当したとき ・死亡一時金加入者が死亡したとき |
退職一時金と企業年金の違いは、税制面での優遇内容です。
退職一時金は一時所得として課税対象になるのに対して、企業年金は雑所得として課税対象になります。
また、企業年金の金額は、掛金の額や加入期間によって異なります。

退職金を受け取る際の注意点は、受け取り方によって手元に残る金額が異なることです。退職一時金として一括で受け取ると、手厚い税制優遇を受けられます。
一方で、年金として分割で受け取る場合には、税負担は比較的大きくなりますが、総支給額は一時金として受け取る場合よりも大きくなることが多いです。
どちらの方がお得になるのかはケースバイケースなので、支給方法を決める前にそれぞれの方法でいくら手元に残るのかシミュレーションしてみましょう。

退職金としてもらえる金額は、さまざまな要因に左右されます。また、退職金以外にも企業年金という形で老後の資金を得ることも可能です。
今回の記事で紹介したさまざまなパターンを参考に、自分が将来どの程度退職金をもらえるのか一度確認してみてはいかがでしょうか。
死亡退職金の相場については、こちらの記事で詳しく解説されています。あわせてご確認ください。
参考:死亡退職金の相場はどれくらい?非課税枠の計算方法についても紹介【みんなが選んだ終活】
キーワードで記事を検索