学資保険に入りたいけれど余裕がない、または家計に余裕があれば入りたいと考えている人はいませんか?
学資保険に入る余裕がない人は、家計の見直しや、児童手当の活用、親の援助を受けるといった方法が有効です。
この記事では学資保険のメリットとデメリット、学資保険に入らなくて良いケースについて紹介します。学資保険に入りたいけれど、金銭的な問題で加入をためらっている人は参考にしてください。
※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
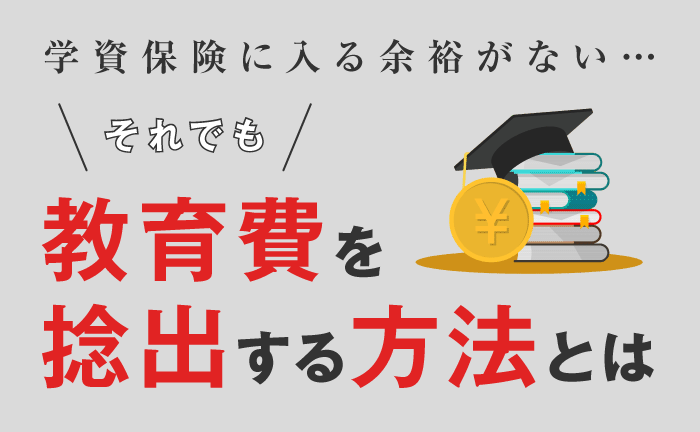
学資保険に入りたいけれど余裕がない、または家計に余裕があれば入りたいと考えている人はいませんか?
学資保険に入る余裕がない人は、家計の見直しや、児童手当の活用、親の援助を受けるといった方法が有効です。
この記事では学資保険のメリットとデメリット、学資保険に入らなくて良いケースについて紹介します。学資保険に入りたいけれど、金銭的な問題で加入をためらっている人は参考にしてください。

学資保険は、大きな金額が必要になる教育費用を効率的に積み立てるために加入するものです。
小学校から大学卒業までかかる費用の目安は、すべて公立に通った場合で約957万円、すべて私立で、文系大学に進学した場合は2,361万円、理系大学に進学した場合は2,492万円です。
このように教育費用は、大きなお金が必要なので1年、2年といった短い期間で準備するのは難しいでしょう。
学資保険を使って積み立てると、払い込んだ保険料よりも、将来受け取る金額の方が多くなる可能性があります。そのため、効率的に教育資金を準備する方法の1つとして、学資保険はよく利用されます。
ただ、学資保険は契約者(通常は親)や被保険者(子ども)の年齢によっては、メリットを受けられず、入らない方がいいこともあります。
学資保険の必要性を考えるうえで、まずメリットを確認しておきましょう。
学資保険に加入すると、銀行口座にお金がある限り、毎月一定額が口座から自動的に引き落とされます。
そのため、学資保険に加入して、強制的にお金が引き落とされる仕組みを作ることで、貯蓄が苦手な人でもコツコツ堅実に資金を貯めることができるようになります。また、学資保険は途中解約をすると元本割れをすることがあるので、解約しにくいという意識が働くこともメリットといえるでしょう。
学資保険は契約者に万が一のことがあったとき、それ以降の保険料の支払いが免除されます。しかし、保険料の負担はなくなっても、契約時に取り決めた祝い金や満期保険金は受け取ることができます。
そのため、学資保険は積み立て機能だけでなく、保障の役割も果たしているといえます。
そのほか、子どもがケガや病気で入院や手術を受けたときの医療費の保障や、親に万が一のことがあったときに年金が受け取れる育英年金などの特約で、保障を拡充することも可能です。
学資保険の保険料は一般生命保険料控除の対象になり、所得税・住民税が減額されます。
仮に所得税・住民税の税率が10%の人の場合、所得税は最大4,000円、住民税は最大2,800円減額されます。こうした控除額は、学資保険の返戻率に反映されないメリットなので知っておきましょう。
次に学資保険のデメリットも見ていきましょう。
学資保険は契約者や被保険者の年齢をある程度制限することで、高い返戻率を維持しています。
年齢制限の目安は保険会社によって異なりますが、契約者(親)の年齢は18歳以上から60代、被保険者は0歳から6歳です。また、被保険者が生まれる前から加入できる学資保険もあります。
学資保険の保険料を払っている期間中、医療費や冠婚葬祭など急に大きな支出があっても、学資保険からお金を引き出すことはできません。
保険料を払っている期間中に学資保険のお金を使うには、途中解約をする必要があります。ただし、途中解約をすると学資保険は多くの場合、元本割れしてしまいます。
学資保険での貯蓄は、万が一のときに引き出すお金とは別に考えておきましょう。また、無理なく支払っていける保険料であることも大切です。
世の中の物価が上昇することをインフレーション(インフレ)といいます。
仮にインフレによって学費が値上がりしたとしても、学資保険の祝い金や満期保険金がそれに合わせて増額されることはありません。
つまり、インフレ局面では学資保険の祝い金や満期保険金の価値は目減りしてしまうことになります。学資保険はインフレに弱い金融商品である点も知っておきましょう。

ここまで紹介した学資保険のメリット・デメリットを踏まえて、以下に当てはまる人は、学資保険が必要ない、あるいは入らない方がいい人といえるでしょう。
教育費、住宅購入費、老後生活費は人生の3大支出といわれるほど、多額のお金がかかるライフイベントです。
そのうちの1つである教育資金がすでに貯まっているのであれば、学資保険ではなく早めに住宅購入費や老後生活費の準備に取りかかりましょう。
先述した小学校から大学卒業までにかかる費用の目安に加え、大学で一人暮らしをする場合の生活費としておおよそ月10万円(4年間で480万円)程度を準備できていれば、教育資金が貯まっているといえます。
| 教育費用 | 4年分の生活費の目安 | 必要額 | |
|---|---|---|---|
| 小学校から大学まですべて公立 | 957万円 | 480万円 | 1,437万円 |
| 小学校から大学まですべて私立(文系大学) | 2,361万円 | 2,841万円 | |
| 小学校から大学まですべて私立(理系大学) | 2,492万円 | 2,972万円 |
保険料を払い続けていく自信がない人や、今後大きな支出が控えていて、途中で解約をする可能性が高い人は学資保険に入らない方が良いでしょう。
なぜなら、学資保険は途中解約をすると高い確率で元本割れするためです。
目安として10年以内に解約すると、元本割れする可能性が高くなります。また、学資保険は保険料を払っている期間中にまとまったお金が必要になっても、途中でお金を引き出すこともできません。
金融商品の中には学資保険より効率良くお金を増やせる商品もあります。
より効率的に教育資金を準備したい人は、学資保険の必要性は低いでしょう。また、学資保険は契約者や被保険者の年齢によって返戻率が異なります。場合によっては返戻率が良くないケースや、元本割れするケースもあります。
年齢的な問題で返戻率の高いプランが作れない人や元本割れする人、あるいはインフレによる資産の目減りが気になる人は、学資保険ではなく資産運用などの方法も検討してみましょう。
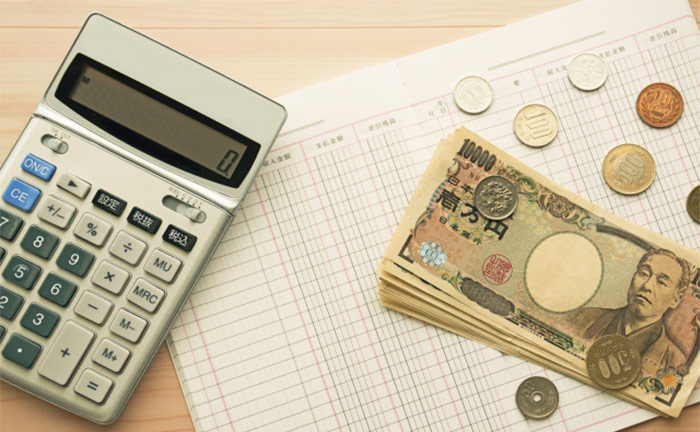
学資保険に入りたいけれど金銭的に入る余裕がない人は、以下の3つの方法を検討してみましょう。
まず、今の家計に見直しの余地がないかを確認してみましょう。とくに毎月の支払額がある程度決まっている固定費を見直すと、その効果はずっと継続するため、見直し効果が高いといわれています。
多くの人は、児童手当を学資保険の保険料に充てています。
| 3歳未満 | 一律15,000円 |
|---|---|
| 3歳以上~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 一律10,000円 |
学資保険を活用して、仮に毎月の保険料が1万円の学資保険に加入すると、子どもが10歳になるまで支払うと少なくとも120万円。15歳になるまで支払うと少なくとも180万円は保険料に充てることができます。
保険料の捻出が難しい場合は、児童手当を保険料に充てられないか検討してみましょう。
学資保険の中には、親ではなく、祖父母を契約者にできる商品もあります。学資保険に入る余裕がない人は、学資保険の費用を親に負担してもらうことも検討しましょう。
ただし、学資保険は契約者に年齢制限を設けているので、必ず加入できるとは限りません。祖父母が契約者になると、祝い金や満期金の受取人を孫や父母にしてしまいがちですが、契約者と祝い金や満期金の受取人を同じにしておかないと、税率が高い贈与税が適用されることがあるため注意が必要です。
贈与税は年間110万円までならかかりませんが、祝い金や満期金が110万円を超えることは十分あり得ます。学資保険の契約者を祖父母にするときは、加入前に、契約条件や課税関係について十分確認しておきましょう。

ここでは、学資保険以外に教育資金を準備する方法を紹介します。
預貯金には、銀行や郵便局などの預貯金や積立預金、定期預金などがあります。
店舗のある銀行の普通預金、定期預金、定期積金で貯蓄する方法
店舗を持たないネットバンクを利用した普通預金、定期預金、定期積金で貯蓄する方法
国と会社が連携して従業員の資産形成を支援する制度
毎月一定額が会社の給与から毎月天引きされる形で、会社が提携している金融機関の運用商品で積み立てられます。銀行預金やネットバンクでの預金は、金利が低いものの、元本割れする心配はありません。
また、金利は、店舗のある銀行と比較し、ネットバンクの方が高い傾向にあります。
そのため、元本割れを避けたい人は、銀行預金やネットバンクでの預金が向いています。また、財形貯蓄は、定期的に給与から天引きされて積み立てができるため、計画的に積み立てしたい人に向いています。
金融機関などからお金を借りる方法です。
JASSO(日本学生支援機構)が運営している奨学金や、民間の銀行が扱っている教育ローンなどがあります。
JASSO(日本学生支援機構)が運営する奨学金制度で、経済的な困難により、修学が難しい学生に対して、学資の貸与や給付をする制度です。
民間の銀行、日本政策金融公庫が扱う、教育関連に用途を限定したローンのことです。教育資金が必要な時期に十分な金額が用意できないとき、借入をすることで、すぐに教育資金を準備することができます。
ただし、審査が必要であり、誰でも利用できるわけではないこと、給付型奨学金以外は将来にわたって返済が必要であること、ほとんどの場合利息が発生するといった点に注意が必要です。
借り入れは、必要な時期までに教育資金の準備が間に合わず、将来にわたって少しずつ返済していきたい人に向いています。
資産運用とは、預貯金や株式、投資信託など金融商品を使ってお金を増やすことをいいます。
ここでは、より効率的な方法として、投資信託(NISA)と個人向け国債を紹介します。
プロのファンドマネージャーが投資商品を選定して運用する金融商品です。
運用はプロにお任せできるので、比較的初心者向きの資産運用といえるでしょう。NISA口座を利用すれば、運用益が非課税になるので、より効率的な運用ができます。
債券とは国や自治体がお金を借りたときの借用証書のことです。国が発行する債券を国債といい、債券を購入すると国にお金を貸すことになります。国債を保有している期間中は定期的に利息を受け取れます。
投資信託は元本割れする可能性があるため、生活に余裕がない人は個人向け国債の方がおすすめです。ここで紹介する2つの資産運用方法は貯蓄より利益は大きくなりますが、元本割れする可能性もあります。
学資保険以外の生命保険でも教育資金は準備ができます。
解約返戻金を一定期間抑えることで、保険料を割安にした終身保険です。
保険料を積み立てて、契約時に取り決めた年齢から受け取りが始まる保険です。
払い込んだ保険料を米ドルや豪ドルに交換して運用する終身保険です。円建ての終身保険よりも大きく資産が増える可能性がありますが、為替レートによっては元本割れになることがあります。
生活に余裕がない人は、教育資金の積み立てと万が一の保障を兼ねられる、低解約返戻型終身保険がおすすめです。外貨建て終身保険は元本割れリスクがあるので、注意が必要です。
いずれの商品も本来は保険なので、教育費用の準備と死亡保障の両方に備えられます。しかし、当然ながら加入すると保険料を払い続けなければならないため、きちんと払っていけるかどうか加入前にしっかり検討しましょう。

学資保険を利用すると効率的に教育資金を準備できますが、学資保険に加入する余裕がない人もいるでしょう。
学資保険に加入する余裕がないときは、家計の見直しをしたり、児童手当を保険料に充てたりする方法もあります。また、祖父母に学資保険の契約お願いすることもできます。ただし、年齢の問題で学資保険を契約できない、契約者と受取人が異なると贈与税が課される、といったこともあるので要注意です。
そのほか、教育資金を準備する方法として、貯蓄、借り入れ、資産運用、その他の生命保険など、学資保険以外にも色々な方法があるので、自分に合ったものを選びましょう。
キーワードで記事を検索