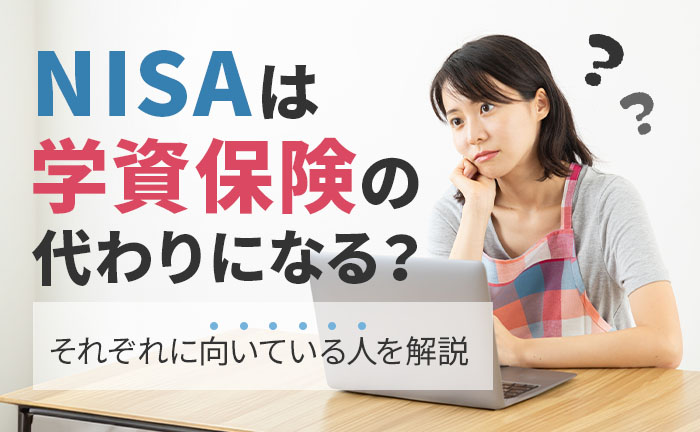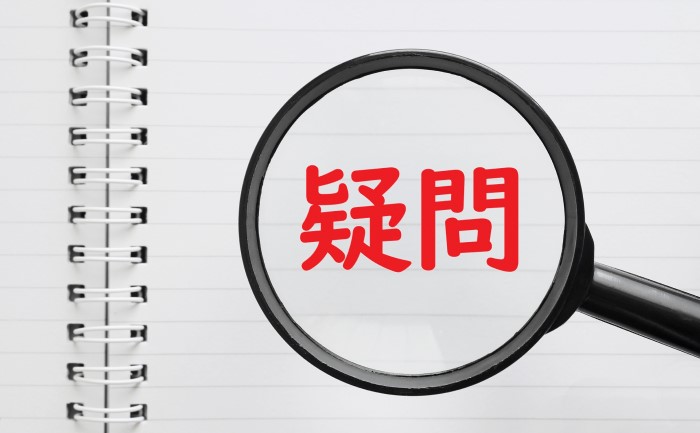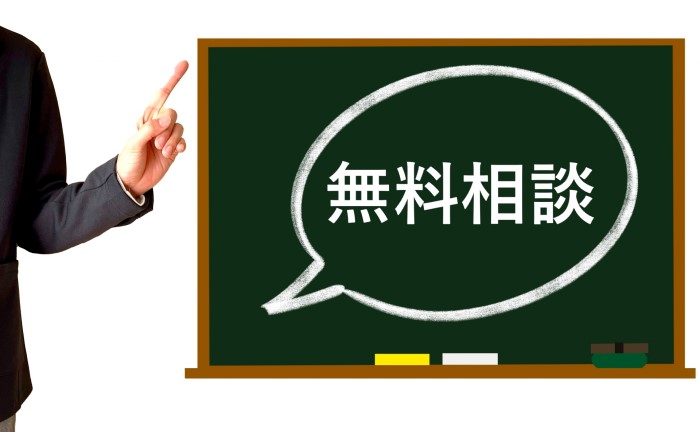学資保険とは、子どもの教育資金を貯めることを目的とした貯蓄型の生命保険です。
子どもの年齢に合わせて満期を設定し保険料を積み立てることで、高校や大学へ進学するタイミングでまとまったお金を受け取れます。受け取ったお金は入学金や授業料などに充てるのが一般的です。
学資保険で教育費を準備するメリット
学資保険で教育資金を準備するメリットは、以下の通りです。
- 計画的に教育資金の準備ができる
- 万一の際は保険料が免除される
- 生命保険料控除の対象である
計画的に教育資金の準備ができる
学資保険は保険金を受け取るタイミングをあらかじめ決めて契約するため、計画的に教育資金の準備ができます。例えば、大学への進学を想定する場合、それに合わせて高校卒業の年に保険金を受け取るように契約するとよいでしょう。
万一の際は保険料が免除される
学資保険は契約期間中に親(契約者)が亡くなった場合、それ以降の保険料の払い込みが免除となり、保障がそのまま継続されて保険金を受け取ることが可能です。
生命保険料控除の対象である
学資保険は生命保険料控除の対象となり、税負担の面でもメリットがあります。保険料によって最大4万円の所得控除を受けられます。会社員や公務員は年末調整で、個人事業主の場合は確定申告を行うことで所得税と住民税の軽減が期待できます。
学資保険で教育費を準備するデメリット
学資保険で教育費を準備する主なデメリットは、以下の通りです。
途中で解約すると損をする
学資保険はあらかじめ設定した満期に保険金を受け取る契約となっています。そのため、契約途中で資金が必要になった場合でも、簡単に引き出すことはできません。早期に解約してしまうと解約返戻金が少なくなり、元本割れを起こす可能性があります。
返戻率が低い
昔の学資保険は返戻率が120%近いこともありましたが、現在は低金利の影響もあり、高くても110%弱の返戻率になっています。学資保険は長期間加入するのが一般的ですが、10年以上加入したにもかかわらず、大してお金が増えない点はデメリットと感じる人もいるでしょう。