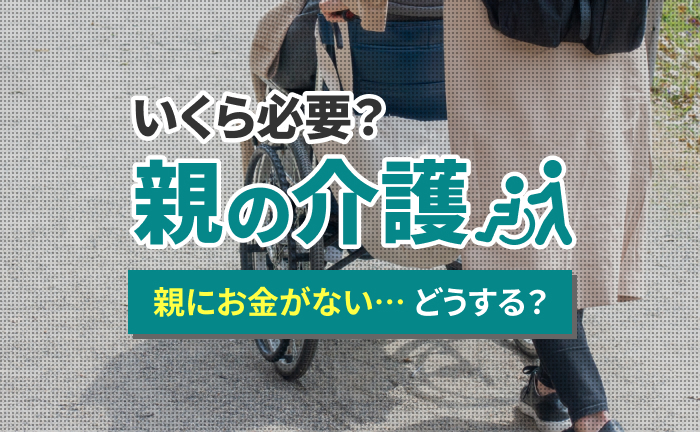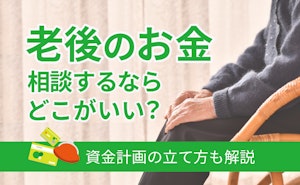親の介護費用については、親自身の収入や貯蓄で賄うのが一般的です。ただし、いつ介護状態になるかは予測できません。また、介護状態になったときに親自身に貯蓄や収入がないことも考えられます。
そのため、親の介護費用を誰が出すかも含め、早めに介護費用について話し合っておくようにしましょう。
親の介護費用について話し合っておきたいこと
- 親が介護に希望する内容
- 親の資産状況
- 家族・兄弟の役割分担
親が介護に希望する内容
両親が介護状態になった際に、どのような介護を希望するのかを知っておくのは重要なことです。
- 自宅で家族による介護を受けたい
- できるだけ在宅サービスを利用したい
- 介護施設へ入所したい
望まない介護サービスを受けることは、ストレスにもつながるので、できるだけ避けることが大切です。希望をかなえるためには、どのような手続きが必要なのか、費用はどのくらいかかるのかを確認しておきましょう。
親の資産状況
前述の通り、一般的に介護費用を捻出するのは親自身です。そのため、まずは親自身が介護状態になった際に、その費用を払えるだけの資産を保有しているかどうかを確認する必要があります。
両親の資産状況を確認する際には、以下の点をチェックしておくとよいでしょう。
- 保有している銀行口座
- 年金収入の状況
- 有価証券の有無
- 生命保険の契約状況
- 不動産などの資産の有無
- 負債の状況
また、ネット銀行やネット証券の口座を持っている場合は、ログインIDやパスワードを把握しておくことも忘れないようにしてください。
家族・兄弟の役割分担
在宅で介護を受けるにしても、施設へ入所するにしても、家族間もしくは兄弟間での役割分担を決めておく必要があります。
公的な介護サービスを受けるには、自治体の窓口に申請しなければなりませんし、医師の診断書なども入手する必要があります。民間の介護サービスを受けるには、契約手続きも必要です。
自治体の窓口への申請は、親の近くに住んでいる方が手続きがスムーズに進みます。また、民間の介護施設に入所するなら、候補を絞って検討する必要があります。資料の入手など、時間がある人が積極的に行うとよいでしょう。
家族の中でキーパーソンを決めておく
親に介護が必要になったときに備えて、あらかじめ「キーパーソン」を決めておくとよいでしょう。
キーパーソンとは、家族代表として病院やケアマネージャーとのやりとりをする人など、介護を進めるにあたっての中心的な役割をする人を指します。
キーパーソンが決まっていないと、突然親が意思疎通できない状況になってしまった場合などに、兄弟姉妹間で揉める可能性が高まります。普段は仲が良くても、「私は遠くに住んでいるから難しい」「子どもの世話だけで手一杯」「一緒に住んでいる人がやるべき」など、押し付け合いに発展してしまうケースもあるので注意が必要です。
介護費用を分担する
キーパーソンを決めると同時に、費用の分担についても話し合っておくことをおすすめします。
キーパーソンが介護費用の全額を負担する必要はありません。むしろ、キーパーソンだけに負担が偏りすぎないよう、それ以外の家族が費用面で積極的に援助するなど、それぞれの負担量を調整することで、円満に介護を進められる可能性が上がるでしょう。
介護費用が不足することがわかった際には、子どもや親族が負担するケースも考えられます。その際の負担割合について、あとでトラブルにならないよう、お互いが納得するまで話し合っておくことが大切です。
子どもや親族が介護費用を負担する場合の負担割合については、以下のようなパターンが考えられます。
- 同じ割合で平等に出す
- 一番お世話になっている人が多めに出す
- お金に余裕のある人が出す
- 物理的なお世話があまりできない人が出す
分担の例
- 長女(親と同居)…キーパーソン。自宅での介護や通院の世話などを担当。費用負担1割
- 長男(遠方在住)…実際の介護はほぼノータッチ。お金は出す。費用負担9割
1人だけが「介護疲れ」になったり、経済的に困窮したりしないよう、家族みんなで支えるためのルールを作っておくと安心です。