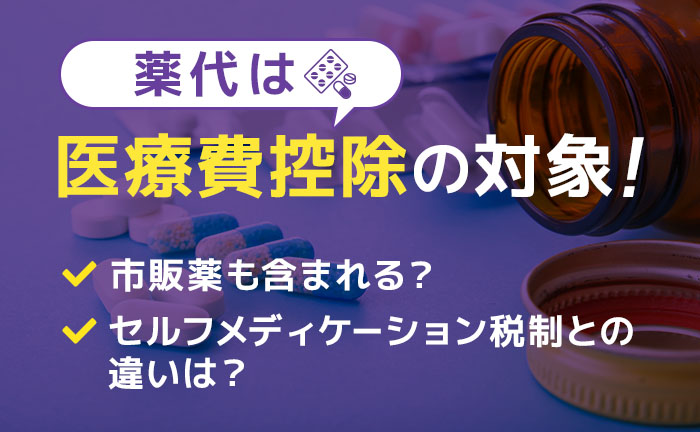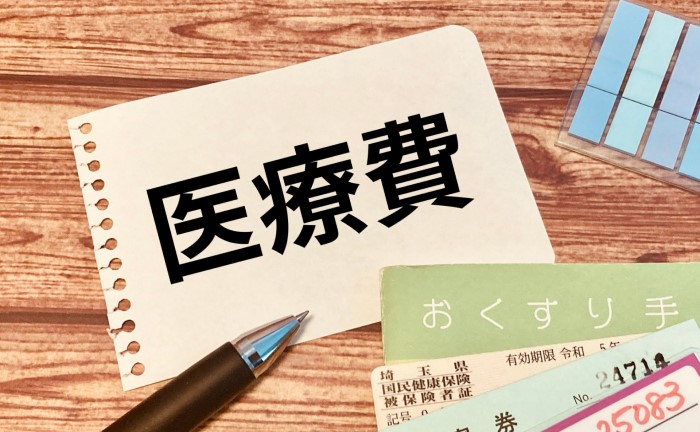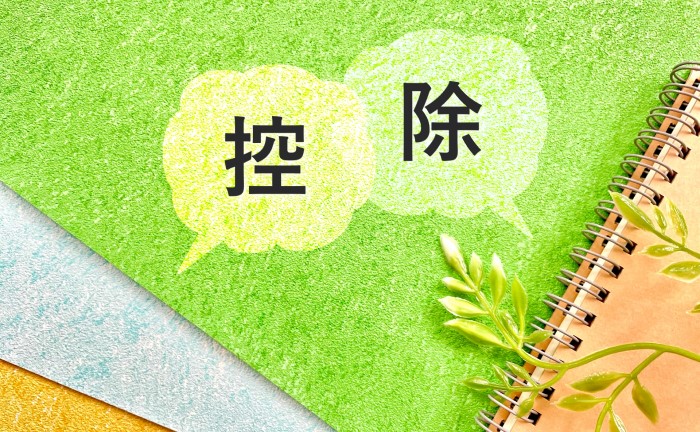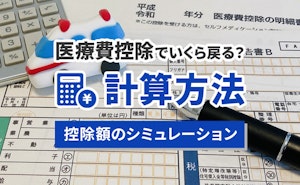医療費控除の申請手順は、以下の通りです。
- 医療費控除の対象になる薬代の金額を計算する
- 確定申告書と医療費控除の明細書を作成し、提出する
- 医療費控除の還付金を確認する
医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。1年間に支払った医療費を集計し、確定申告書と明細書を作成します。そして、翌年の確定申告期限までに提出すれば、後日支払いすぎていた分の税金が還付されます。
1.医療費控除の対処になる薬代の金額を計算する
まずは、年内に支払った薬代の領収書を集め、すべて揃っているか確認してください。加入している健康保険から「医療費通知」が送られてくるので、薬代や医療費通知の金額を合算します。合算した金額が10万円以上であれば、医療費控除の対象となります。
医療費控除額の計算式は以下の通りです。
[医療費控除額]=[1年間で支払った医療費の合計金額(控除対象分の費用)]-[保険金などで補てんされた金額]-[10万円]
(※)総所得200万円未満の場合は「10万円」の代わりに「総所得×5%」を差し引く
例えば、1年間で要した医療費合計が20万円で、そのうち受け取った保険金が3万円だったとします。その場合の医療費控除額は、次の通りです。
年収200万円以上の場合
20万円(医療費)-3万円(保険金)-10万円=7万円
年収200万円未満の場合(所得150万円で計算)
20万円(医療費)-3万円(保険金)-7万5000円=9万5000円
2.確定申告書と医療費控除の明細書を作成&提出する
「確定申告書」と「医療費控除の明細書」を入手しましょう。税務署の窓口で入手できますが、国税庁のサイトからPDFやExcelデータとしてダウンロードも可能です。
これらの明細書は手書きで作成することも可能ですが、Excelを使用しての作成がおすすめです。Excelを使用すれば、計算も自動的に行われるため、ミスも防ぎやすくなるでしょう。
次に「医療費控除の明細書」を作成します。
明細には、領収書を確認しながら、医療を受けた人の名前、病院名、医療費の区分、保険などで補填される金額を記入します。通院にかかった交通費なども忘れずに記入してください。
すべての記入が完了すると、Excelデータであれば自動で医療費控除額が算出されます。手書きの場合は、医療費控除の明細書の「控除額の計算」を基に控除額を計算してください。
医療費控除額が算出されれば、その金額を確定申告書の「医療費控除」欄に記入すれば書類は完成です。
作成した「医療費控除の明細書」は確定申告書と一緒に税務署に提出します。領収書やレシートを添付する必要はないですが、5年間は保管するようにしてください。
確定申告の提出期間は翌年2月16日~3月15日です。
3.医療費控除の還付金を確認する
確定申告書の提出後、還付金は申請から約1ヵ月~1ヵ月半後に、指定した銀行口座に振り込まれるか、ゆうちょ銀行・郵便局で受け取ることが可能です。
還付されるのは、源泉徴収票に記載されている所得税額から、確定申告した所得税額を差し引いた金額です。
還付額のシミュレーションについては、『医療費控除でいくら戻る?計算方法と控除額のシミュレーション』も参考にしてください。