出産を控え、気になるのが経済面での負担でしょう。「出産のために支払った費用は医療費控除の対象になるの?」「どれぐらい還付されるの?」など疑問を持っている人はいませんか?
出産費用は医療費控除の対象に含まれます。ただし、すべての出産費用が医療費控除の対象になるわけではありません。
この記事では、医療費控除で還付される出産費用について解説します。
- 医療費控除の対象になる出産費用
- 医療費控除で戻ってくる還付金の計算方法
- 医療費控除の申請方法
※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

【監修】株式会社RKコンサルティング河合 克浩

一般企業、外資系金融機関を経て、現在はファイナンシャルプランナー(FP)として年間150件超のお金の相談に対応。難しく感じる経済やお金の話をわかりやすく説明することに定評がある。夢を実現するため相談者に寄り添い、人生が豊かになるサポートを心がけている。
出産を控え、気になるのが経済面での負担でしょう。「出産のために支払った費用は医療費控除の対象になるの?」「どれぐらい還付されるの?」など疑問を持っている人はいませんか?
出産費用は医療費控除の対象に含まれます。ただし、すべての出産費用が医療費控除の対象になるわけではありません。
この記事では、医療費控除で還付される出産費用について解説します。
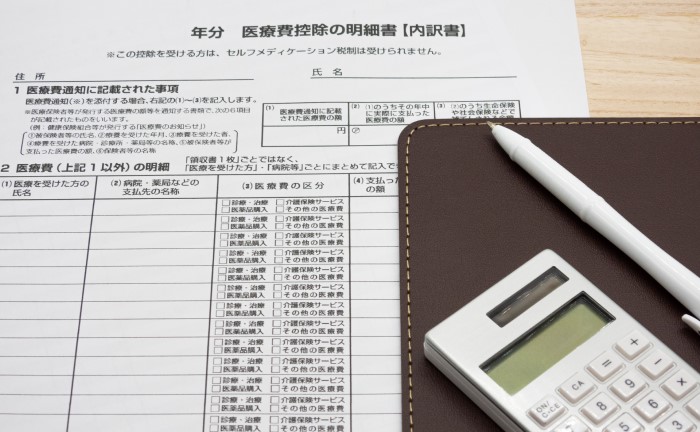
医療費控除とは、その年の1月1日~12月31日に、自分および自分と生計を一つにする配偶者や親族のために支払った医療費について、一定額を超える部分について所得控除が受けられる仕組みです。
所得控除なので、一定額を超えて支払った医療費がすべて戻ってくるわけではありません。また、医療費控除の適用には確定申告が必要です。該当する場合には、期間内に申告するようにしてください。
医療費控除の対象となる費用は、以下の通りです。

医療費控除の対象には、出産費用も含まれます。ただし、すべての出産費用が医療費控除の対象になるわけではありません。
ここでは、医療費控除の対象となる妊娠・出産費用および、対象とならない妊娠・出産費用について解説します。医療費控除の確定申告を行う際には、自分が支払った費用がどちらに該当するかを確認してください。
医療費控除の対象になる妊娠・出産費用は、以下の通りです。
妊娠中の虫歯や歯周病は早産のリスクを高める可能性があるといわれており、これらの治療の目的で歯医者に通った場合の費用は医療費控除の対象です。
また、出産で入院するにあたり、電車やバスなどの通常の公共交通機関で病院に行くのが困難なためタクシーを利用した場合、そのタクシー代も医療費控除の対象になります。
一方で、以下に該当する費用は医療費控除の対象外です。
実家で出産する際の帰省交通費は対象外ですが、実家から出産する病院への交通費は医療費控除の対象です。

医療費控除の計算にあたって、保険金などで補填される金額は、実際に支払った医療費から差し引かれます。
例えば、加入している健康保険組合や国民健康保険などから支払われる出産育児一時金も「保険金などで補填される金額」になります。ほかにも、以下のものが該当します。
なお、以下の費用は保険などで補填される金額に該当しません。
出産手当金は特に間違えやすいため、誤って差し引かないよう注意してください。
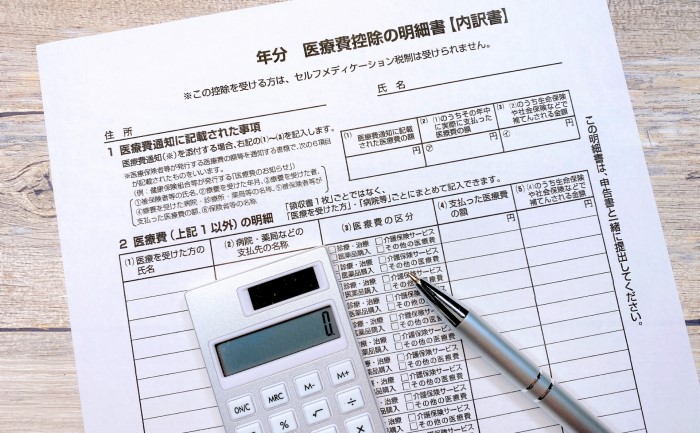
医療費控除は所得控除の一部です。適用を受けるためには医療費控除の額を計算し、確定申告しなければなりません。
ここでは、実際に医療費控除の適用を受ける際の控除金額と還付金の計算方法について解説します。
医療費控除額は、以下の計算式に基づいて計算します。
[医療費控除額]=[1年間で支払った医療費の合計金額(控除対象分の費用)]-[保険金などで補てんされた金額]-[10万円]
ただし、総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%が差し引かれます。
例えば、1年間の医療費合計が20万円で、そのうち受け取った保険金が3万円だったとします。その場合の医療費控除額を計算すると次の通りです。
20万円(医療費)-3万円(保険金)-10万円=7万円
20万円(医療費)-3万円(保険金)-7万5000円=9万5000円
厚生労働省の資料によると、2021年の出産費用(自然分娩)の平均は約52万円です。出産費用が年間平均1%程度で増加していることを加味すると、2023年の平均出産費用(自然分娩)は約53万円になると考えられます。
健康組合や国民健康保険から支払われる出産一時金は50万円です。
これらの値を下表に当てはめると、医療費控除額が求められます(所得200万円以上の場合)。
| 出産にかかった費用 | 53万円 |
|---|---|
| 保険金などで補てんされる金額 | 50万円 |
| 計算式 | 53万円-50万円-10万円=-7万円 |
| 医療費控除額 | 0円 |
帝王切開などの異常分娩の場合は、保険が適用されるため、自然分娩に比べ自己負担額が少なくなる傾向にあります。実際に、異常分娩の場合、自然分娩に比べてかかる費用が3万円程度少なくなっていることからも、平均は50万円程度であると考えられます。
異常分娩であっても、受け取れる出産一時金は50万円なので、医療費控除額は以下の通りです(所得200万円以上の場合)。
| 出産にかかった費用 | 50万円 |
|---|---|
| 保険金などで補てんされる金額 | 50万円 |
| 計算式 | 50万円-50万円-10万円=-10万円 |
| 医療費控除額 | 0円 |
このように、出産費用はかかるものの、高額手当である出産一時金が受け取れるため、出産にかかる費用では、医療費控除額が発生するケースはあまりありません。
医療費控除の額がわかれば、還付される金額の把握が可能です。還付される金額は以下の式で求めます。
還付金額=医療費控除額×所得税率
ここで用いる所得税率は、申告する人の所得によって異なります。例えば、課税される所得金額が300万円なら税率は10%、400万円だと20%です。
医療費控除額が20万円、課税所得が300万円の場合、課税所得が300万円の人の税率は10%です。還付される金額は20万円×10%=2万円になります。
医療費控除額が20万円、課税所得が500万円の場合、課税所得500万円の所得税率は20%です。還付される金額は20万円×20%=4万円になります。
医療費控除は1月1日~12月31日までの医療費を対象とするため、妊娠から出産までの間に年を越すと医療費控除の対象額が1月1日からリセットされて、結果的に医療費控除額が減る可能性があります。
以下は、年をまたぐことにより、医療費控除が適用されない例を示した表です。2022年春に妊娠し、2023年2月に出産。出産でかかった医療費合計は57万円、医療費の補てんとして出差育児一時金50万円を受給した、と設定します。なお、比較しやすいように、このケースでは2022年と2023年の妊娠・出産以外の医療費はないものとして考えます。
| 2022年1月1日~12月31日まで | 2023年1月1日~12月31日まで | |
|---|---|---|
| 条件 | 期間中にかかった医療費:7万円 医療費の補てん:0円 |
期間中にかかった医療費:50万円 医療費の補てん:50万円(出産育児一時金) |
| 医療費控除額の計算 | 7万-10万=-3万(円) | 50万-50万-10万=-10万(円) |
| 医療費控除額 | 0円(医療費控除適用なし) | 0円(医療費控除適用なし) |
このような設定では、2022年と2023年ともに医療費控除が受けられないことになります。妊娠や出産の時期は予測が困難ですが、条件によっては医療費控除が受けられない可能性もあることを見越しておきましょう。

出産費用を含む医療費控除の申請の流れは、以下の通りです。
医療費控除については、『医療費控除でいくら戻る?計算方法と控除額のシミュレーション』も参考にしてください。

医療費控除の対象には、出産費用も含まれます。ただし、中にはマタニティマッサージやヨガの費用など対象とならないものもあるので注意してください。また、出産一時金は保険として補填される費用として扱われる点も覚えておきましょう。
医療費控除の適用を受ける際には、確定申告書と医療費控除の明細書を作成し、管轄の税務署に提出しなければなりません。申告が必要なときは、早めに書類の作成に取り組むようにしてください。
キーワードで記事を検索