年が明けると確定申告の時期です。個人事業主やフリーランスになりたての人は、初めての確定申告であわてないよう、しっかりと準備をしておくことが大切です。
この記事では、確定申告に向けて、事前に準備をしておいたほうが良いことや、申請できる各種控除について解説します。
※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
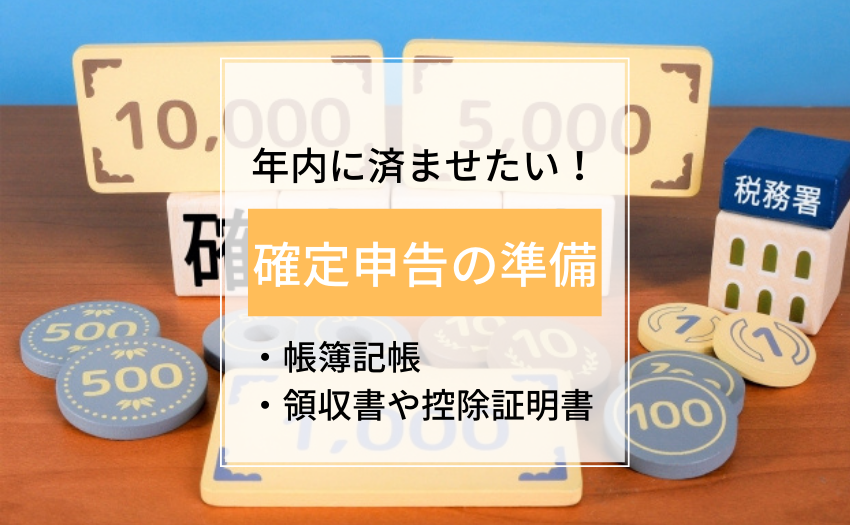
マネーFix 編集部

マネーFix 編集部は、FP有資格者や「ビジネス書」や「学習参考書」などさまざまなジャンルの編集経験者で構成されています。わかりやすく確かな情報を発信し「人生におけるお金の決断」の判断基準となる、信頼できるメディアを目指します。
年が明けると確定申告の時期です。個人事業主やフリーランスになりたての人は、初めての確定申告であわてないよう、しっかりと準備をしておくことが大切です。
この記事では、確定申告に向けて、事前に準備をしておいたほうが良いことや、申請できる各種控除について解説します。
確定申告とは、毎年1月1日〜12月31日の1年間に発生した所得金額と所得金額に対する所得税などの金額を計算して、所得を確定させる手続きのことです。
源泉徴収された税金や予定納税額などがあった際には、確定申告をすることで過不足分が精算される仕組みとなっています。
また、確定申告をする際の所得税の金額は「(売上-経費-控除)× 税率」で計算することが可能です。
売上・経費・控除になる内容を漏れなく確認して、確定申告書に記入しましょう。
確定申告の申請期間は、毎年2月16日〜3月15日です。
万が一、期間内に提出できなかった場合は、延滞税や無申告加算税などが課されることがあるため、注意が必要です。
確定申告をする必要がある人は、主に以下の通りです。
会社員の場合は原則として勤務先の年末調整で処理をしてくれるため、確定申告の必要がありません。
ただし、例外として年間2,000万円以上の給与所得がある人は、自分で確定申告を行う必要があります。
そのほかにも、不動産収入や株取引で収入がある人や、住宅ローン控除などの各種控除を受けたい人も確定申告をする必要があるため、注意しましょう。
個人事業主やフリーランスで事業収入がある人は必ず確定申告を行わなければなりません。
個人事業主やフリーランスは、会社員のように自動的に年末調整をしてくれる制度はないため、個人事業主やフリーランスになりたての人は注意が必要です。
確定申告には、毎年必ずやっておいたほうが良いことや準備しておくべき書類があります。
確定申告前にやっておいたほうが良いことは以下の2つです。
帳簿とは、売上などの収入金額や事業運営にかかった仕入や経費に関する事項について、お金の流れを記載した記録簿のことです。
確定申告の直前に1年間の記録をまとめて記帳することは非常に大変な作業です。
毎日が望ましいですが、難しければ1週間〜1ヵ月の間で、こまめに記帳することをおすすめします。
なお、記帳をするときは、取引ごとではなく日付ごとの合計金額でまとめて記帳しても良いことになっているため、頭に入れておきましょう。
事業運営で発生した領収書や、各種控除証明書を保管することも忘れてはいけません。
経費として使える領収書には、事業の必要経費として購入した事務用品や、交通費、医療費、クライアントとの会食などさまざまです。
月ごとや勘定科目ごとにファイリングをして保管することをおすすめします。
また、生命保険料やふるさと納税などの各種控除証明書も確定申告の際に必要になるため、大切に保管しましょう。
確定申告の際に申請できる各種控除の一例を紹介します。
医療費控除とは、申告する本人や家族の分を含めて1年間の医療費が一定額を超えた場合に、所得税の還付が受けられる制度のことです。
医療費控除の対象は以下の通りです。
なお、予防接種費や美容整形費、レーション費など、病気やケガに関わりのない治療費については医療費控除の対象にはなりません。
寄附金控除とは、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに特定寄附金を支出した場合に、所得税の還付が受けられる制度のことです。
寄附金控除の対象は以下の通りです。
また、認定NPO法人や政治活動、特定公益増進法人などの寄付金に関しては、寄付金控除または寄付金特別控除のいずれかで控除額が多いほうを選ぶことが可能です。
扶養控除とは、納税者に控除対象扶養親族となる人がいる場合に、所得税の還付が受けられる制度のことです。
控除対象扶養親族は、本年の12月31日時点で16歳以上の子どもや親、親族のことを指します。
扶養親族は、以下のすべてに該当する人です。
老人以外であれば同居かどうかは問われないため、学校に通うために1人暮らしをしていて、仕送りを受けている子どもなども含まれます。
雑損控除とは、災害や盗難、横領によって資産について損害を受けた場合などに所得控除を受けられる制度のことです。
雑損控除となる対象資産は以下の通りです。
「事業用資産」、「棚卸資産」、「趣味や娯楽の目的で所有する不動産」、「書画・骨董・美術工芸品・貴金属などの価額が30万円を超えるもの」などは対象になりません。
住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローンなどを利用してマイホームを新築で購入もしくは増改築をした場合に、年末の残高に応じて所得税額から控除する制度のことです。
住宅借入金等特別控除の適用要件は以下の通りです。
住宅借入金等特別控除の控除率や控除期間は、住宅の購入時期や入居時期によって異なるため、国税庁のホームページなどで確認しましょう。
キーワードで記事を検索