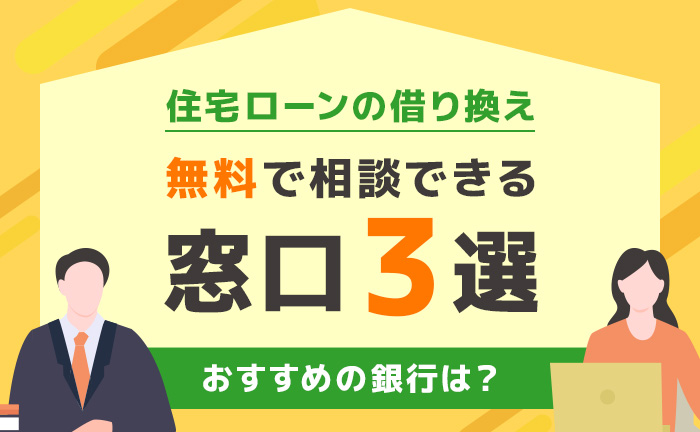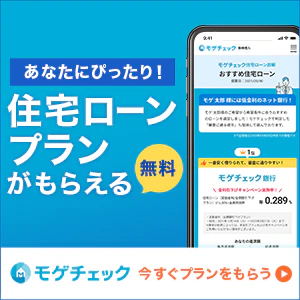住宅ローンの借り換えの流れは、以下の通りです。
- 借り換え先のローンを選ぶ
- 借り換え先のローンに申し込む
- 審査
- 借り換え手続き
- 返済計画に基づいて返済開始
1.借り換え先のローンを選ぶ
借り換え先の候補となる住宅ローン商品を取り扱っている金融機関を複数ピックアップして内容を比較し、利用する金融機関を選びます。
借り換え先のローンを選ぶ際のポイントは、以下の通りです。
- いまよりも金利が低いか
- 金利タイプが複数用意されているか
- 諸費用はどのくらいかかるか
- 団体信用生命保険の内容など、サービスが充実しているか
多くの金融機関では、借り換えを検討する際に利用できるシミュレータを用意しています。借り換えたあとの利息削減効果や諸費用などが把握できるので、シミュレーションを行ってから決めるのがおすすめです。
2.借り換え先のローンに申し込む
借り換え先の金融機関が決まったら、その金融機関に住宅ローンの借り換えを申し込みます。
申し込みや審査に必要な主な書類は、以下の通りです。
- 本人確認書類:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
- 収入証明書類:源泉徴収票、確定申告書の控えなど
- 住んでいる住宅に関する書類:不動産登記簿謄本、売買契約書など
- 現在のローンの返済状況がわかる書類:返済予定表、引き落とし口座の写しなど
3.審査
借り換え先の住宅ローンの審査項目は、いまのローンを借りたときと基本的には変わりません。主な審査項目は、以下の通りです。
- 年収
- 勤務先
- 雇用形態
- 勤続年数
- 申し込み時の年齢
- 健康状態
いまの住宅ローンを借りたときよりも収入が下がっていたり、転職したばかりだったりすると、審査に不利になる可能性があります。
また、忘れてはならないのが健康状態です。住宅ローンを組む際には団体信用生命保険へ加入しますが、新たなローンで団体信用生命保険の加入が認められないケースがあります。特に「直前に大病を患った」「持病が悪化した」などの場合には、借り換えができない可能性もあるので注意しましょう。
そういった場合は、申し込み時期をずらすことで団体信用生命保険へ加入できることがあります。また持病が悪化した場合でも、病気の程度によっては、団体信用生命保険に加入できるケースもあるので、詳しくは借り換え先の金融機関に相談してください。
4.借り換え手続き
借り換え先の住宅ローンの審査に通ったら、契約手続きに入ります。
契約に必要な書類を提出し、住宅ローンの手続きに関する諸費用の支払いのほか、借り換え元の金融機関に残債を支払い、解約手続きを行う流れです。
手続きの際は、金銭消費貸借契約書を交わすほか、抵当権抹消登記および設定登記を行わなければなりません。そのため、手続きの際には、金融機関にて司法書士も交えて行われるのが一般的です。
5.返済計画に基づいて返済開始
手続きが完了したら、新たなローンでの返済が開始します。毎月の返済額が家計を圧迫しないような、無理のない返済計画を立て、それに沿って返済を続けることが大切です。
無理のない返済計画を立てるためには、月々の返済額を手取りの20%程度に抑えるようにし、さらに今後予想されるイベントがあるなら、それに充てる資金を貯蓄できるよう余裕を持たせておきましょう。
また、一時的にまとまった収入が入った際には繰り上げ返済を活用するなど、できるだけ利息負担を減らせるよう心がけてください。