子どもの教育資金のうち、一般的に多くのお金がかかるのが大学資金です。教育資金の準備にはさまざまな方法があり、奨学金制度もそのうちのひとつです。
奨学金の基本的な仕組みを理解しておくと、選択肢の幅が広がります。この記事では、JASSO(日本学生支援機構)の奨学金について解説します。
※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
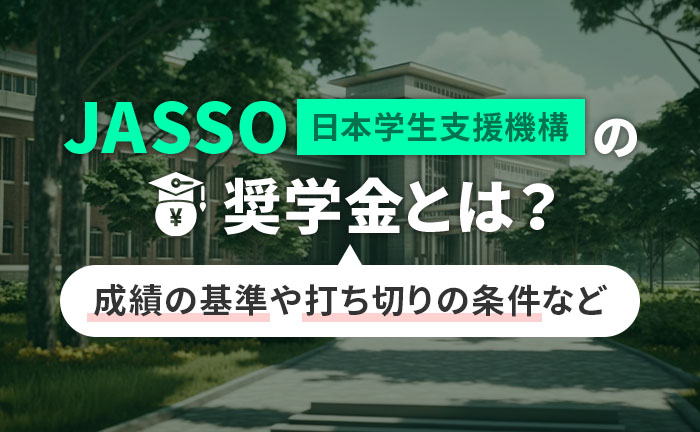
マネーFix 編集部

マネーFix 編集部は、FP有資格者や「ビジネス書」や「学習参考書」などさまざまなジャンルの編集経験者で構成されています。わかりやすく確かな情報を発信し「人生におけるお金の決断」の判断基準となる、信頼できるメディアを目指します。
子どもの教育資金のうち、一般的に多くのお金がかかるのが大学資金です。教育資金の準備にはさまざまな方法があり、奨学金制度もそのうちのひとつです。
奨学金の基本的な仕組みを理解しておくと、選択肢の幅が広がります。この記事では、JASSO(日本学生支援機構)の奨学金について解説します。

給付型奨学金は、2020年4月に新設された奨学金制度で、学力基準と収入基準を満たしていれば受け取ることができます。
JASSOの給付型奨学金の学力基準と家計基準は以下の通りです。
上記のいずれかに該当していればよいため、必ずしも成績上位者でなくてもよく、学力基準を満たすことが可能です。
| 支援区分 | 収入基準 |
|---|---|
| 第1区分 | 生計維持者の市町村税所得割が非課税であること |
| 第2区分 | 生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上2万5600円未満 |
| 第3区分 | 生計維持者の支給額算定基準額の合計が2万5600円以上5万1300円未満 |
収入基準は、世帯構成によって異なるため、JASSOが公開している「進学資金シミュレーター」で確認してみましょう。また、上記に加えて、学生と生計維持者の資産総額の合計が2000万円未満である必要があります。
給付型奨学金には、返済義務がありません。まずは給付奨学金の基準を満たしているかどうかを確認し、満たしていなければ、貸与奨学金を検討します。給付奨学金と貸与奨学金を併用することも可能です。
給付上限金額は、進学先が国公立か私立かによって異なります。
| 校種 | 区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
|---|---|---|---|
| 大学短期大学専修学校 | 第1区分 | 2万9200円 | 6万6700円 |
| 第2区分 | 1万9500円 | 4万4500円 | |
| 第3区分 | 9,800円 | 2万2300円 | |
| 高等専門学校 | 第1区分 | 1万7500円 | 3万4200円 |
| 第2区分 | 1万1700円 | 2万2800円 | |
| 第3区分 | 5,900円 | 1万1400円 |
| 校種 | 区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
|---|---|---|---|
| 大学短期大学専修学校 | 第1区分 | 3万3800円 | 7万5800円 |
| 第2区分 | 2万5600円 | 5万600円 | |
| 第3区分 | 1万2800円 | 2万5300円 | |
| 高等専門学校 | 第1区分 | 2万6700円 | 4万3300円 |
| 第2区分 | 1万7800円 | 2万8900円 | |
| 第3区分 | 8,900円 | 1万4500円 |
JASSOの貸与型奨学金には無利息の「第一種」と、有利息の「第二種」があります。第一種と第二種は併用することも可能です。
貸与型奨学金の学力基準と家計基準は、以下の通りです。
貸与金額は、進学先別に決められた額の中から選びます。詳細は、下表の通りです。
| 区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
|---|---|---|
| 国公立 | ・2万円 ・3万円 ・4万5000円 |
・2万円 ・3万円 ・4万円 ・5万1000円 |
| 私立 | ・2万円 ・3万円 ・4万円 ・5万4000円 |
・2万円 ・3万円 ・4万円 ・5万円 ・6万4000円 |
| 区分 | 貸与額 |
|---|---|
| 大学 | 2万~12万円で1万円刻み |
| 短期大学 | 2万~12万円で1万円刻み |
| 大学院 | ・5万円 ・8万円 ・10万円 ・13万円 ・15万円 |
| 高等専門学校 | 本科4・5年生は2万~12万円で1万円刻み |
| 専修学校 | 2万~12万円で1万円刻み |
日本学生支援機構(JASSO)以外で返済不要で支給される奨学金については、『給付型奨学金一覧』で、多くの企業・財団法人の奨学金制度を紹介しています。
あわせて読みたい
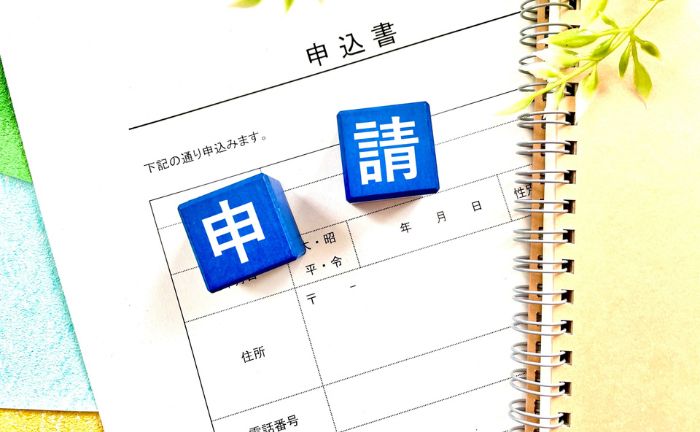
次に、JASSO(日本学生支援機構)奨学金の成績基準や申請手続きの流れや、審査で見られる成績の範囲について解説します。
前述の通り、奨学金が受けられる成績の基準は、第1種が平均3.5以上、第2種が平均水準以上となっています。審査の対象となる成績の範囲は、予約採用と在学採用とで異なります。
ただし、基準は成績だけではないため、成績で基準を満たさなくても、奨学金の対象となる可能性はあります。
奨学金を受けるために必要な提出書類は以下の通りです。
このうち、「提出書類一覧表」と「給付奨学金確認書/貸与奨学金確認書」は全員が提出必須です。ほかの書類は、該当者のみが提出します。また「マイナンバーの代用書類」は、専用封筒に入れて日本学生支援機構に郵送します。
奨学金を申し込む流れは以下の通りです。
手続きが完了すると、「採用候補者決定通知」が交付されます。奨学金を受け取るためには、進学後に正式に申込をします。その際に「採用候補者決定通知」が必要となります。

奨学金は入学時の判定だけでなく、毎年3月に在学中の学業成績などによる判定(適格認定)が行われ、次年度の奨学金について審査されます。給付型奨学金の場合は家計基準についての審査もあります。
適格認定の区分には、「廃止」「停止」「警告」「継続」があり、給付型奨学金の「廃止」と「警告」の成績基準は次の通りです。
なお3ヵ月未満の停学や訓告処分を受けた場合は、適格認定の区分が「停止」となり、停学や訓告処分の終了後に支給が再開されます。
適格認定の区分が「廃止」になった場合、給付奨学生の資格を失い、奨学金を受け取れなくなります。「廃止」の成績基準は以下の通りです。
適格認定の区分が「警告」になった場合、給付奨学金は継続されます。しかし、次回の適格認定で「警告」と認定されると、「廃止」となります。「警告」の成績基準は以下の通りです。
貸与型奨学金の場合は、「人物」「学業」「経済状況」について審査されます。審査基準は以下の通りです。
適格認定の区分は、給付型奨学金と同様、「廃止」「停止」「警告」「継続」があります。このうち、「警告」では、奨学金は継続されますが、学業成績が向上しなければ、次回以降の奨学金が「停止」または「廃止」になります。

万一、奨学金が「廃止」となり、教育資金が不足すると懸念される場合、銀行が取り扱う教育ローンや、国の教育ローンが選択肢となります。
教育ローンは、一般的なローンと異なり、金利が低めに設定されています。銀行の教育ローンの金利は2~5%で、1000万円以上の借入が可能です。一方、国の教育ローンは、銀行の教育ローンより金利は低いですが、借入金額の上限は350万円です。
国の教育ローンについては『国の教育ローンの利用条件や審査基準』で詳しく解説されています。ぜひ参考にしてください。
銀行の教育ローンの場合、同じ銀行で住宅ローンなどのほかのローンを利用しているなどの要件を満たしていると、金利が優遇される場合もあります。ただし、教育ローンは学業基準だけでなく、家計基準で対象外となる可能性もあるため、事前に調べておくとよいでしょう。
銀行の教育ローンについて詳しく知りたい人は、『おすすめの教育ローンランキング』を参考にしてみてください。

教育資金の準備の仕方には、奨学金や教育ローンなどがあります。給付奨学金、貸与奨学金、教育ローンの順番に検討するとよいでしょう。ただし、給付型奨学金以外は、返済義務があるため、利用する前に返済計画を立てておくようにしましょう。
また、奨学金は申込時点だけでなく、在学中も成績などの基準を満たす必要があります。奨学金を申し込む場合は、審査基準を確認し、学業を怠らないように気をつけましょう。
キーワードで記事を検索