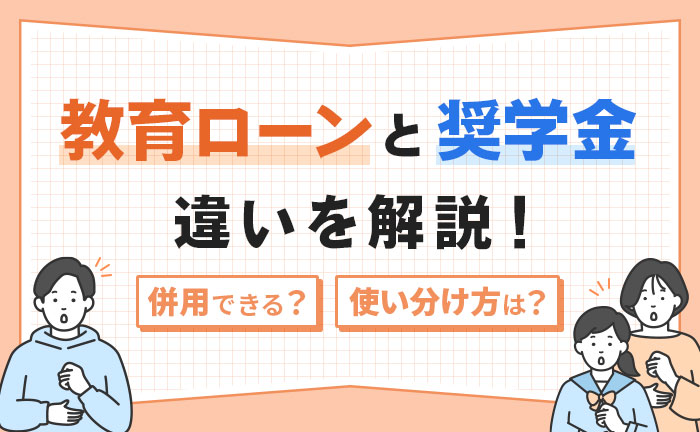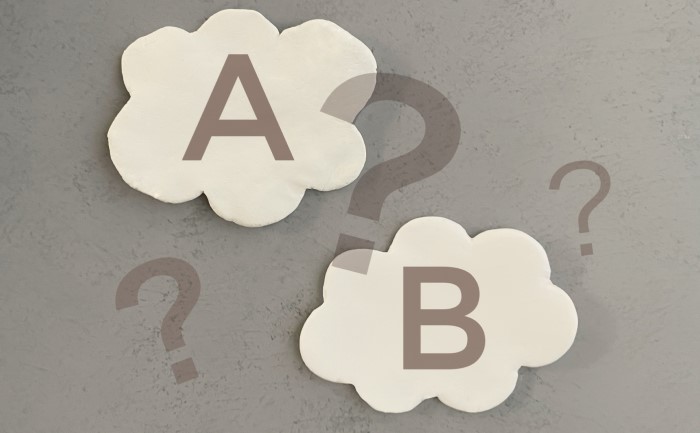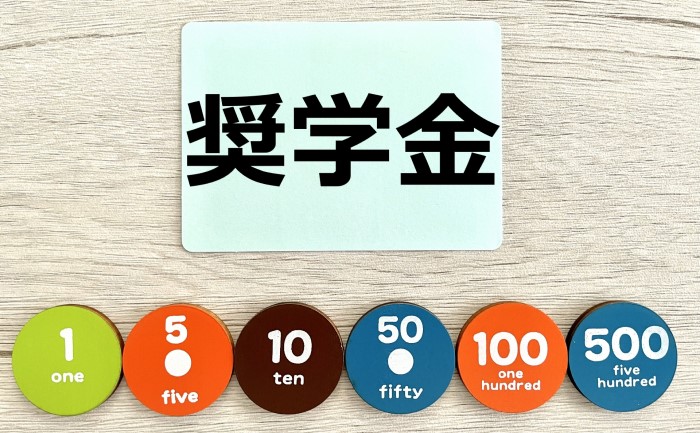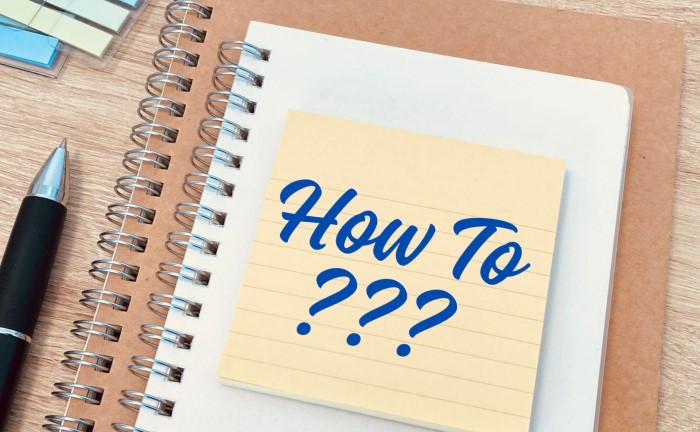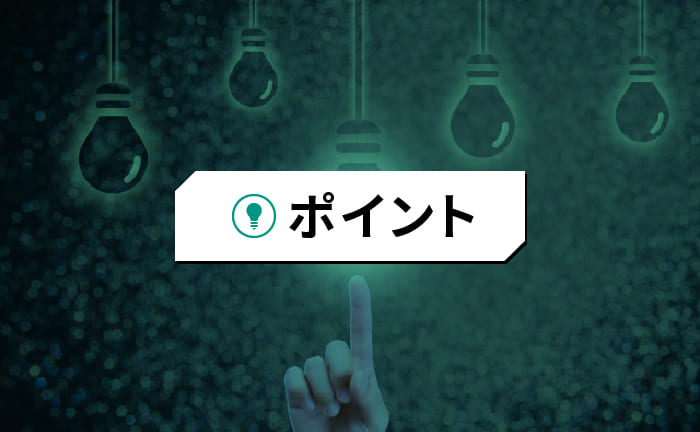ここでは、教育ローンと奨学金をどのように使い分ければよいのか説明します。
使い分けのポイントは、お金を受け取るタイミングです。教育ローンと奨学金はお金を受け取るタイミングが異なります。
- 教育ローン:審査に通ったあとに受け取り
- 奨学金:学校に入学してから受け取り
お金が必要になるタイミングはいつ?
お金が必要になるタイミングによって、教育ローンを利用するか奨学金を利用するかが異なります。
具体的には、入学前に必要な費用が不足しているなら教育ローンの利用がおすすめです。入学後に必要な費用が不足しているなら奨学金の利用を考えるようにしましょう。
入学前に必要な費用が不足している場合
奨学金を受け取れるのは入学してからです。そのため、入学までに支払う必要のある受験費用や入学金、前期の授業料などは、奨学金以外の手段で調達しなければなりません。貯蓄や学資保険などで賄えれば問題ないですが、不足する場合は教育ローンの利用も考えましょう。
教育ローンを検討するにあたっては、まずは国の教育ローンへ申し込めるかを確認してみましょう。申し込み条件を満たしているなら、国の教育ローンの方が金利は低くおすすめです。ただし、借入限度額上限が低めに設定されている点には注意してください。
入学後に必要な費用が不足している場合
後期の授業料や教材費用など、入学後に必要な費用が不足しているなら、奨学金と教育ローンのどちらも利用可能です。
奨学金は所得基準と学力基準を満たせば申し込め、返済不要の給付型や無利息の第一種奨学金を利用できれば、卒業後の返済負担も少なくなります。
奨学金だけでは不足する場合は、教育ローンとの併用も考慮しましょう。
誰が返済する?
奨学金と教育ローンのどちらを選ぶかは、誰が返済するかによっても異なります。
奨学金の場合
奨学金は、学生本人が借入し、卒業後に返済する仕組みです。学生本人に返済の負担をかけたくない場合は、教育ローンを選ぶことをおすすめします。
教育ローンの場合
教育ローンは、親が借入して、親が返済します。基本的に借入した翌月から返済が始まりますが、在学中は利息だけの返済でよいとする教育ローンもあります。
在学中は色々とお金がかかるため、利息だけの支払い期間が設けられていることはありがたいかもしれませんが、卒業後の返済額が一気に増える点には注意が必要です。
おすすめの使い分け方
教育ローンと奨学金それぞれに向いている人の特徴について紹介します。
教育ローンが向いている人
教育ローンが向いている人は、以下に当てはまる人です。
- 親に返済能力がある人
- まとまった費用が必要である人
- 年収が高く奨学金が条件を満たさない人
- 学費の高い学校・学科に進学する人
- 幅広い用途で利用したい人
奨学金は、基本的に教育に関する経済的な困窮を緩和するための制度です。そのため、審査においては所得基準を満たさなければなりません。年収が高い場合は基準に当てはまらず、奨学金を利用できないケースもあるでしょう。
また、教育ローンは奨学金よりも借入上限額が高めに設定されているほか、借入した資金使途も幅広く設定されています。そのため、高額な費用が必要な人や、入学金や授業料以外の費用にも使いたい人に向いています。
奨学金が向いている人
奨学金が向いている人の特徴として挙げられるのは、以下の点です。
- 金利負担を軽減したい人
- 親が返済できない人
- 学業の成績が優秀な人
- 収入が低く、民間の教育ローンの借入が難しい人
奨学金は所得基準を満たさなければ申し込めないため、低所得世帯や一人親世帯などが利用しやすい仕組みになっています。また、奨学金の返済は学生本人が卒業後に行う必要があります。