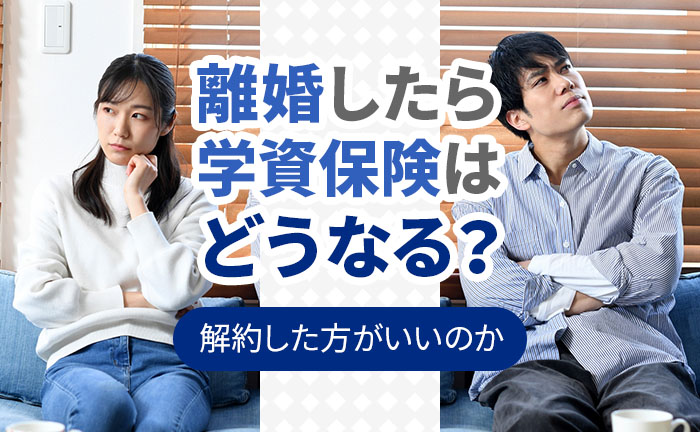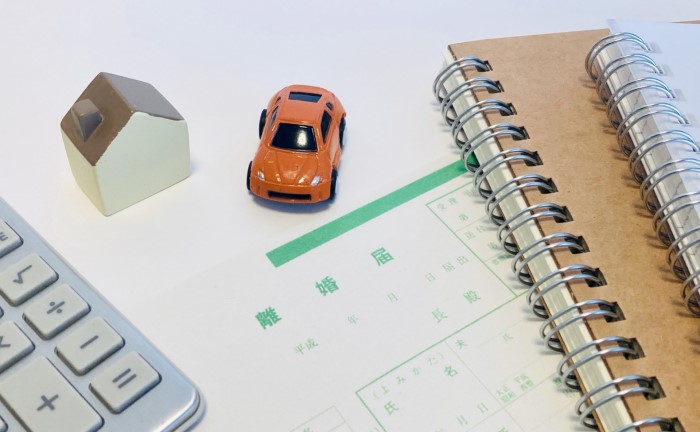離婚後に学資保険を継続する場合、名義変更が必要なことがあります。名義変更の要否は、保険契約者と親権、保険金の受取人によって判断します。
保険契約者と親権および受取人が異なれば、名義変更が必要になります。一方で、保険契約者と親権および受取人が同じであれば、名義変更は不要です。
名義変更をしなかった場合のリスク
離婚後に名義変更の手続きをしなかった場合のリスクを紹介します。
学資保険を勝手に解約される
名義人は親権者の同意なしに学資保険を解約することができます。解約すると解約返戻金を受け取れます。そのため、満期前に解約して受け取った解約返戻金を持ち逃げされるリスクがあります。
正しく振り込まれない
満期のときに保険契約者と受取人が違う場合には、祝い金や満期金を親権者がもらえない可能性があります。
受け取る際に贈与税が発生する
保険契約者と受取人が異なると、満期で受け取った金額を受取人に贈与したことになります。贈与税の基礎控除となる年間110万円を超えた部分に、贈与税が課税されます。
保険料滞納や解約のコントロールができない
保険契約は、保険契約者の意思で解約や保険料の支払方法の変更などができます。
しかし親権者と契約者が異なると、保険契約者の意思で解約されてしまったり、保険料の支払方法を変更されて滞納してしまったりする可能性があります。
学資保険の名義を変更する手順
学資保険の名義変更をする際に必要な書類は、以下の通りです。
- 保険証券
- 新たに保険契約者になる人の身分証明書
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 保険契約者承継請求書
- 新契約者の口座振替依頼書
学資保険の名義変更の手順は、以下の通りです。
- 保険会社に問い合わせて、名義変更に必要な書類を送付してもらう
- 保険契約者承継請求書や口座振替依頼書に記入する
- 手続きに必要な戸籍謄本を取り寄せる
- 書類の準備が整ったら保険会社に提出する
名義変更する場合は保険料を支払えるか確認
学資保険の名義変更をする際は、まずは保険料の支払いを継続できる見込みがあるか確認しましょう。保険料の支払いが終わる前に保険を解約すると、それまでに支払った保険料よりも解約返戻金が少なくなる恐れがあります。
保険料の支払いが難しい場合は、当初設定していた保険金の金額を引き下げることで、支払う保険料を安くできます。ただし、保険商品によっては最低保険金額があるため、保険金の減額ができない可能性もあります。