フリーランスなどの個人事業者は、所得を確定させるために毎年2月16日から3月15日の間に確定申告をする必要があります。
個人事業者の場合は収入から経費を差し引いて所得を算出し、所得から所得控除を差し引くことで課税所得を算出します。さらに、課税所得に税率をかけることで所得税を算出することとなります。
税負担を抑えるためには経費と所得控除の範囲や要件を知り、効率的に控除を受けることが重要です。
この記事では、個人事業者が知っておくべき必要経費と所得控除・税額控除の範囲や内容について解説します。
※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
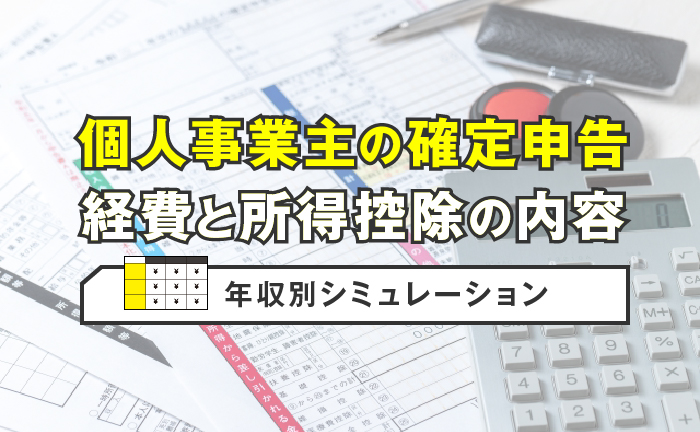
【記事執筆】税理士佐藤 憲亮

「お客様との対話を大事に」をモットーに、気軽に相談できる専門家として税務顧問業務をメインに活動。税務記事や税務論文の執筆もおこなっている、書くことが好きな税理士。税理士事務所で12年の実務経験を積み、2020年に税理士登録。
フリーランスなどの個人事業者は、所得を確定させるために毎年2月16日から3月15日の間に確定申告をする必要があります。
個人事業者の場合は収入から経費を差し引いて所得を算出し、所得から所得控除を差し引くことで課税所得を算出します。さらに、課税所得に税率をかけることで所得税を算出することとなります。
税負担を抑えるためには経費と所得控除の範囲や要件を知り、効率的に控除を受けることが重要です。
この記事では、個人事業者が知っておくべき必要経費と所得控除・税額控除の範囲や内容について解説します。
まず、「事業経費の範囲」「所得控除及び税額控除」の概要を解説します。
必要経費とは、「売上原価」「収入を得るためにかかった費用」「間接的にかかった販売費」「一般管理費」などのことです。具体例は以下の通りです。
必要経費の範囲は広いため、ざっくりと「事業収入を得るためにかかったものは経費だ」という認識で問題ないでしょう。
ただし、パソコンや車などの「10万円以上の固定資産」を購入した場合は、その年で全額経費にするのではなく、減価償却という方法で一定の年数にわたり経費とする必要があります。
また、住宅の一部を事務所や店舗として利用している場合、賃貸費用の一部を経費として計上することも可能です。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。「青色申告」を選択した場合、次の5つの特典を受けることができます。
(青色申告をするには、「税務署への青色申告承認申請書の提出」と「複式簿記による帳簿作成」が必要です。)
1.青色申告控除
最大65万円の控除を受けることができる
2.少額減価償却資産
30万円未満の固定資産であれば、年間合計300万円まで一括で経費処理することができる(通常、10万円以上の固定資産は減価償却によって経費にする)
3.繰越欠損金、繰戻しによる所得税の還付
赤字決算となった場合に、赤字を翌年以降3年間繰り越すことができる
本年が赤字で前年が黒字であった場合、前年に遡って所得税の還付を受けることができる
4.青色専従者給与
家族に対して支払った給与を経費にできる(原則、親族間で支払ったものは経費にならない)
5.貸倒引当金
売掛金等の回収できない可能性を見積もり、一定割合の金額を経費とすることができる
事業部分とプライベート部分の両方に関係する支出のことを家事関連費と言います。合理的な割合で按分することで、事業経費として計上することが可能です。
例えば、2LDKの賃貸住宅の一室を事務所としている場合、家賃を部屋の面積で按分することが考えられます。
また、事業のために自宅を利用している時間が、1日のうちの10時間であるとすれば、10時間÷24時間で利用割合を算出し、その割合で按分することも合理的な方法と言えるでしょう。
同様に、水道光熱費や通信費なども按分することができます。
ただし、必要以上に豪華な部屋を事務所として利用している場合や、通常では考えられないほどの高い光熱費などは、経費として認められないリスクが高いと言えます。
常識的な範囲において、合理的な方法で按分していることを説明できるようにしておきましょう。
経営セーフティ共済とは、取引先の倒産時に、無担保・無保証人で事業資金を借入できる共済で、個会社または個人事業者が加入することができます。
最大月20万円(年間240万円)まで払い込むことが可能で、払い込んだ金額はその年の経費となります。なお、払込後40ヵ月が経過してからの解約であれば、払い込んだ金額は全額返金されます。
ただし、返金された金額は収入に計上する必要があるため、赤字になっている年に解約するなどの工夫が必要です。
所得控除は全部で15種類あり、実際に支払った金額を基に控除額を計算する「物的控除」と、生活・扶養状況等により控除額を算出する「人的控除」があります。
内容と控除できる金額は以下の通りです。
| 種類 | 内容 | 控除金額 |
|---|---|---|
| 社会保険料控除 | 健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金など※同一生計の家族分を含む※別居で仕送りをしている場合も含む | 実際に支払った社会保険料の合計金額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払い時に所得控除を受けて積み立てることができ、事業を廃業する際に解約する場合は退職所得として受け取ることができる | 支払った掛金の合計金額(最大月7万円→年間最大84万円) |
| 生命保険料控除 | 生命保険、介護医療保険、個人年金保険 | 一定の方法により計算した金額(最大12万円) |
| 地震保険料控除 | 地震保険料、旧長期損害保険 | 一定の方法により計算した金額(最大5万円) |
| 寡婦ひとり親控除 | 配偶者と死別している場合、または離婚して扶養する子がいる場合 | 27万円(一定要件を満たす場合は35万円) |
| 勤労学生控除 | 学校等に通って働いている学生の場合(合計所得金額が75万円以下) | 27万円 |
| 障害者控除 | 本人が障害者、扶養親族が障害者の場合 | 特別障害:40万円(身体障害1・2級、精神障害1級)普通障害:27万円(特別障害者以外)同居特別障害者:75万円(特別障害者と同居) |
| 配偶者(特別)控除 | 配偶者のその年の所得が133万円未満の場合 | 38~1万円(納税者本人の所得と配偶者の所得により変動) |
| 扶養控除 | 同一生計の親族がいる場合 | 特定扶養:63万円(19歳~23歳未満)老人扶養:48万円(70歳~で非同居)同居老親等:58万円(70歳~で同居)一般扶養:38万円(16歳以上で上記以外) |
| 基礎控除 | 一定の所得以下の人に適用 | 合計所得金額2400万円以下:48万円合計所得金額2400万円超2450万円以下:32万円合計所得金額2450万円超2500万円以下:16万円 |
| 雑損控除 | 災害、盗難、横領で損害を受けた場合 | 下記のいずれかのうち多い金額・損害額-総所得金額等×10%・損失額のうち災害関連支出金の金額-5万円 |
| 医療費控除 | 治療費を一定額以上支払った場合 | (支払った治療費-保険金等の補填金額)-10万円※その年の総所得金額200万円未満の場合は、総所得金額等×5% |
| 寄付金控除 | 一定の寄付をした場合 | 下記のいずれかのうち少ない金額・寄付金合計額-2,000円・所得金額×40% |
所得控除は課税標準となる所得金額を減少させる効果がありますが、税額控除は所得税の負担を直接減少させる効果があります。ここでは、比較的活用しやすい税額控除を3種類解説します。
中小企業者(個人事業者を含む)が機械装置等の一定の設備を取得した場合において、取得価額の30%の特別償却、または7%の税額控除を受けることができる制度です。
特別償却は、通常耐用年数にわたって行う減価償却を早期に行うことで、初年度に経費を多くとることができます。
一方、税額控除は、通常の減価償却に上乗せして受けることができるため、トータルでは税額控除のほうが有利です。まずは税額控除を受けることを検討しましょう。
従業員に対する給与支給額が前年と比較して増額した場合に受けられる制度です。
毎年改正があるため徐々に適用範囲は広がってきており、従業員を雇用している場合は適用できるか確認する必要があるでしょう。適用要件は下記の通りです。
従業員に支給した給与(雇用調整助成金を控除した金額、親族への給与を除く)が前年と比較して1.5%以上増加した場合、増加した金額の15%を所得税から控除することができます。
従業員に支給した給与(雇用調整助成金を控除した金額、親族への給与を除く)が前年と比較して2.5%以上増加し、かつ次のいずれかを満たした場合、増加した金額の25%を所得税から控除することができます。
なお、いずれの場合においても所得税の20%が上限となります。
金融機関等で住宅ローンを組んで居住用住宅を取得した場合、ローンの年末残高に応じて一定の控除を受けることができます。
住宅ローン控除の内容は、令和4年の税制改正で大きく変更されています。

以上の解説を前提に、個人事業者のAさんが確定申告をする場合のシミュレーションをしてみましょう。
年収450万円、550万円、年収650万円の場合についてシミュレーションします。
| 区分 | 科目 | 金額(単位:千円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 収入 | 売上高 | 4,500 | 37万5000円/月 |
| 経費 | 資料費 | 60 | 5,000円/月 |
| 備品消耗品費 | 60 | 5,000円/月 | |
| 研修費 | 200 | スキルアップ 講習費 | |
| 通信費 | 72 | 6,000円/月 | |
| 水道光熱費 | 39 | 18万円/年×21.43% | |
| 地代家賃 | 386 | 180万円/年×21.43% | |
| 計 | 817 | ||
| 差引 | 3,683 | ||
| 青色申告控除 | 650 | ||
| 所得金額 | 3,033 | ||
| 所得控除 | 社会保険料控除 | 360 | 3万円/月 |
| 小規模企業共済 | 120 | 1万円/月 | |
| 生命保険料控除 | 120 | ||
| 地震保険料控除 | 0 | ||
| 寡婦・ひとり親控除 | 0 | ||
| 配偶者控除 | 0 | 配偶者扶養外 | |
| 扶養控除 | 0 | 未就学児のため適用なし | |
| 基礎控除 | 480 | ||
| 雑損控除 | 0 | ||
| 医療費控除 | 0 | ||
| 寄付金控除 | 0 | ||
| 計 | 1,080 | ||
| 差引課税所得 | 1,953 | 税率10% 控除額9万7500円 | |
| 所得税 | 137 | (課税所得×税率-控除額)×(1+復興特別所得税2.1%) | |
| 住民税 | 195 | おおよそ、所得×10% ここでは所得税の課税所得を基礎とします |
|
| 税額合計 | 332 | 所得税+住民税 | |
課税所得が「195万円~329万9000円」のため、税率は10%、控除額は9万7500円になります。所得税の税率と控除額は下表の通りです。

出典:国税庁「No.226 所得税の税率」
自宅兼事務所であるため、家賃と水道光熱費は事務室の平米数で按分しています。利用した時間等で按分する方法も考えられます。
また、青色申告控除65万円を受けるためには、以下のすべてを満たす必要があります。
| 区分 | 科目 | 金額(単位:千円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 収入 | 売上高 | 5,500 | |
| 経費 | 資料費 | 60 | 5,000円/月 |
| 備品消耗品費 | 60 | 5,000円/月 | |
| 研修費 | 200 | スキルアップ 講習費 | |
| 通信費 | 72 | 6,000円/月 | |
| 水道光熱費 | 39 | 18万円/年×21.43% | |
| 地代家賃 | 386 | 180万円/年×21.43% | |
| 計 | 817 | ||
| 差引 | 4,683 | ||
| 青色申告控除 | 650 | ||
| 所得金額 | 4,033 | ||
| 所得控除 | 社会保険料控除 | 360 | 3万円/月 |
| 小規模企業共済 | 120 | 1万円/月 | |
| 生命保険料控除 | 120 | ||
| 地震保険料控除 | 0 | ||
| 寡婦・ひとり親控除 | 0 | ||
| 配偶者控除 | 0 | 配偶者扶養外 | |
| 扶養控除 | 0 | 未就学児のため適用なし | |
| 基礎控除 | 480 | ||
| 雑損控除 | 0 | ||
| 医療費控除 | 0 | ||
| 寄付金控除 | 0 | ||
| 計 | 1,090 | ||
| 差引課税所得 | 2,943 | 税率10% 控除額9万7500円 | |
| 所得税 | 200 | (課税所得×税率-控除額)×(1+復興特別所得税2.1%) | |
| 住民税 | 294 | おおよそ、所得×10% ここでは所得税の課税所得を基礎とします |
|
| 税額合計 | 494 | 所得税+住民税 | |
年収550万円の場合でも、課税所得が「195万円~329万9000円」のため、税率は10%、控除額は9万7500円になります。
WEBライター・編集等のあまり経費がかからない業種は、売上が伸びた分の金額がそのまま利益となり、課税所得が増えやすいと言えます。経費の計上漏れがないかをしっかりとチェックをしましょう。
その上で大きく利益が出るのであれば、社会保険料控除や小規模企業共済控除等の所得控除を増やすことを検討します。
| 区分 | 科目 | 金額(単位:千円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 収入 | 売上高 | 6,500 | |
| 経費 | 資料費 | 60 | 5,000円/月 |
| 備品消耗品費 | 60 | 5,000円/月 | |
| 研修費 | 200 | スキルアップ 講習費 | |
| 通信費 | 72 | 6,000円/月 | |
| 水道光熱費 | 39 | 18万円/年×21.43% | |
| 地代家賃 | 386 | 180万円/年×21.43% | |
| 計 | 817 | ||
| 差引 | 5,683 | ||
| 青色申告控除 | 650 | ||
| 所得金額 | 5,033 | ||
| 所得控除 | 社会保険料控除 | 360 | 3万円/月 |
| 小規模企業共済 | 120 | 1万円/月 | |
| 生命保険料控除 | 120 | ||
| 地震保険料控除 | 0 | ||
| 寡婦・ひとり親控除 | 0 | ||
| 配偶者控除 | 0 | 配偶者扶養外 | |
| 扶養控除 | 0 | 未就学児のため適用なし | |
| 基礎控除 | 480 | ||
| 雑損控除 | 0 | ||
| 医療費控除 | 0 | ||
| 寄付金控除 | 0 | ||
| 計 | 1,090 | ||
| 差引課税所得 | 3,943 | 税率20% 控除額42万7500円 | |
| 所得税 | 368 | (課税所得×税率-控除額)×(1+復興特別所得税2.1%) | |
| 住民税 | 394 | おおよそ、所得×10% ここでは所得税の課税所得を基礎とします |
|
| 税額合計 | 762 | 所得税+住民税 | |
年収650万円の場合、課税所得が「330万円~694万9000円」のため、税率は20%、控除額は42万7500円になります。
こちらのパターンにおいても、まずは経費の計上漏れがないかしっかりとチェックしましょう。その上で所得控除を増やすことを検討します。
シミュレーションの通り、所得が増えると、税率が上がり支払う所得税額も高くなっていきます。さらに事業拡大していくのであれば、法人化をすることも一つの方法です。
法人税は税負担がおおよそ一定です。また経費の範囲や考え方も個人とは異なります。
法人化をすると給与の設定金額によっては社会保険の負担が大きく増加してしまうこともありますが、総合的に個人と法人のどちらのほうが最適なのかしっかり検討しましょう。

確定申告は一年間の事業に関するキャッシュの動きを集計して所得を確定させるものです。基本的にはその年の翌年以降に集計をすれば間に合います。
しかし、定期的に現状を把握しておくことで、効率的な節税対策を検討することができます。その際、利用できる選択肢を増やすために、税制について基本的なことを押さえておくようにしましょう。
キーワードで記事を検索