インボイス制度が2023年10月1日から始まります。
インボイス制度とは、売り手が買い手に対して、適用税率や消費税額などを記載した「適格請求書(=インボイス)」を発行する制度です。
インボイス制度の背景にあるのは、2019年10月に軽減税率が導入され、取引や商品によって税率が異なることです。どちらの税率(標準税率10%、軽減税率8%)が適用されるかを明確にすることで、経理処理の正確性を上げることが狙いです。
この記事では、フリーランスや副業者がおさえておきたい、インボイス制度のポイントについて解説します。
フリーランスが知っておくべき「インボイス制度」制度概要と負担軽減措置(2割特例)クラウドソーシングの対応も
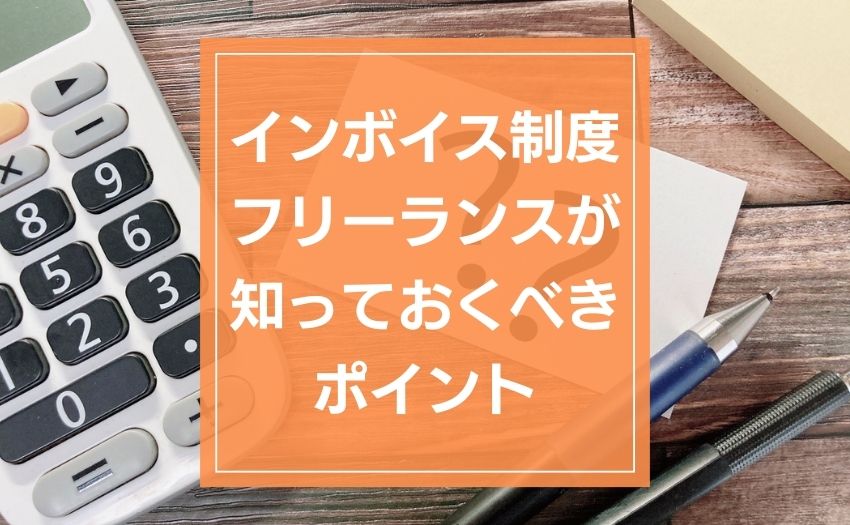
マネーFix 編集部

マネーFix 編集部は、FP有資格者や「ビジネス書」や「学習参考書」などさまざまなジャンルの編集経験者で構成されています。わかりやすく確かな情報を発信し「人生におけるお金の決断」の判断基準となる、信頼できるメディアを目指します。
インボイス制度の概要
フリーランスや副業者がおさえておきたい、インボイス制度のポイントは以下の通りです。
- インボイス制度は、クライアント(買い手)に正確な適用税率や消費税額率を伝えるために、フリーランス(売り手)などがインボイスを交付する制度である。
- インボイスを交付するためにはインボイス発行事業者にならなければならない。
- インボイス発行事業者になると、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」に登録番号、氏名(または名称)、登録年月日などが公表される。
- インボイスの登録は任意である。
インボイス制度は、簡単に言うと「消費税に関するルールの変更」です。
一般的に、事業者が取引先にサービスや品物を提供した場合、消費税を含めた報酬を受け取ります。
受け取った消費税は納税する義務がありますが、売上高が1000万円以下であれば、消費税を納める必要のない免税事業者となります。
- 課税事業者:課税売上高が1000万円を超える事業者
- 免税事業者:課税売上高が1000万円以下の事業者
出典:国税庁 「消費税のしくみ」
100万円の報酬を受け取った場合で考えてみましょう。
軽減税率以外の消費税率が10%なので、実際に受け取る金額は、以下の通りです。
- 消費税:100万円×10%=10万円
- 受け取り総額:100万円+10万円=110万円
免税事業者の場合は、10万円の消費税は納税する必要がありません。
では、インボイス制度の導入によって、消費税におけるルールがどのように変わるのでしょうか。
仕入税額控除の観点から解説します。
仕入れ税額控除とは、売上にかかる消費税から経費にかかる消費税を差し引く制度です。
2023年10月から、仕入れ税額控除を受けるために、「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書(インボイス)」が必要になります。
「適格請求書発行事業者」の登録は、課税事業者のみが対象となります。
そのため、買い手側は、免税事業者が発行した請求書では、仕入税額控除を受けることができなくなります。
買い手側が、インボイスを発行できない免税事業者との取引を中止する可能性も考えられるため、個人・法人を問わず、「適格請求書発行事業者」になることが求められています。
現時点で免税事業者の人が「適格請求書発行事業者」になるということは、課税事業者になるということなので、消費税を国に納める必要があります。
負担軽減措置としての2割特例
インボイス発行事業者に登録して課税事業者になった場合、受け取った消費税に対して、納付額を「8割」軽減する「2割特例」が受けられます。
100万円の報酬を例にすると、以下の通りになります。
- 消費税:100万円×10%=10万円
- 納税額:10万円×20%=2万円
インボイス発行事業者に登録して課税事業者になった場合、2割特例があるかないかで、消費税の納付額がどの程度変わるのでしょうか。
- 売上330万円(うち消費税30万円)
- 外注費50万円(うち消費税5万円)
消費税の納付額は受け取った消費税から、外注等で支払った消費税を、差し引いて計算します。
- 消費税の納付額(負担軽減策なし):30万円-5万円=25万円
- 消費税の納付額(負担軽減策あり):25万円×20%=5万円
2割特例によって、消費税の納付額に20万円の差が生じました。
ただし、この2割特例が適用される期間は、インボイス制度を開始してから3年間(2023年10月1日~2026年9月30日)です。
なお、2割特例は売上高が1000万円以下の場合のみ受けることができます。
国税庁の「インボイス制度特設サイト」には、制度の説明や相談用フリーダイヤルが設けられています。
また、各地域で開催される説明会の案内も掲載しています。参考にしてください。
クラウドワークスやランサーズのインボイス制度施行後の対応
フリーランスの場合、クラウドワークスやランサーズなどのクラウドソーシングを利用している人も多いでしょう。
ここでは、クラウドソーシングのインボイス制度施行後の対応について解説します。
消費税請求について
クラウドワークスやランサーズでは、インボイス制度開始後も、クライアント(発注者)への消費税請求はこれまで通り行われます。
クライアントは「クラウドワーカーがインボイス発行事業者でない場合、消費税を支払わない」といった対応はできなくなっています。
クラウドワーカー(受注者)がインボイス発行事業者であるかないかに関わらず、消費税請求は行われるため、報酬金額が変わることはありません。
媒介者交付特例について
媒介者交付特例とは、クラウドソーシング事業者が、クラウドワーカーの代わりにインボイスを発行できる制度です。
クラウドソーシングの場合、本名を明かさずに仕事のやりとりをしているケースが多いですが、インボイスを発行すると、クライアントに本名が判明してしまいます。
しかし、クラウドソーシングでは、媒介者交付特例によって、クラウドソーシング事業者が代理でインボイスを発行します。
そのため、クラウドワーカーがクライアントに直接インボイスを発行する必要はありません。
ただし、クラウドソーシング事業者がインボイスを代理発行するには以下の条件が必要です。
- インボイス登録事業者であること
- 自身の登録番号をクラウドソーシングに登録しておくこと
各クラウドソーシングでは、インボイス発行事業者の登録番号を登録することができるようになっています。
10月1日以降、クラウドソーシングにおいてインボイスを発行したい場合は、利用しているクラウドソーシングにインボイス発行事業者の登録番号を登録しておくようにしましょう。
なお、フリーランスが知っておくべきインボイス制度に関しては、こちらの記事でも詳しく解説されています。合わせて確認してみてください。
- 国税庁「消費税のしくみ」