水は生活に欠かせないものですが、家計負担を減らすためにも節水できるに越したことはありません。「節水したいけど方法がわからない」「そもそもうちは使いすぎなの?」という人もいるでしょう。
節水を心がけるためにも、まずは水道を使いすぎていないか確認する必要があります。
この記事では、水道代の計算の仕組みや平均額について解説します。
- 水道代の計算の仕組み
- 世帯人数別・月別・地域別の水道代の平均額
※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
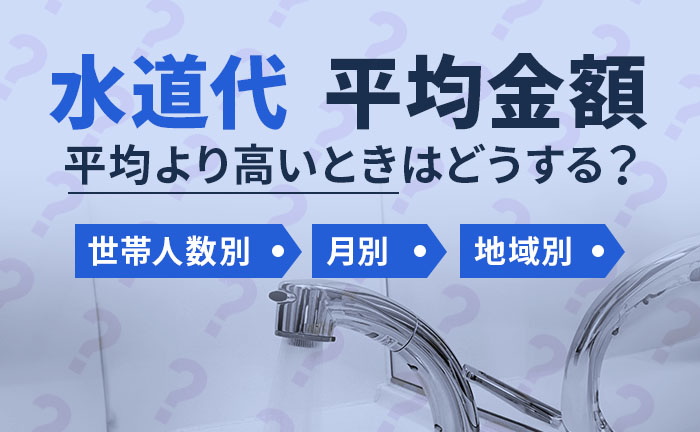
【監修】株式会社RKコンサルティング河合 克浩

一般企業、外資系金融機関を経て、現在はファイナンシャルプランナー(FP)として年間150件超のお金の相談に対応。難しく感じる経済やお金の話をわかりやすく説明することに定評がある。夢を実現するため相談者に寄り添い、人生が豊かになるサポートを心がけている。
水は生活に欠かせないものですが、家計負担を減らすためにも節水できるに越したことはありません。「節水したいけど方法がわからない」「そもそもうちは使いすぎなの?」という人もいるでしょう。
節水を心がけるためにも、まずは水道を使いすぎていないか確認する必要があります。
この記事では、水道代の計算の仕組みや平均額について解説します。

水道代の内訳は、以下の通りです。
水道料金はメーター口径と使用水量に基づいて計算します。例えば、メーター口径が20mm、2ヵ月分の使用水量が50立方メートルだったとしましょう。この場合、1ヵ月あたり25立方メートルとして計算します。
| 項目 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 基本料金(口径20mm) | 979円 | |
| 従量料金 | 3,619円 | 10立方メートル×62.7円=627円 10立方メートル×165円=1650円 5立方メートル×268.4円=1342円 |
| 小計 | 4598円 | |
| 10円未満の端数切り捨て | ▲8円 | |
| 合計 | 4,590円 |
水道料金は、2ヵ月に1回請求されます。2ヵ月分の水道代は4,590円×2ヵ月=9,180円です。

世帯人数によっても、水道代の平均額は異なります。家計調査の結果をもとに世帯人数ごとの平均額を紹介します。
月々の平均水道料金 「2022年総務省の家計調査」によると、世帯人数ごとの月々の平均水道料金は、単身世帯が2,248円、2人世帯で4,344円、3人世帯で5,749円、4人世帯で6,465円となっています。
人数が多くなればなるほど、水道代の平均額も高くなります。6人以上になると1万円を超えることも珍しくありません。
2ヵ月分の水道代の平均は以下のとおりです。
| 世帯人数 | 水道代(2ヵ月分) |
|---|---|
| 一人暮らし | 4,496円 |
| 2人家族 | 8,688円 |
| 3人家族 | 11,498円 |
| 4人家族 | 12,930円 |
| 5人家族 | 14,614円 |
| 6人家族以上 | 18,380円 |

下表は、2人以上の世帯の月別水道代の平均額をまとめたものです。
| 月別 | 水道代平均 |
|---|---|
| 1~2月 | 10,876円 |
| 3~4月 | 10,258円 |
| 5~6月 | 10,662円 |
| 7~8月 | 10,444円 |
| 9~10月 | 10,255円 |
| 11~12月 | 9,991円 |
1年を通じて大きな差はありませんが、1~3月の冬の期間がやや高めです。
世帯人数によっても、平均額は異なります。下表は季節ごとの水道代(1ヵ月分)を世帯人数別にまとめたものです。
| 世帯人数 | 春 (4~6月) |
夏 (7~9月) |
秋 (10~12月) |
冬 (1~3月) |
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2,106円 | 2,101円 | 2,156円 | 2,163円 |
| 2人 | 4,234円 | 4,304円 | 4,028円 | 4,258円 |
| 3人 | 5,495円 | 5,498円 | 5,312円 | 5,433円 |
| 4人 | 6,320円 | 5,972円 | 6,256円 | 6,260円 |
| 5人 | 6,982円 | 7,129円 | 6,899円 | 7,377円 |
| 6人以上 | 9,468円 | 8,695円 | 8,328円 | 9,998円 |
一人暮らしの場合、季節による大きな差はありません。しかし、4人以上など世帯人数が大きい家庭の場合、夏より冬の方が多く水を使う傾向にあります。

地域によっても、2ヵ月の水道代の平均額は異なります。ここでは、地域別に2ヵ月あたりの水道代の平均を紹介します。
| 地域 | 水道代 |
|---|---|
| 北海道 | 8,116円 |
| 東北 | 10,312円 |
| 関東 | 8,100円 |
| 北陸 | 9,514円 |
| 東海 | 8,016円 |
| 近畿 | 7,850円 |
| 中国 | 8,206円 |
| 四国 | 7,148円 |
| 九州 | 7,716円 |
| 沖縄 | 7,114円 |
水道料金は、自治体の水道運営にかかるコストを考慮して決められます。水源からの近さ、地域の水質、人口などが影響するため、地域によって差が大きくなっています。
例えば、最も高い東北地方では、集落がかなり離れて存在していることも多く、各家庭まで水を届けるコストも高くなります。
一方、関東地方や東海地方、近畿地方は人口密度が高く、効率的に水を家庭に届けられることからコストも安い傾向です。
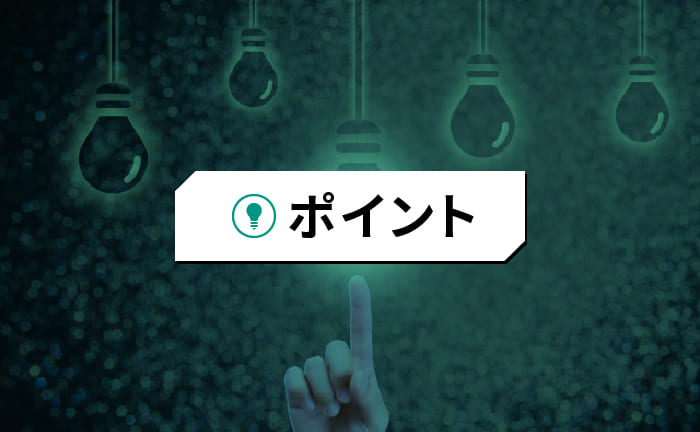
自宅の水道代が平均額より高い場合は、以下のポイントを確認しましょう。
水の使い方に特に問題がないにもかかわらず、高額な水道料金を請求されている場合、水道管の水漏れが原因の可能性があります。特に、ある月を境に明確に水道料金が上がった場合、水漏れを疑ってみましょう。
以下を行い、水道管の水漏れの有無を確認してください。
さらに正確な原因を追究するためには、水道業者を呼んで調べてもらいましょう。
なお、水漏れが原因で水道代が上がっていたとしても、本来は使用者が料金を払います。ただし、自治体によっては条件次第で減額請求できる可能性もあるため、管轄の水道局に問い合わせてみてください。
水道代が高いと感じたら、節約を考えてみましょう。水道代の節約方法は多岐にわたります。代表的な節約方法は、以下の通りです。
ほかにも色々な方法があるので、『水道代を節約する方法』も参考にしてみてください。

水道代は世帯人数や季節、地域によっても異なります。一概に「いくらなら大丈夫」とはいえないですが、平均よりあまりに高い場合は、使いすぎもしくは水漏れを疑い、対策を講じましょう。
使いすぎていた場合でも、生活スタイルを見直すことで節約できる余地は十分にあります。ただし、やりすぎは禁物なので、生活に支障をきたさない程度に続けられる方法を取り入れてみてください。
キーワードで記事を検索