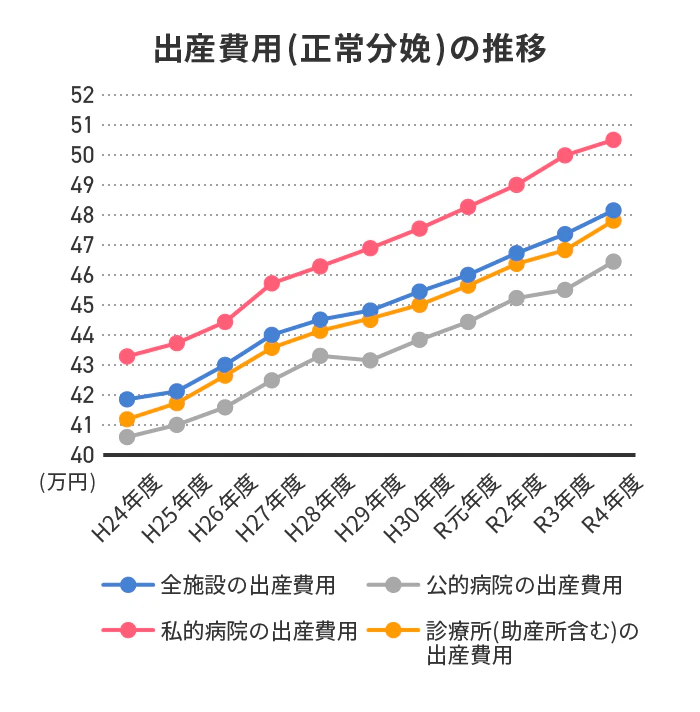妊娠・出産にかかる費用は自己負担となりますが、国や自治体で提供している助成金を活用することで自己負担額を軽減できます。
出産費用の負担軽減に利用できる制度は、以下の通りです。
- 妊婦健診の助成制度
- 出産一時金
- 出産手当金
- 出産日貸付制度
- 生活福祉資金
- 高額療養制度
- 医療費控除
- 育児休業給付金
- 社会保険料の免除
妊婦健診の助成制度
妊婦健診の費用は自己負担で対応するのが原則ですが、自治体による助成制度も利用できます。
自治体によって助成回数や補助額が異なりますが、どの自治体でも妊婦健診を最低14回は受けられるよう設定されています。
妊婦健診の助成制度
- 助成・補助内容(金額):妊婦検診の費用(最低14回分)
- 対象者の条件:各自治体に在住する妊婦
- 申請のタイミング:妊娠が判明してから次の健診前まで
- 申請の方法:役所へ妊娠届を提出する
出産育児一時金
出産育児一時金とは、子どもを出産したときに加入している健康保険制度から受け取れる一時金です。妊娠週数が22週以上で出産した場合、正常分娩・異常分娩ともに50万円が健康保険から支給されます。1児につき50万円なので、双子の場合は100万円です。
出産育児一時金の受け取り方法は、「直接支払制度」「受取代理制度」「事後申請」の3つです。
「直接支払制度」「受取代理制度」を選択した場合は、入院・分娩費用の支払いは出産育児一時金と相殺した部分のみを支払うことになります。「事後申請」では出産費用を本人が先に全額立て替え、後日、健康保険組合に請求します。
出産育児一時金
- 助成・補助内容(金額):1児あたり50万円(一定要件以下の場合は8万円)
- 対象者の条件:妊娠4ヵ月以上で出産した健康保険の被保険者および被扶養者
- 申請のタイミング:「直接支払制度」は入院時から、「受取代理制度」は出産2カ月前から、「事後申請」は出産翌日から提出可能
- 申請の方法:医療機関または加入している健康保険に申請
出産育児一時金については、『出産育児一時金とは?もらえる金額や条件をわかりやすく解説』も参考にしてください。
出産手当金
出産手当金とは、出産によって会社を休み、給与の支払いが行われなかった期間を対象として支給される手当です。対象期間は出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲内で支給されます。出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても支給の対象です。
ただし、対象期間であっても給与が支払われている場合、支給額の減少や、支給停止となる場合があります。また、この制度は国民健康保険の加入者は対象外になる点にも注意が必要です。
出産手当金の計算式は以下の通りです。
1日あたりの出産手当金=直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30日×2/3
「標準報酬月額平均額」とは、過去12ヵ月間の月々の給与などの報酬平均を示す額です。具体的には、最初の支給日の前の12ヵ月間における各月の「標準報酬月額」を足し合わせ、12で割った平均額を指します。
出産手当金
- 助成・補助内容(金額):過去12ヵ月間における標準報酬月額平均額の2/3を日額として支給
- 対象者の条件:健康保険組合に加入している被保険者で妊娠4ヵ月以降に出産する人
- 申請のタイミング:出産後56日経過後が一般的
- 申請の方法:加入している健康保険組合へ申請書を郵送する
出産手当金については、『出産手当金とは?支給条件・支給額や申請方法』も参考にしてください。
出産費貸付制度
出産費貸付制度は、出産育児一時金が支給されるまでの期間、無利子で貸付を行う制度です。
医療機関などの事情で出産育児一時金の「直接支払制度」が利用できず、「事後申請」を選択しなければならない場合があります。その際、出産費用を先に立て替える必要がありますが、そうすると経済的に支払いが困難になる人も出てくるかもしれません。
このような場合に、一定の条件を満たせば、出産育児一時金が支給されるまでの間、出産育児一時金見込額の8割相当を無利子で融資してもらうことが可能です。その後、出産育児一時金が支給された際に精算し、融資された金額を返済します。
出産日貸付制度
- 助成・補助内容(金額):出産育児一時金見込額の8割相当を無利子で融資
- 対象者の条件:全国健康保険協会または、国民健康保険に加入の被保険者、および被扶養者
- 申請のタイミング:出産予定日の1ヵ月前から
- 申請の方法:出産費貸付金貸付申込書を加入している健康保険組合へ提出
生活福祉資金
生活福祉資金貸付は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的な部分から支援するための貸付制度です。都道府県社会福祉協議会を実施主体とし、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。
この貸付は出産も対象で、50万円を上限に借入可能です。返済期間は3年以内、利息は年1.5%(連帯保証人を付ける場合は無利子)で融資が可能なため、消費者金融で借入するよりも利息負担が抑えられるでしょう。
生活福祉資金
- 助成・補助内容(金額):福祉資金として最大50万円までの貸付
- 対象者の条件:低所得者や高齢者、障害者
- 申請のタイミング:経済的な支援が必要なとき
- 申請の方法:最寄りの社会福祉協議会に直接申し込む
高額療養制度
高額療養費制度とは、病院や薬局の窓口で支払った費用が、1ヵ月(月の初めから終わりまで)で自己負担の上限額を超えた場合に、超えた部分が戻ってくる制度です。
出産に関しては、通常分娩の場合は保険適用外となるため、高額療養費制度の対象にはなりませんが、帝王切開のような異常分娩では保険適用が認められています。ただし、個室を選択した場合のベッドや室料の差額分などは対象外です。
高額療養制度
- 助成・補助内容(金額):1ヵ月の自己負担の上限額を超えた医療費を後日返金
- 対象者の条件:健康保険に加入していて、1ヵ月の医療費が自己負担の上限額を超えた場合
- 申請のタイミング:自己負担の上限額を超えた次の月から申請可能。「限度額適用認定証」を提示する方法であれば事前申請も可能
- 申請の方法:勤務先の会社経由(または直接)で健康保険組合に提出
医療費控除
医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた際に所得控除を受けられる制度です。医療費控除が適用された場合、確定申告をすることで払い過ぎた税金が還付されることがあります。
加入している健康保険や分娩方法に関係なく利用でき、健診や通院費用、入院中の食事代なども対象です。ただし、支払った医療費を計算する際には、出産育児一時金などで受け取った金額を相殺して計算します。
医療費控除
- 助成・補助内容(金額):1年間の医療費が一定額を超えた場合に所得控除が適用
- 対象者の条件:1年間に支払った医療費が一定額を超えた人。ただし、受け取った出産育児一時金などは相殺して計算
- 申請のタイミング:原則、所得税の確定申告期間中(翌年2月16日?3月15日)
- 申請の方法:確定申告
出産費用の医療費控除については、『出産費用の医療費控除で節税に!控除額と還付金の計算や確定申告の方法』も参考にしてください。