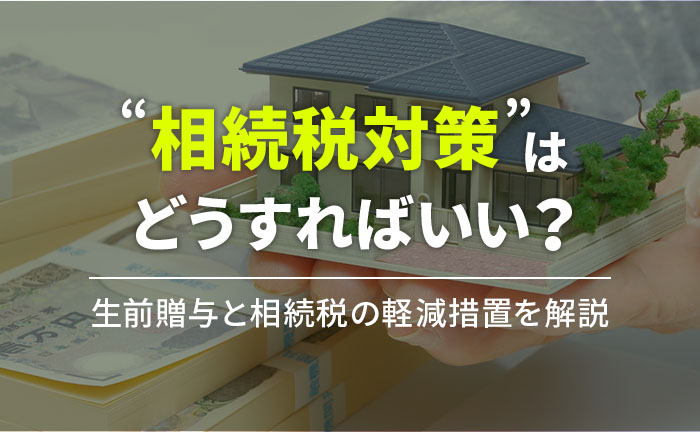生前贈与をする際、「暦年課税税度」か「相続時精算課税制度」を利用して贈与をすることになります。それぞれの課税制度の内容について説明します。
暦年課税制度
暦年課税制度を使うと、110万円以内の贈与であれば無税で財産を渡すことができます。そのため、相続対策として、まずは毎年110万円の範囲内で財産を贈与していくことを検討します。
ただし、贈与された財産については「生前贈与加算」という制度が適用され、相続開始前3年間(※)に贈与された財産は、相続時の財産に加算する必要があります。そのため、相続直前に贈与されたとしても、その財産は相続税の対象となります。(※令和5年の税制改正において、生前贈与加算の期間を7年にすることが検討されています)
なお、生前贈与加算が適用されるのは、「相続により財産を取得した人のみ」であり、相続放棄した人や遺産分割協議により財産を取得しなかった人には、適用されません。(非課税財産、みなし相続財産を取得した場合は当該規定が適用されます)
相続時精算課税制度
110万円を超えた財産を一括で子や孫に贈与する場合は、「相続時精算課税制度」の適用を受ければ、2500万円までは贈与税がかかりません。
相続時精算課税制度を活用するメリットは、不動産や株などで将来値上がりする可能性があるものを生前贈与することで、値上がり益に対して相続税が課税されないことにあります。
なお、不動産収入が生じている不動産(建物)がある場合は、生前贈与しておくことで、相続税を回避することにもつながります。
一方、相続時精算課税制度のデメリットは、当該制度の適用を受けると110万円までの贈与に適用される基礎控除(暦年課税制度)が使えなくなる点です。(なお、令和5年の税制改正において、相続時精算課税制度を適用した場合、毎年110万円の基礎控除の枠を設けることが検討されています)
また、合計2500万円以上の贈与があった場合、2500万円を超えた部分の金額に対しては、一律20%の贈与税が課されます。
また、小規模宅地等の特例などの税負担軽減措置が適用できません。これについては次で詳しく解説します。