生涯賃貸住宅で暮らすのと、自宅を購入するのでは最終的にどちらがお得なのでしょうか。持ち家にも賃貸にもそれぞれメリット・デメリットがあり、その人の置かれている状況にもよるため、一概にどちらがよいか判断するのは難しいです。
この記事では、持ち家と賃貸の特徴を紹介し、生涯コストを比較します。それぞれに向いている人も解説するので、参考にしてください。
※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
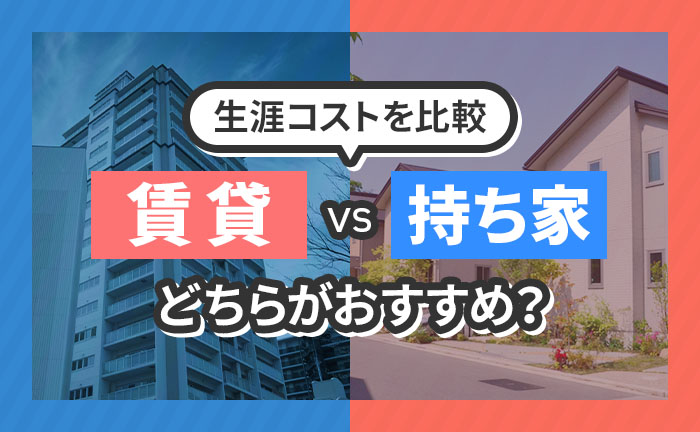
【監修】株式会社RKコンサルティング河合 克浩

一般企業、外資系金融機関を経て、現在はファイナンシャルプランナー(FP)として年間150件超のお金の相談に対応。難しく感じる経済やお金の話をわかりやすく説明することに定評がある。夢を実現するため相談者に寄り添い、人生が豊かになるサポートを心がけている。
生涯賃貸住宅で暮らすのと、自宅を購入するのでは最終的にどちらがお得なのでしょうか。持ち家にも賃貸にもそれぞれメリット・デメリットがあり、その人の置かれている状況にもよるため、一概にどちらがよいか判断するのは難しいです。
この記事では、持ち家と賃貸の特徴を紹介し、生涯コストを比較します。それぞれに向いている人も解説するので、参考にしてください。

持ち家と賃貸のメリット・デメリットは、下表の通りです。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 持ち家 | ・完済後の支払い負担がない ・資産になる ・リフォームができる |
・引っ越ししにくい ・定期的なメンテナンスが必要 ・固定資産税がかかる |
| 賃貸 | ・引っ越ししやすい ・固定資産税が不要 ・年収に合わせて住居費を変えやすい |
・管理費や更新料がかかる ・内装を変えられない ・高齢時に契約更新できない物件もある |
持ち家の場合、多くの人は住宅ローンを組んで購入します。完済までは家賃の支払いと同様に、毎月ローンを返済することになりますが、完済してしまえば月々の負担はなくなります。
また、不動産は資産なので、自宅を担保に融資を受けるなど、資金調達の方法として活用できます。
さらに、そのときどきの生活状況に応じてリフォームできる点もメリットです。
家を購入すると、気軽に引っ越しができなくなります。転勤が多い仕事をしている人などは、この点を考慮した方がよいでしょう。
持ち家の大きなデメリットは、固定資産税がかかることです。固定資産税は土地と建物両方に課せられます。建物の資産価値は経年で下がりますが、土地の評価額は上下する場合があります。固定資産税は、家や土地を所有している限り、毎年課税されます。
戸建てでもマンションでも、経年劣化によって建物の修理が必要になります。屋根や外壁、ベランダなど屋外部分はもちろん、室内の設備も定期的な修理や交換が必要なので、修繕計画を立てて、必要な費用を準備しておかなければなりません。
賃貸に住むメリットは、引っ越ししやすいことです。家族の増減や仕事の都合に合わせて住む場所や間取りを選べるので、ライフススタイルの変化にも柔軟に対応できるでしょう。
また、賃貸の場合、持ち家のような固定資産税の負担がありません。さらに、そのときの収入状況に見合った部屋に住み替えられる点もメリットです。
生涯賃貸で暮らす場合、ずっと賃料を払い続けなければなりません。リタイアして収入が年金だけになると負担に感じられるケースもあります。
また、賃貸契約を結ぶ際には2年ごとの更新を設けているケースがほとんどです。そのため、更新時期には更新料が発生します。
内装を自由に変えられないこともデメリットです。室内をリフォームしようと思ってもオーナーの許可が必要で、大がかりなリフォームはなかなか認めてもらえません。
さらに、高齢になると、契約が更新されないリスクもあります。そうすると住む場所がなくなってしまい、新たに探す必要が出てきますが、高齢であることを理由に断られるケースがあります。

30~90歳までの60年間を、持ち家もしくは賃貸で暮らすと想定した場合のコストを比較して紹介します。
まず、持ち家の場合の生涯コストをシミュレーションしてみましょう。4000万円の住宅を頭金なし、ボーナス払いなしの35年ローンで購入したケースを例に紹介します。
| 初期費用 | 200万円(物件の5%) |
|---|---|
| 住宅ローン | 5394万3120円(金利1.8%) |
| 住宅ローン諸費用 | 約88万円 |
| 修繕費用 | 700万円(1回350万円×2回程度) |
| 固定資産税 | 720万円(延べ床70㎡、1年あたり12万円) |
| 火災保険 | 180万円(1年あたり3万円) |
| 生涯コストの概算 | 約7282万円 |
4000万円の住宅を購入する場合、購入時の初期費用に200万円かかります。さらに、住宅ローンを組むための費用が別途約88万円かかります。
金利1.8%で35年ローンを組んだ場合、毎月の返済額は12万8436円で、35年間の返済総額は約5394万3120円です。
また、1回あたり350万円の修繕費用が60年間で2回必要になると仮定すると、必要な修繕費用は700万円です。年間12万円の固定資産税が60年間かかり、これが総額720万円になります。
そのほか、火災保険料などを加えると、持ち家にかかる生涯コストは約7282万円になることがわかります。
ローン完済後は、年間3万円の火災保険料と、12万円の固定資産税だけで住み続けられます。
次に、賃貸にかかる生涯コストをシミュレーションしてみましょう。持ち家と比較しやすいよう、家賃を毎月のローン返済額と同程度の12万8000円で計算します(管理費は込みとする)。
| 火災保険 | 60万円(1年あたり1万円) |
|---|---|
| 初期費用 | 25万6000円(敷金・礼金1ヵ月ずつ) |
| 契約更新費用 | 12万8000×30=384万円(2年ごとなので30回支払う) |
| 家賃 | 12万8000×720=9216万円(60年×12ヵ月=720ヵ月) |
| 生涯コストの概算 | 約9686万円 |
このケースでは、賃貸の生涯コストは約9686万円となりました。持ち家の生涯コストを比較すると、賃貸の方が約2400万円多くかかることがわかります。仮に、持ち家の生涯コストと同程度にしようと考えた場合、家賃を約9万6000円に抑えなければなりません。
家賃は住んでいる間ずっと発生するため、長生きするほど生涯コストは高くなります。同じ家に住み続けようと思うなら、1年あたり154万円程度支払わなければなりません。
生涯賃貸で暮らすためには、ライフスタイルに合わせて引っ越しをして、賃料をコントロールするなどの対策が必要です。

ここまでの内容を踏まえたうえで、持ち家が向いている人と賃貸が向いている人の特徴を解説します。
持ち家が向いている人の特徴は、以下の通りです。
収入が安定していると、住宅ローンの審査に通りやすくなります。逆に、収入が不安定な場合は住宅ローンの審査に通りにくく、通ったとしても希望通りの額が借入できるとは限りません。
また、収入が減少したときに住宅ローンの返済が負担となり、場合によっては購入した住宅を手放さなければならなくなるケースもあります。
収入が安定しており、住宅ローンを利用できる条件がそろっているなら、生涯コストを少なくできる持ち家を選ぶのがおすすめです。
大家族だと必要な部屋数もそれだけ多くなりますが、賃貸で4LDK以上の物件はなかなか見つかりません。あったとしても、家賃が高額なケースが多いでしょう。
持ち家で戸建てを選べば部屋数も多くできます。子どもが独立したあとはリフォームを行い、部屋数を変えることも可能です。条件に見合う賃貸物件がなかなか見つからない人は、家の購入を考えてみてもよいでしょう。
住宅ローンを組み、退職までに完済できれば、住居費の負担を抑えられ、退職金や年金を老後の生活資金に充てられます。逆に、退職までに完済できないと、老後の生活をするうえで返済が大きな負担になる可能性があります。
持ち家は完済したあとは毎月の返済を考える必要がなく、火災保険料と固定資産税のほか、あとは定期的なメンテナンス費用だけで済みます。
また、老後に必要な資金が不足しそうになった場合には、持ち家を担保にお金を借りることも可能です。
賃貸だと毎月の家賃の支払いが続くため、老後の収入が年金のみになったときは負担が重く感じられます。老後に住居の心配をすることなく暮らしたいなら、持ち家を選ぶことをおすすめします。
賃貸が向いている人の特徴は、以下の通りです。
転勤が多い仕事にもかかわらず住宅を購入すると、転勤の際には単身赴任、もしくはマイホームを第三者に貸し出す選択を迫られます。単身赴任先でも住居費がかかるので、住宅ローンの返済が負担になることもあり得ます。
第三者に貸し出す場合は、住宅ローンではなく不動産投資ローンへ切り替えなければなりません。住宅ローンは、あくまでも自分が住むための住居を購入するために必要な資金を融資してくれるローンです。
転勤が多いのなら、住宅を購入するより賃貸を選ぶ方がよいでしょう。
収入が安定していない場合、住宅ローンの審査に通らない可能性があります。無事にローンが組めてもその後の返済が負担になる事態は避けたいところです。
収入が安定していない場合は、そのときの収入レベルに応じて住み替えられる賃貸を選ぶことをおすすめします。
ただし、老後の住居費の負担も考慮し、早いうちから老後資金の形成に取りかかることも大切です。毎月の生活費の中から少しでも預貯金に回すなど、老後の生活を考えながら資産形成を行いましょう。

持ち家と賃貸を比較すると、持ち家の方が生涯コストは低いことを解説しました。しかし、ローン返済額と家賃が必ずしも同じレベルになるとは限りません。人によっては賃貸でも、持ち家と同程度のコストに抑えられる可能性もあります。
持ち家と賃貸、どちらを選ぶかはその人の収入や仕事の内容、家族構成などで異なります。それぞれのメリット・デメリットをしっかりと把握し、自分のライフスタイルに合った方を選びましょう。
一戸建てとマンション・賃貸の維持費の種類や特徴については下記の記事で詳しく解説されています。併せてご確認ください。
参考:マンションと戸建て・賃貸の維持費を徹底比較!維持費の種類と、特徴や注意点について解説| 不動産とくらしの評判
キーワードで記事を検索