人生の中では、しばしば大きな資金が必要になることがあります。「家を買いたいけれど頭金が用意できない」「子どもの教育資金が足りるか心配」「老後に備えて貯蓄したいが手が回らない」という悩みはありませんか?
住宅購入資金、教育資金、老後資金は「人生の三大資金」と呼ばれています。
この記事では、人生の三大資金の費用相場や、おすすめの準備方法を解説します。
- 住宅購入資金の相場
- 教育資金の相場
- 老後資金の相場
- 人生の三大資金を準備する方法
※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

【監修】株式会社RKコンサルティング河合 克浩

一般企業、外資系金融機関を経て、現在はファイナンシャルプランナー(FP)として年間150件超のお金の相談に対応。難しく感じる経済やお金の話をわかりやすく説明することに定評がある。夢を実現するため相談者に寄り添い、人生が豊かになるサポートを心がけている。
人生の中では、しばしば大きな資金が必要になることがあります。「家を買いたいけれど頭金が用意できない」「子どもの教育資金が足りるか心配」「老後に備えて貯蓄したいが手が回らない」という悩みはありませんか?
住宅購入資金、教育資金、老後資金は「人生の三大資金」と呼ばれています。
この記事では、人生の三大資金の費用相場や、おすすめの準備方法を解説します。

人生の三大資金は、次の3つです。
子どもの教育・住宅の購入・老後の生活費などの支出は人生における三大支出です。
住宅の購入費用は、新築か中古かにもよりますが、3000万~5000万円台が平均です。また、住宅を購入すると、固定資産税や、維持管理費などのランニングコストも生じてきます。
住宅を購入せず、賃貸住宅で生活する選択肢もあります。その場合は家賃を支払っていくことになり、長期的に見ると賃貸料の合計の方が高額になる可能性もあります。
どちらを選択するかはライフスタイルや資金計画などによって異なるため、十分に比較検討する必要があるでしょう。
教育資金は、入学金、授業料、習い事に要する費用などが含まれます。教育資金の金額は、子ども1人あたり1000万~2000万円が一般的です。
教育資金は子どもの進学先が公立なのか、私立なのかによっても異なります。進学直前などに用意するのは大変なので、子どもが生まれた段階から計画を立てていくことが重要です。
老後資金とは、退職後の生活費や医療費、介護費用などを賄うために必要となる資金です。現役を引退し、年金生活になったあとも、安定した生活を維持するためには一定の蓄えが必要になるでしょう。
「老後資金は2000万円必要」といわれますが、老後にどのような生活を送りたいかで、必要な金額は異なってきます。そのため、現役時代からどれくらいの資金を準備すべきかをきちんと把握し、計画的に準備していくことが重要です。

住宅の購入費用には、物件価格に加えて仲介手数料やローン手数料、登記費用なども含まれます。また、購入後は固定資産税や、維持管理費などのランニングコストの支払いも発生してきます。
ここでは、住宅購入資金について解説します。
国土交通省「令和4年度住宅市場動向調査」によると、新築マンションの平均購入費は5279万円、注文住宅は5436万円、中古戸建は3340万円です。
| 住宅の種類 | 購入資金 | 頭金(10%) |
|---|---|---|
| 注文住宅 | 5436万円 | 540万円 |
| 分譲戸建住宅 | 4214万円 | 420万円 |
| 分譲マンション | 5279万円 | 520万円 |
| 中古戸建住宅 | 3340万円 | 330万円 |
| 中古マンション | 2941万円 | 290万円 |
前述の通り、住宅の購入費用には物件価格に加えて仲介手数料、ローン手数料、登記費用などが必要です。これらを合わせると物件価格の10%程度の資金が必要となるでしょう。
また、住宅を購入する際は、購入価格の10%程度の頭金を準備することが一般的です。頭金を入れることで、住宅ローンの借入額を減らすことができ、返済負担を軽減できます。
これらの費用を考えた場合、住宅価格の20%程度の資金を用意するのが望ましいでしょう。例えば、4000万円の住宅を購入する場合は、諸費用と頭金の合計は800万円程度が目安です。
住宅購入資金は、比較的近い将来に使用する資金となるため、元本保障型の商品で準備していくことをおすすめします。具体的には普通預金や定期預金、後述する財形住宅貯蓄などが挙げられるでしょう。
住宅購入資金をコツコツ積み立てて準備していく人や、親族から住宅購入資金として贈与を受ける人もいるでしょう。その場合に活用したい制度が、次の2つです。
財形住宅貯蓄は、住宅購入資金やリフォーム資金を貯めることを目的とした貯蓄制度です。毎月、給与から天引きで積立していくため、計画的にまとまったお金を準備したい人に向いているでしょう。
財形住宅貯蓄を活用すれば、合計550万円まで利息が非課税になるメリットもあります。
「住宅取得資金贈与の非課税措置」とは、祖父母や親から子・孫などに対して住宅取得のための資金を贈与する場合、一定の条件を満たすことで贈与税が非課税となる制度です。この制度を利用すると、最大1000万円までの贈与が非課税扱いとなります。
この制度の適用期限は2023年12月31日までです。今後の税制改正によっては延長する可能性もあります。
住宅購入資金については、『マイホームの資金計画の考え方は?無理のない計画を立てるポイント』も参考にしてください。

教育にかかる費用としては、入学金、授業料、習い事に要する費用などが挙げられます。
教育資金は、子ども1人あたり1000万~2000万円が一般的です。教育資金の準備が上手くできず、子どもの進学を断念せざるを得ない事態になることは避けたいところです。
文部科学省が公表した資料によると、子どもが幼稚園から高校まですべて公立に通う場合は約577万円、すべて私立に通った場合は約1840万円の費用が必要です。
日本政策金融公庫が公表した資料では、国公立の大学に通った場合は約481万円、私立大学に通った場合は文系で約690万円、理系で約822万円の費用がかかる見込みです。
合計すると、すべて国公立に通った場合は約1059万円、すべて私立の場合には2500万円以上の教育資金がかかる結果となりました。
| 公立 | 私立 | |
|---|---|---|
| 幼稚園(3年間) | 49万5378円 | 92万6727円 |
| 小学校(6年間) | 211万5396円 | 1000万1694円 |
| 中学校(3年間) | 161万6397円 | 430万9095円 |
| 高等学校(3年間) | 153万8913円 | 316万3332円 |
| 大学(4年間) | 481万2000円 | ・文系689万8000円 ・理系821万6000円 |
子どもの教育にかかる費用は、1人あたり1000万円を超える金額になります。教育資金の準備は子どもが小さいうちから長い期間かけて進めていくことが重要です。
教育資金は、預貯金で準備する方法に加えて、学資保険や、投資信託のような運用商品を活用しながら進めていくのもよいでしょう。
学資保険であれば、早期で解約しなければ預貯金よりも高い利益が期待でき、契約者に万一のことが起きた場合はその後の保険料の払い込みが免除されるという安心感も得られます。
教育資金の準備が10年以上の長期間に渡る場合は、学資保険よりも投資信託のような運用商品を利用する方がより高いリターンを期待できます。さらに、NISA口座を活用すると、運用で得られた利益に対して一定額まで非課税で運用でき、効率的に資産形成ができるでしょう。
教育資金の準備に活用できる制度は、以下の通りです。
児童手当は、中学校卒業までの子どもを持つ世帯に支給されます。詳細は以下の通りです。
中学校卒業まで児童手当をすべて貯蓄した場合、約200万円の教育資金を準備することが可能です。
なお、児童手当は2024年10月に制度改正予定で、支給対象が高校生まで延長されます。
就学援助制度は、経済的な理由から学校教育を受けることが難しい生徒に対して、教育費の支援を行う制度です。小中学生の子どもがいる家庭がノートや鉛筆、給食費、修学旅行費などを支援してもらえます。
この制度を受けられるのは生活保護者(要保護者)と、教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた人(準要保護者)です。準要保護者の認定基準は市区町村ごとで異なります。
高等学校等就学支援金制度は、国立、公立、私立を問わず、高校(高専、専門学校等を含む)の教育費負担を軽減する目的で作られた制度です。高校に通う子どもがいる家庭に授業料の一部または全額が支給されます。
国公立の高校の場合は11万8800円(月額9,900円)支給され、授業料は実質0円になります。私立の場合も2020年から支給上限額が最大39万6000円(月額3万3000円)まで拡大し、授業料は実質0円になりました。
ただし、所得制限が設けられており、一定額以上の所得を超えている世帯では、満額で支給されなくなります。例えば、子ども1人の場合、国公立であれば年収が約1030万円を超えると支給対象外に、私立であれば約660万円を超えると満額支給されません。
高校生等奨学給付金とは、学校教育を受けることが難しい低所得世帯の生徒を支援するための制度です。授業料以外にかかる教科書費や学用品費、修学旅行費などの教育負担を軽減できるよう経費の一部を国が補助します。
この制度を受けられるのは、生活保護世帯、住民税所得割が非課税の世帯です。
| 国立・公立高校 | 私立高校 | |
|---|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 年額3万2300円 | 年額5万2600円 |
| 非課税世帯(全日制・第一子) | 年額11万7100円 | 年額13万7600円 |
奨学金はさまざまな企業や団体が実施していますが、とくに利用者が多いのが日本学生支援機構(JASSO)の奨学金です。
JASSOの奨学金は、「給付型」「貸与型」の2つに分かれています。給付型は返済不要の奨学金で、高校時代の成績が一定以上の学生や、特定の条件を満たす学生が対象です。貸与型は、利息がかからない「第一種」と、利息がかかる「第二種」に分かれています。
注意点として、奨学金は大学入学後に支給が開始されるため、入学金の納入には間に合いません。そのため、入学金などの入学前に支払う費用が不足している場合は、教育ローンなど別の方法をおすすめします。
教育資金については、『教育資金の貯め方はどれがおすすめ?効率よく貯蓄して負担を軽減するポイントを解説』も参考にしてください。

老後には食費や住居費、水道・光熱費といった現役時代からの継続的な費用がかかります。それに加えて、健康状態の変化に伴う医療費や介護費、定期的な健康診断などの出費も増える可能性があるでしょう。
また、生活費だけでなく老人ホームの費用や、医療・介護関連の費用、趣味やいきがいに時間を使うための費用なども考慮する必要があります。
老後に必要な生活費は、世帯状況によって異なります。参考になるのが、総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)」です。これをもとに、老後の生活費内訳を独身、夫婦のそれぞれに分けて整理しました。
| 費目 | 独身 | 夫婦 |
|---|---|---|
| 食費 | 3万7485円 | 6万7776円 |
| 光熱・水道費 | 1万4704円 | 2万2611円 |
| 日常費 | 5,956円 | 1万374円 |
| 服飾費 | 3,150円 | 5,003円 |
| 医療費 | 8,128円 | 1万5681円 |
| 交通費 | 1万4625円 | 2万8878円 |
| 教養・娯楽費 | 1万4473円 | 2万1365円 |
| その他 | 3万1872円 | 4万9430円 |
| 合計 | 13万393円 | 22万1118円 |
夫婦で年金生活を送る場合は22万円1118円の生活費がかかり、単身の場合は13万393円かかります。夫婦の場合の可処分所得は21万4426円になるため、差し引くと、毎月約7,000円の不足が生じます。一方の単身世帯は可処分所得が12万2559円で、差し引くと毎月約8,000円の不足です。
この不足額に家賃などの住居費を加えることで、毎月のおおよその不足額が算出できます。
仮に、夫婦2人で家賃5万円の賃貸で生活していくとします。この場合、毎月5万7000円、年間では68万4000円が不足します。65~90歳の35年間老後生活が続いた場合、約2400万円の老後資金が必要です。
老後資金の準備は、短い期間で行うと毎月の積立額が多くなり、家計の圧迫を招いてしまいます。そのため、長い期間をかけて準備をしていきたいところです。
老後資金の準備をする際に活用できる制度は、以下の通りです。
iDeCoとは、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受けられる私的年金制度です。公的年金とは異なり加入は任意です。この制度は、申し込みから掛金の拠出、運用商品の選定などをすべて本人が行います。そして、掛金とその運用益の合計額を60歳以降に年金として受け取る仕組みです。
iDeCoのメリットは、次の通りです。
iDeCoは掛金の全額が所得控除の対象です。会社員や公務員の場合は年末調整で、個人事業主の場合は確定申告を行うことで所得税と住民税の軽減が期待できます。さらに、65歳以降に年金として受け取る際も、「退職所得控除」「公的年金控除」といった税金優遇制度が設けられています。
ただし、iDeCoは原則65歳までは掛金を引き出すことはできません。また、市場動向によっては元本割れを起こす可能性があります。
財形年金貯蓄とは、老後資金を作ることを目的に、給与から毎月一定額を天引きして積立を行う貯蓄制度です。積み立てた資金は、60歳以降に年金として受け取ることが可能です。この制度は住宅財形貯蓄との合計で550万円まで非課税で積立できます。
注意点としては、加入できるのが54歳までとなっていることです。また、財形年金貯蓄を扱っていない会社もあるため、勤務先へ確認してください。
老後資金については、『老後資金の貯め方で年齢別のおすすめ貯蓄方法とは?』も参考にしてください。
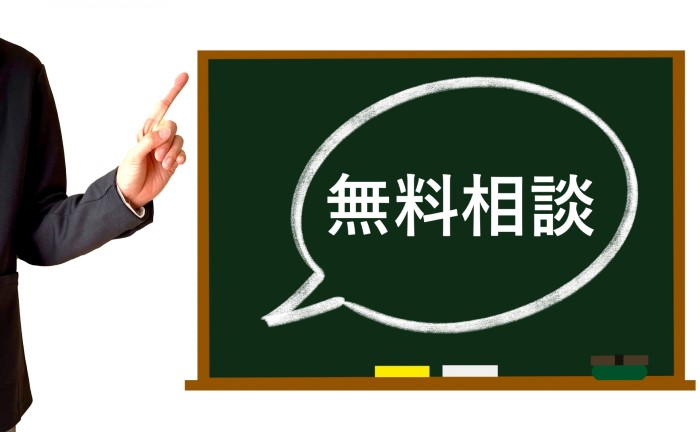
家計の状況やライフプランによっておすすめの貯蓄方法は異なります。計画的に三大費用の準備を進めていくなら、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談することをおすすめします。
FPに相談することで、個々の家計状況やライフプランに合わせて資金の準備方法をアドバイスしてくれるでしょう。ほかにも、家計の見直しや保険の見直しなど、お金に関する相談に幅広く対応してくれます。
三大資金について相談するなら、マネードクターのFP相談がおすすめです。
マネードクターには優秀なFPが多数在籍しており、何度でも無料で相談を受けられます。オンライン相談も可能で、全国からどこでも気軽に相談できます。強引な勧誘もないため、安心して利用できるでしょう。

人生の三大費用である住宅購入資金、教育資金、老後資金は、それぞれ1000万円を超える大金が必要になります。これらの資金を計画的に準備するためには、少しでも早い段階から積立や運用などを活用して、貯蓄に取り組むことが重要です。
それぞれの資金を用意するのに使える国の制度も用意されています。どのような方法で三大資金を準備すべきかわからない人は、金融の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に相談してみるのも選択肢の1つでしょう。
キーワードで記事を検索