お金を貯めたいのに貯まらないという人もいるでしょう。「もったいないお金の使い方してしまっている…」「無駄遣いがやめられない」「このままで将来は大丈夫だろうか」など悩んでいませんか?
お金が貯まらない人は、考え方や時間概念、口癖、習慣を見直すことが大事です。
この記事では、貯蓄ができない人の特徴や、貯蓄がしやすくなる方法を解説します。
- お金が貯まらない悪い習慣
- 無駄遣いを止めるコツ
- 資産形成の手段
※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
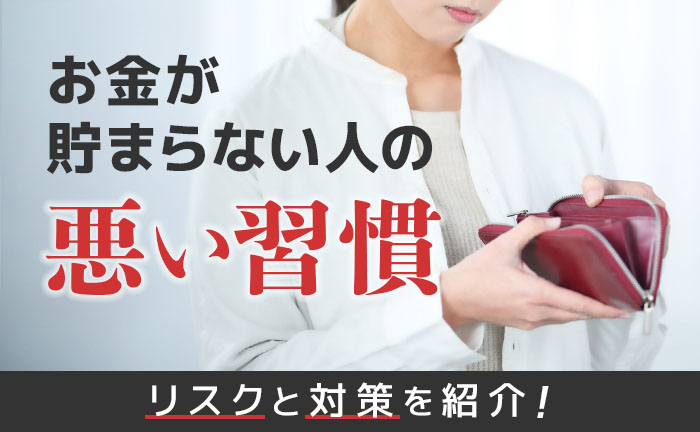
【監修】株式会社RKコンサルティング河合 克浩

一般企業、外資系金融機関を経て、現在はファイナンシャルプランナー(FP)として年間150件超のお金の相談に対応。難しく感じる経済やお金の話をわかりやすく説明することに定評がある。夢を実現するため相談者に寄り添い、人生が豊かになるサポートを心がけている。
お金を貯めたいのに貯まらないという人もいるでしょう。「もったいないお金の使い方してしまっている…」「無駄遣いがやめられない」「このままで将来は大丈夫だろうか」など悩んでいませんか?
お金が貯まらない人は、考え方や時間概念、口癖、習慣を見直すことが大事です。
この記事では、貯蓄ができない人の特徴や、貯蓄がしやすくなる方法を解説します。

お金が貯まらない人の特徴を、以下4つの項目に分けて解説します。
お金が貯まらない人の思考は、以下の通りです。
貯蓄をするためには、少なからず努力が必要です。楽しいことやラクなことばかりを優先して考え、面倒なことや努力が必要なことを後回しする人は、なかなか貯蓄を始めることができません。
また、貯蓄した方がよいことはわかっていても、「いつか必要になったときに考えればいい」と逃げるケースもあります。そうすると、病気などで急にお金が必要になったら借金するしかありません。
お金が貯まらない時間観念とは、具体的には次の通りです。
時間にルーズな人は、お金の支払いにもルーズになりがちです。
例えば、クレジットカードで買い物をすれば、支払いは先送りになりますが、期日までには引き落とし口座に入金しておかなければなりません。残高が不足して引き落としができない場合、延滞利息など余計な費用が発生することもあります。
逆に、支払い期日をきちんと管理し、支払いが滞ることがなければ余計な費用を抑えることができます。その結果、お金が貯まりやすくなるといえるでしょう。
お金が貯まらない人の口癖は、次の通りです。
「私なんかにできるわけない」などネガティブな口癖はネガティブな感情をもたらします。実際にやってみればできることでさえ、やる前からできない気分になってしまいます。
貯蓄をしたいと思っても、初めから上手くできないと「私なんかに貯蓄ができるわけない」とすぐにあきらめてしまうでしょう。お金を貯められる人は、お金を捻出しようと努力しています。「私にもできる」という口癖に変えると、お金を貯められるようになる可能性があります。
また、緊急の支払いが発生した場合、お金が貯まらない人は、「緊急の支出があったから仕方がない」とあきらめてしまいます。お金が貯まる人は、緊急で支出が発生した場合でも対応できるように、貯蓄用の口座を分けるようにしています。
お金が貯まらない習慣とは、具体的には次の通りです。
毎月赤字を出さないためには、収入の範囲内でお金を使う必要がありますが、そのためには収入と支出をきちんと把握しておかなければなりません。
例えば、クレジットカード払いやスマホ決済などの月額利用額の合計が、月々の収入より多い人は要注意です。収支が黒字になるように管理しましょう。
また、財布にレシートが大量に入っているのは、支出の管理に無頓着である証拠です。そういう人は、レシートを貯めるのをやめて、ざっくり家計簿をつけるようにするとよいでしょう。

厚生労働省の調査によると、全世帯の貯蓄平均額は1368万3000円で、貯蓄がない世帯の割合は11%です。
最も貯蓄額が多いのは「高齢者世帯」で、1603万9000円です。
一方、「児童のいる世帯」(1029万2000円)、「母子世帯」(422万5000円)など、子育て世帯は貯蓄額が少ないことがわかります。子どもの養育時期は貯蓄がしにくいことが伺えます。
| 貯金がない世帯の割合 | 貯蓄の平均額 | |
|---|---|---|
| 全世帯 | 11.0% | 1368万3000円 |
| 高齢者世帯 | 11.3% | 1603万9000円 |
| 高齢者以外の世帯 | 10.8% | 1248万4000円 |
| 児童のいる世帯 | 9.2% | 1029万2000円 |
| 母子世帯 | 22.5% | 422万5000円 |

お金が貯まらないと、どうなるのでしょうか。貯蓄がないことで起こり得るリスクは、以下の通りです。
突然、不測の事態に陥った場合に、貯蓄がないと生活ができなくなってしまうリスクがあります。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
いずれのケースも、いつ起こるかわからず、またいつでも起こり得ます。こうしたことをきっかけに離職、あるいは休職しなければならない可能性もあります。収入が得られず、貯蓄もないとなると、暮らしていくのが大変です。
貯蓄がないと、自分の思い描いたライフプラン(人生設計)を実現できないリスクがあります。
例えば、人生の節目では以下のようなライフイベントが想定されます。
どんなに節約したとしても、こうしたイベントにはお金がかかります。とりわけ、住宅購入は人生で最も大きな買い物といえるでしょう。
貯蓄がないと、諸経費が賄えないので、住宅購入ができない恐れがあります。そもそも、貯蓄がないと住宅ローンの審査に通らなかったり、希望の金額が借りられなかったりする可能性もあるでしょう。
ライフプランの作り方については、『ライフプランの作り方とは?無料テンプレートでライフプラン表を作成する方法』で解説しています。
貯蓄がないと老後の生活は年金のみでやりくりしなければなりません。年金の受給額は、年金保険料を納めた年数や収入によっても変わります。いずれにせよ、現役時代の収入ほどはもらえません。
厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、会社員だった人(厚生年金の年金受給権者)の平均年金月額は、14万4000円です。ここから税金や社会保険料を納めるので、手取りはさらに少なくなります。
また、自営業の人(国民年金の新規裁定者)の平均年金月額は、6万4000円です。手取りはさらに少なくなります。

では、どうすれば貯蓄ができるようになるのでしょうか。お金を貯める3つのコツを紹介します。
整理整頓をすることで、いま自分が持っているものを把握でき、必要なものが何かがすぐにわかるようになります。その結果、必要なものだけを買うので無駄遣いが減り、貯蓄に回す余裕が生まれます。
とはいえ、実際に商品を目にすると、必要ないものへ目移りすることもあるかもしれません。そんなときでも、目的以外のものを買わないための工夫をしましょう。
例えば、食料品なら1週間のメニューを決めて買物前に冷蔵庫の中身を確認し、必要なものを書き出して買物に行きましょう。リストにないものは見ない、買わないことを実行できれば無駄遣いを防げます。
収入よりも支出が少なくなるように管理して家計の黒字化を実現すれば、貯蓄もできるようになります。
支払い項目を使用目的ごとに分類すると、前月や前年と比較しやすいでしょう。過去より支出が増えているものを見直し、増えた原因を突き止めて節約方法を検討することで無駄遣いを防げます。
まずは、ざっくり以下の2つに分けるだけでもよいでしょう。
先取預貯金とは、毎月決まった金額を預貯金して、残った金額で生活する方法です。
例えば、20万円の収入があり、月に2万円の貯蓄をしたいと思った場合に、2万円を貯蓄口座に移しておいて、残りの18万円で生活費やそのほかの費用を賄うイメージです。
最も手軽な方法は、先取り預貯金用の財布を作り、毎月その財布へ貯蓄したい金額を入れていくことです。銀行口座を使うなら、積立定期預金などで給料の入金日に一定額を定期預金へ自動振替すれば、お金が貯まる仕組みが作れます。
ただし、初めから張り切って多額の先取り預貯金をしようとすると、あとで足りなくなって結局取り崩してしまうことになりかねません。無理のない金額から始めることがポイントです。
先取り貯金におすすめの銀行口座については、以下の記事で詳しく解説しています。
◆ 先取り貯金を成功に導くやり方!おすすめの銀行口座も紹介

いざというときに備えて確保しておきたい「緊急資金」は、一般的には生活費の3ヵ月~1年分とされます。その金額が貯まったら、老後資金など将来へ備えるためのお金は資産運用をするのもおすすめです。
具体的には、次のような方法があります。
普通預金は金利が低く、ほとんどお金は増えないですが、投資ならば効率的に増やせる可能性があります。ただし、元本割れするリスクもあるので注意してください。
NISAやiDeCoなど、税制優遇のある制度を積極的に活用して資産形成をするとよいでしょう。通常、投資から得られる利益には20.315%の税金がかかりますが、NISAやiDeCoでは非課税になります。
NISAは要件を満たした投資信託に積立投資ができます。iDeCoは、利益に税金がかからないことに加え、掛金(投資金額)も全額所得から控除されます。また、受取時にも一定の控除額があります。
iDeCoの注意点は、原則60歳までおろせないことと手数料がかかることです。金融機関によって手数料は異なるので、よく比較してから口座を開設しましょう。
NISAとiDeCoのどちらを選ぶべきか迷っている方は、『あなたはどっち派?NISA vs iDeCo!後悔しないためのポイント』をご覧ください。

お金の管理が苦手で、なかなか貯金ができないと悩んでいる方は多いのではないでしょうか?
そんな方におすすめなのが、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談です。FPは、お金に関する知識や経験が豊富な専門家であり、個々の状況に合わせたアドバイスをしてくれます。
FPに相談することで、以下のようなメリットがあります。
お金が貯まらない原因は、悪い習慣にあることが多いです。FPは、悪い習慣を洗い出し、改善するためのアドバイスをしてくれます。
FPへの相談は、無料相談を実施しているところも多くあります。まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか?
FPに相談する際の注意点や、相談内容、メリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
◆ ファイナンシャルプランナーに相談するときの注意点は?相談内容やメリットを解説

お金が貯まらない人には、現実逃避型の思考、時間の観念の欠如、ネガティブな口癖、収支の管理ができないなどの特徴があります。
万一働けなくなったときに貯蓄がないと、生活費に困る事態に陥ります。また、貯蓄がないままだと、希望する人生を送るのが困難になることもあるでしょう。
先取り貯蓄などの工夫をして将来に備えておくことをおすすめします。自分だけで解決するのが難しいときは、お金のプロであるFPに相談してみるのも1つの方法です。
キーワードで記事を検索