「幼児教育・保育無償化」により、子どもが小学校入学までの間に通う幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料・保育料が無償になりました。負担が減って助かったという家庭も多いのではないでしょうか。
「幼児教育・保育無償化」は、利用料・保育料のすべてが無償となるわけではなく、無償化の対象とならない費用も存在します。本記事では、「幼児教育・保育無償化」について詳しく解説します。
※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
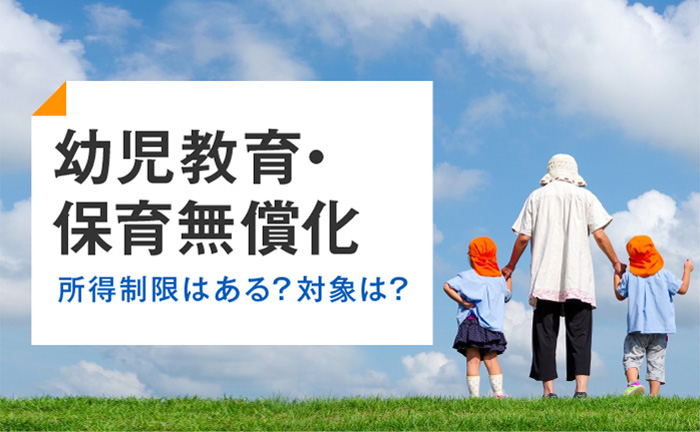
マネーFix 編集部

マネーFix 編集部は、FP有資格者や「ビジネス書」や「学習参考書」などさまざまなジャンルの編集経験者で構成されています。わかりやすく確かな情報を発信し「人生におけるお金の決断」の判断基準となる、信頼できるメディアを目指します。
「幼児教育・保育無償化」により、子どもが小学校入学までの間に通う幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料・保育料が無償になりました。負担が減って助かったという家庭も多いのではないでしょうか。
「幼児教育・保育無償化」は、利用料・保育料のすべてが無償となるわけではなく、無償化の対象とならない費用も存在します。本記事では、「幼児教育・保育無償化」について詳しく解説します。

「幼児教育・保育無償化」は、子育て世帯を応援し、幼児教育の負担を軽減する目的で、2019年10月1日より導入されました。これは、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3~5歳の子どものほか、住民税非課税世帯であれば0~2歳の子どもの利用料が無料になる制度です。
そのほか、「企業主導型保育事業」「幼稚園の預かり保育」「認可外保育施設」も無償になりますが、利用するためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
保育無償化の対象となる年齢は、原則として3~5歳の子どもです。ただし、利用する施設によっては、利用開始時期が異なる点に注意が必要です。
例えば、保育所の場合、利用できるのは3歳の誕生日を迎えた次の4月1日からとなっており、4月生まれの子どもは3歳の誕生日を迎えてから約1年間、利用を待たなければなりません。これが保育園無償化における「4月生まれが損」といわれる理由です。
幼児教育・保育無償化の対象となる施設は、以下の通りです。
幼児教育・保育無償化の対象となる施設は、「幼稚園」「保育所」「認定こども園」などです。
| 幼稚園 | 文部科学省が管轄。3~5歳の子どもを対象とし、学校教育法に基づいて保育を行う。 |
|---|---|
| 保育所 | 厚生労働省が管轄。0~5歳の子どもが利用でき、児童福祉法に基づいて運営される児童福祉施設。 |
| 認定こども園 | 内閣府が管轄。改正認定こども園法に基づいて0~5歳の子どもに教育と保育の両方を提供する。 |
幼稚園の利用料については、無償化される上限金額が月額2万5700円と定められています。
住民税非課税世帯の子どもについては、0~2歳の子どもが利用できますが、最年長の子どもを第1子とし、0~2歳の第2子は半額、第3子以降が無償で利用できます。ただし、年収360万円未満相当の世帯については、第1子の年齢は問われません。
「企業主導型保育事業」は、2016年に内閣府が開始した企業向けの助成制度です。企業によっては、従業員の柔軟な働き方をサポートするために保育施設を設置しており、そうした施設に対して設備費・運営費の助成を行うものです。
利用者は企業の従業員の子どもが中心で、原則として0~5歳の子どもが利用できます。
「障害児発達支援施設」は、未就学の子どもの発達に不安がある家庭のサポート的な役割を担う施設です。原則としては1割負担で利用できますが、幼稚園や保育所のように毎日通えるわけではありません。
無償化の対象となるのは、満3歳以降の4月1日から小学校入学前までの子どもであり、毎月の利用料が無料となります。幼稚園、保育所、認定こども園との併用も可能で、併用する場合の利用料はどちらも無料です。
保育無償化は、「認可外の保育施設」も対象となります。原則として3~5歳の子どもが利用でき、月額3万7000円までの利用料が無料となります。対象となるのは、認可外保育施設に加えて、「一時預かり事業」「病児保育事業」「ファミリーサポートセンター事業」です。また、「地域型保育事業」に認可された施設についても、無償化の対象となります。
住民税非課税世帯の場合は、0~2歳の子どもも利用でき、その際の利用額上限は4万2000円です。
幼児教育・保育の無償化に関して、施設別の無償化の上限を一覧表でまとめました。
一覧表に出てくる【〇号認定】というのは、保育の必要性や必要量を判断するための認定区分です。分け方は以下のようになります。
この認定区分で利用できる施設や「保育を必要とする事由」については、後ほど詳しく解説していきます。
| 0~2歳児クラス | 3~5歳児クラス | ||
|---|---|---|---|
| 【2号・3号認定の場合】 保育園認定こども園の保育園部分地域型保育 |
住民税非課税世帯は無料※ それ以外の世帯については、第2子が半額、第3子以降が無料 |
無料 | |
| 【1号認定の場合】 幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行した施設)認定こども園の幼稚園部分 |
通常教育時間 | ※プレ保育や満2歳児クラスなどのいわゆるプレスクールの利用料に関しては、自治体によってルールが異なりますので、各施設へお問い合わせください。 | 無料 |
| 預かり保育 | 月額1万1,300円まで無料※注1 | ||
| 幼稚園 (子ども・子育て支援新制度に未移行の施設) |
通常教育時間 | 月額2万5,700円まで無料 | |
| 預かり保育 | 月額1万1,300円まで無料※注1 | ||
| 認可外保育施設※注2 | 住民税非課税世帯は月額4万2,000円まで無料 | 月額3万7,000円まで無料 | |
| 就学前の障害児の発達支援※注3 | - | 満3歳を迎えた翌年度から小学校入学までの3年間、無料 | |
※注1:「幼稚園の預かり保育」については、月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、小さいほうが月額1万1,300円まで無料となります。なお、無償化のためには「保育の必要性」の認定を受ける必要があります(後述の「無償化のために必要な手続き」で解説します)。
※注2:「認可外保育施設」には一般的な認可外保育施設に加え、自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も含まれます。ただし、無償化の対象となるのは保育所や認定こども園等を利用できていない方で、なおかつ「保育の必要性」の認定を受けた方のみとなります。
※注3:「就学前の障害児の発達支援」とは児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設を指します。幼稚園(新制度)、保育所、認定こども園などと併用(併行通園)する場合は、両方とも無料になります。
1号認定を受け、幼稚園やこども園(幼稚園部分)に通う場合、3~5歳児クラスの3年保育が基本となります。
つまり、3歳になった翌年度から幼稚園の3歳児クラスに入園するのが一般的です。
しかし、学校教育法第26条で「幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児」と定められているため、3歳になれば幼稚園に入園する資格があります。
そのため、年度途中でも満3歳の誕生日を迎えた日以降に3歳児クラスに入園することができます*。
翌年度は再度3歳児クラスに入り直すため、3歳児クラスを2年、4歳児クラスと5歳児クラスを1年ずつで4年保育と呼びます。
幼稚園の場合は4年保育も無償化の対象となり、満3歳から利用料が無料となります。
3歳児クラスの受け入れ状況により入園ができないケースがあるため、入園を希望している園に定員の空き状況を問い合わせてみましょう。
一方、プレ保育(慣らし保育)や満2歳児クラス(未就園児クラス)など、3歳の誕生日を迎える以前から幼稚園に通う場合については、一律に無償化の対象とはなりません。
施設が一時預かり事業や認可外保育施設としての届出を出していることや、利用者が住民税非課税世帯であること、保育の必要性が認定されていることなど、細かな条件を満たす必要があります。
さらに、利用実態に応じて無償化の対象とするかどうかの判断が自治体によって異なるため、各施設へお問い合わせください。
また、保育園、認定こども園、地域型保育の0~2歳児クラスに関しては、世帯年収に関わらず「第2子が半額、第3子以降は無料」とされていますが、子どもの人数のカウント方法には下記のようなルールがあります。
| 世帯年収が下記に相当する場合 | 3号認定 保育園、認定こども園(保育園部分)、地域型保育 |
|---|---|
| 年収360万円未満 | 年齢に関わらず、世帯の子ども全員をカウントする |
| 年収360万円以上 | 小学校1年生以上の子どもはカウントしない |
なお、企業主導型保育事業に関しては、年齢に応じて「標準的な利用料」が減額されます。
| 0歳児クラス | 1・2歳児クラス | 3歳児クラス | 4歳児クラス |
|---|---|---|---|
| 3万7,100円 | 3万7,000円 | 2万6,600円 | 2万3,100円 |

幼児教育・保育無償化の制度の利用にあたっては、所得制限はありません。該当する子どもがいれば、どの家庭でも利用できます。

利用料が無料になるとはいえ、実費として徴収される費用は無償化の対象外です。具体的には、以下の費用が当てはまります。
ただし、年収360万円未満相当の世帯の子どもたちや、すべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食費(おかず・おやつ代)が免除されます。

幼稚園や保育所を利用する場合、申請は不要です。ただし、幼稚園の預かり保育を利用する場合は、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。預かり保育の利用については、月内の預かり保育日数に450円を乗じた額と、預かり保育利用料の少ない方が月額1万1,300円まで無料となります。
また、認可外保育施設等で無償化の対象になるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性の認定」を得るには、就労等の要件を満たす必要があります。詳細は、自治体の窓口で確認しましょう。
幼稚園(新制度に移行した施設)、保育園、認定こども園、地域型保育施設を利用するには、お住まいの市区町村からの認定が必要です。すでに認定を受けている場合は新たに無償化の手続きは必要ありません。
子どもの年齢や各家庭の保育を必要とする事由の有無によって、1号・2号・3号に区分され、その認定区分によって、利用できる施設の種類が変わります。
| 認定区分 | 1号認定 (教育標準時間認定) |
2号認定 (保育認定) |
3号認定 (保育認定) |
|---|---|---|---|
| 子どもの年齢 | 3~5歳 | 3~5歳 | 0~2歳 |
| 保育を必要とする事由 | なし | あり | あり |
| 利用できる施設 | 幼稚園(新制度) 認定こども園 |
保育園 認定こども園 |
保育園 認定こども園 地域型保育 |
利用できる施設別に整理すると、下記のとおりになります
| 幼稚園 | 保育園 | 認定こども園 | 地域型保育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管轄 | 文部科学省 | 厚生労働省 | 内閣府 | 厚生労働省 | ||
| 子どもの年齢 | 3~5歳 | 0~5歳 | 3~5歳 | 0~2歳 | 0~2歳 | |
| 認定区分 | 1号認定 | 2号認定 3号認定 |
1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | 3号認定 |
| 開所時間 | 4時間 程度 |
8~11時間 程度 |
4時間 程度 |
8~11時間 程度 |
8~11時間 程度 |
|
| 特徴 | 小学校以降の教育の基礎を作るための幼児教育を行う学校施設 | 家庭で保育できない親に代わって保育を行う施設 | 幼稚園と保育所の特長を併せ持つ地域の子育て支援を行う (園に通っていなくても子育て相談や親子の交流の場などに参加できる) |
少人数単位で保育を行う施設―家庭的保育 (保育ママ)―小規模保育―事業所内保育―居宅訪問型保育 |
||
2号、3号認定を取得するには、両親がともに以下の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当することが必要です。
両親がともに「就労」に該当するパターン(共働き)以外にも、妊娠・出産や介護、就学などさまざまな理由が認められています。
就労は「就労証明書」や「就労状況申告書」、妊娠出産は「母子手帳の写し」など、それぞれ証明書が必要な場合があるので、お住まいの市区町村にご確認ください。
2号または3号の認定を受けるとさらに「保育の必要量(保護者の就労状況など)」によって、保育標準時間と保育短時間に認定区分が分かれます。
保育標準時間に認定されると最長11時間まで、保育短時間に認定されると最長8時間まで施設を利用することができます。
認定された預かり時間や施設の定める通常保育時間を超えて利用する場合には、延長保育料がかかり、この延長保育料は無償化の対象とはなりません。
| 認定区分 | 保育の必要量 | 預かり時間 |
|---|---|---|
| 保育標準時間認定 | 1ヶ月あたり120時間以上の労働 (フルタイムを想定) |
最長11時間 |
| 保育短時間認定 | 1ヶ月あたり48時間(64時間)~ 120時間未満の労働(パートタイムを想定) |
最長8時間 |
保育短時間が認められる就労時間の下限は1ヶ月あたり48~64時間の範囲で定められています。
市区町村によって異なるため確認してみましょう。
下記の施設を利用する場合、無償化のために手続きが必要です。
・企業主導型保育事業(0~2歳児クラスで、住民税非課税世帯の場合)
・認可外保育施設
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用している場合、幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用している場合は、園から配付された申請書類を園に提出します。
企業主導型保育事業に関しては、施設によって申請方法が異なるため、利用施設の指示に従って手続きを行ってください。
認可外保育施設を利用している場合は、申請書類を直接市区町村に提出します。
ファイナンシャルプランナーは、お金の専門家です。お客様のライフプランに沿った総合的なアドバイスを提供します。
マネードクターの無料相談では、お客様の現在の家計状況を分析し、キャッシュフロー表を作成、将来のライフプランを提案します。
家計の見直し、保険の見直し、教育資金、住宅ローンなど、あらゆるお金の不安を解消します。
お金の専門家に相談して、あなただけの「お金の羅針盤」を見つけ、幸せな未来を築きましょう!

幼児教育・保育無償化の制度は、子どもの保育費の負担軽減に役立つ制度です。まずは、利用する施設が制度に対応しているかどうかを調べましょう。該当する場合は、利用申請の手続きを行います。
認定こども園などの各施設や自治体に問い合わせると、申請のために必要な書類・情報などを教えてくれます。「保育の必要性の認定」については、さまざまな要件を満たす必要があります。わからないことがあったら早めに確認し、かしこく制度を利用しましょう。
将来必要な教育資金を貯めるために家計の見直しを検討している方は、ファイナンシャル・プランナー(FP)へ相談してみてはいかがでしょうか。下記よりお気軽にお問い合わせください。
キーワードで記事を検索